米中もし戦わば 戦争の地政学
「米中もし戦わば 戦争の地政学」(著:ピーター・ナヴァロ 翻訳:赤根洋子)を読みました。
本書によってトランプの対中政策が正しいことを再確認しました。
著者がトランプ政権に提言をしている一人であることから、トランプ政権の政策と本書の内容が近いのは当然のことかもしれませんが、いずれにしてもトランプとナヴァロの対中戦略には賛同です。
本書にはアメリカの戦略が書かれているわけですが、言うまでもなく米中関係の先行きは日本の行く末にも大きな影響を与えます。
当然、日本のことも考えながら読み進めるわけですが、弱みを握られているのか積極的なのか分かりませんが、改めて日本の親中派の活動に危機感を覚えました。
さらに、情報戦に洗脳・惑わされているのではないかと思えるような国民の考え方には失望感を抱きました。
このままだと日本は終わりかもしれませんが、政治家・官僚・マスコミ・経済人・文化人等だけでなく
日本人自体がこれでは・・・、もはや神にすがるしかないのかもしれません。
「米中もし戦わば 戦争の地政学」(著:ピーター・ナヴァロ 翻訳:赤根洋子)を紹介するために、以下に目次や目を留めた項目をコピペさせていただきます。
興味が湧いて、他も読んでみたいと思ったら、是非とも本書を手にしていただければと思います。
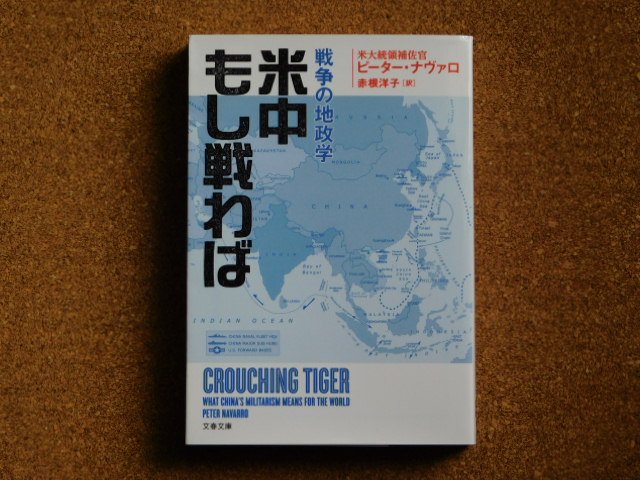
目次
■第一部 中国は何を狙っているのか?
第1章 米中戦争が起きる確率 / 第2章 屈辱の一〇〇年間 / 第3章 なぜマラッカ海峡にこだわるのか? / 第4章 禁輸措置大国アメリカ / 第5章 中国共産党の武力侵略
■第二部 どれだけの軍事力を持っているのか?
第6章 軍事費の真実 / 第7章 第一列島線と第二列島線 / 第8章 「空母キラー」の衝撃 / 第9章 地下の万里の長城 / 第10章 マッハ10の新型ミサイル / 第11章 機雷による海上封鎖 / 第12章 深海に潜む核兵器 / 第13章 ヨーロッパの最新軍事技術を手に入れる / 第14章 小型艦が空母戦闘群を襲う / 第15章 第五世代戦闘機の実力 / 第16章 宇宙戦争 / 第17章 サイバー戦争 / 第18章 国際世論の操作 / 第19章 「非対称兵器」が勝負を分ける
■第三部 引き金となるのはどこか?
第20章 台湾という不沈空母 / 第21章 問題児・北朝鮮 / 第22章 尖閣諸島の危機 / 第23章 ベトナムの西沙諸島 / 第24章 南シナ海の「九段線」 / 第25章 排他的経済水域の領海化 / 26章 水不足のインド / 第27章 火の付いたナショナリズム / 第28章 地方官僚の暴走 / 第29章 中露軍事同盟の成立
■第四部 戦場では何が起きるのか?
第30章 質の米軍vs. 量の中国軍 / 第31章 米軍基地は機能するのか? / 第32章 中国本土への攻撃 / 第33章 海上封鎖の実行 / 第34章 どんな「勝利」が待っているのか?
■第五部 交渉の余地はあるのか?
第35章 米軍はアジアから撤退すべきか? / 第36章 中国の経済成長は何をもたらすのか? / 第37章 貿易の拡大で戦争は防げるのか? / 第38章 核抑止力は本当に働くのか? / 第39章 中国との対話は可能か? / 第40章 「大取引」で平和は訪れるのか?
■第六部 力による平和への道
第41章 「戦わずして勝つ」唯一の方法 / 第42章 経済力による平和 / 第43章 軍事力による平和 / 第44章 同盟国を守り抜く / 第45章 中国の脅威を直視する
■解説 飯田将史(防衛省防衛研究所 主任研究官) 「日本の安全をどう守るのか」
第6章 軍事費の真実
問題;軍事費が多いほうを選べ。
①中国
②アメリカ
本書が中国の急激な軍事力増強の危険性にたびたび言及していることから、「中国」と答えたくなる読者が多いのではないかと思う。ところが予想に反して、正解は2の「アメリカ」である。
たしかに中国は急速に軍備を拡張しているが、軍事費の総額でも軍事費がGDPに占める割合でも、アメリカはいまだに中国を遥かに上回っている。
軍事費総額では、中国の年間軍事費は急速に増加して2,000億ドルを超える勢いだが、アメリカの軍事費はその3倍以上である。同時に、過去10年間の中国の軍事費はそのGDPのわずか2%を占めるに過ぎないが、アメリカのそれは4%に近い。
何てことだ。戦争したがっているのはどっちなんだろうか。
なぜ中国は軍事費を低く抑えられるのか
実際、「アメリカの軍事費は中国を大幅に上回っている」という話は、中国の脅威を過小評価するための論拠としてよく持ち出される。しかし、この話にはいくつか批判的考察を加える必要がある。
第一に、軍事費総額を直接比較すること自体が間違いの元である。アメリカ軍が世界規模で戦力投射しなければならないのに対して、中国軍はアジア地域での戦力投射に焦点を絞っている。これを兵器という文脈に当てはめると、アメリカの納税者は空母10隻の費用を負担しなければならないが、アジア地域のパトロールに派遣されている空母はそのうちの数隻でしかないということである。
第二に、中国における軍事費1ドルはアメリカにおける軍事費1ドルよりも遥かに使い出がある。それはなぜか。
まず、中国軍兵士の人件費は、アメリカ軍兵士の人件費よりも遥かに安い。加えて、兵器の製造コストも中国のほうが確実に安い。その理由は、労働力が安価だからというだけではない。そこには、環境への配慮や労働者保護に費用をかけないで済むからという理由もある。中国では大気や水の汚染が進み、労働環境は非常に危険だが、自動車や家庭電化製品からミサイルや潜水艦まで、あらゆるものの製造コストはずっと安く抑えられるのである。
中国がコスト面で有利な理由には、次のような不愉快な事情もある。中国は、軍事研究や新兵器システム開発にほとんど費用をかける必要がないのである。その重要な理由の一つは、最新兵器の設計をペンタゴンや民間防衛企業から盗み出す中国人ハッカーのスキルの高さである。もう一つの理由としては、中国が外国から購入したテクノロジーの多くを不法にリバースエンジニアリング(※製品を分解したり動作を観察することによって、技術を模倣すること)していることが挙げられる。
中国によるリバースエンジニアリングの最大の被害者は、アメリカではなくロシアである。中国はロシアから最新鋭の戦闘機スホーイ(Su-27)を購入してその模倣品を製造し、瞬く間に世界市場に売り出してロシアの売り上げに打撃を与えた。
空母艦載戦闘機Su-33をもコピーし、それを非難されたとき、中国側は、「スホーイをコピーした我が国のJ-15戦闘機は、実はオリジナルよりも性能がいい」という趣旨の噴飯物の答弁で対抗した(中国側はその滑稽さに気づいていなかったようだが)。だが、コピーのほうがオリジナルよりも高性能だという中国側の主張はたしかに正しい。そして、これこそ競合国が直面する問題の一つである。中国は他国のテクノロジーを盗む能力だけでなく、それを改良する能力をも有しているのである。
こうした事実を踏まえると、中国の軍事費がアメリカに遠く及ばないように見えるからという理由で安心するのは間違いだということが分かる。GDPの成長率において中国はアメリカを大きく上回り続け、アメリカ経済は低迷を続けているため、米中の軍事費のグラフがそう遠くない将来に交差するものと思われるだけになおさらである。
実際、軍事費というパズルをよくよく見れば、中国がアメリカよりもずっと少ない金額で軍事力を増強できていることは安心材料どころではないことが分かる。中国の急速な軍備拡張を可能にしている経済発展について考えると、次のような、はっとさせられる疑問が湧いてくる。かつてアメリカが第一次大戦時にドイツ帝国に対して、第二次大戦時にナチス・ドイツと大日本帝国に対して、そして冷戦時にソ連に対して発揮した強みを、いずれ中国がアメリカに対して発揮するようになるのだろうか。つまり、中国はその製造能力の優位性を利用してアメリカとの戦争に勝てるようになるのだろうか、という疑問である。
第二次大戦は国の経済力で勝負がついていた
中国の台頭と成長の戦略的な意味を、次の歴史的事実に照らして考えてみよう。第二次大戦勃発時、ナチス・ドイツと大日本帝国を合わせた経済力はアメリカ一国の半分に過ぎなかった。だから、工場や労働者の数という理由だけでも、アメリカは戦略的に有利な立場にあった。
実際、第二次大戦当時の統計を見ると、経済力と軍事力の間に驚くほどの相関関係があったことが分かる。アメリカが30万機の軍用機を動員できたのに対して、ドイツと日本を合わせてもその数は20万機に満たなかった。アメリカが海上の前線に配置した駆逐艦の数がおよそ350隻だったのに対して日本は63隻、陸上の前線では、アメリカ軍の戦車の数が7万台以上だったのに対してドイツ軍は4万5000台を下回っていた。
だから、第二次大戦の勝利は、勇敢に戦ったアメリカの陸・海・空軍兵士のおかげには違いないが、彼等は、敵に破壊される数を遥かに上回るペースで戦車や飛行機や船を生産することのできる祖国の工場に支えられていたということである。
これは、プロイセンの偉大な戦術家カール・フォン・クラウゼヴィッツがいみじくも「代数による戦争」と呼んだ必勝法が正しいことを決定的に証明した実例である。だが、アメリカに勝利をもたらしたこれらの工場の多くは今ではシャッターを下ろし、成都や重慶や深圳といった都市に移転してしまった。
「中国は、ソ連とはまったく異なるタイプの軍事的競合国である」
崩壊した帝国としてのソ連の運命にここで言及しておくことは、今後の米中の軍事関係を考える上で適切かもしれない。1980年代の冷戦時代、ロナルド・レーガン大統領は戦略防衛構想に基づいてソ連を打倒すべく、きわめて攻撃的な「スター・ウォーズ」戦略を採用した。しかし、レーガンはソ連を実戦によって決定的に打ち負かそうと考えていたわけではなかった。彼の真の計画は、ソ連をカネのかかる軍拡競争に誘い込み、「悪の帝国」を経済的に破綻させることだった。
1980年代にアメリカの軍事費及び財政赤字が急増したため、レーガンのタカ派的戦略は繰り返し非難を浴びた。だが、レーガンの戦略は結局、親レーガン派の最も楽観的な予想をも上回る成功を収めた。当時のGDPの成長率と軍事費の統計を見るとその理由が分かる。
レーガンと一緒に軍拡ゲームを続けるため、ソ連は軍事費を大幅に増額せざるを得なかった。軍事費がGDPに占める割合は40%にもなった、と分析する研究者もいるほどである。ソ連が最終的に財政破綻し、崩壊へと至った原因は、この過重な軍事費負担とそれに付随して生じた軍事以外の経済部門の軽視だった。このソ連の没落を中国の台頭と比較して、プリンストン大学教授アーロン・フリードバーグは次のように述べている。
中国は、ソ連とはまったく異なるタイプの軍事的競合国である。イデオロギー上の理由から、ソ連は国際貿易システムに参入しなかったし、国際的な技術システムからも距離を置いて何もかも自国だけで賄おうとした。中国は、これとは正反対の戦略を取っている。中国は世界経済に進出し、世界の科学技術システムにできるだけ深く参入しようとしている。遥かに賢明なこの戦略が中国に、遥かに迅速な台頭を可能にしている。
「中国はソ連とは違う」というこの意見に賛同し、ブルッキングス研究所のマイケル・オハンロンは次のように言う。
中国の成長率は7%ないし6%にまで減速するかもしれないが、それでも世界最高水準の経済成長率だし、中国は世界第一の製造大国である。そして、この傾向はいささかも減速していない。だから、何とか努力すれば軍艦や戦闘機の製造数で中国を上回ることができるという考えは、せいぜいのところ短期的で不完全な解決策である。
はっとさせられるようなこの発言には、偉大なアイスホッケー選手ウェイン・グレツキーのアドバイス「パックが今ある場所ではなく、これから行く場所へ滑っていけ」に通じるところがある。
このままでは、アメリカは中国に(少なくともアジア地域で)「降参」と言わざるを得なくなるかもしれない。そこで、次章では、「その目標を達成するために、中国は今後数十年間にどんな戦略を取るだろうか」という問題を取り上げることにしよう。
第18章 国際世論の操作
問題:21世紀において中国がその領土的野望を前進させるのにより効果的だったものを選べ。
①駆逐艦、戦闘機、弾道ミサイルなどの「殺傷(キネティック)兵器」
②心理戦、メディア戦、法律戦といった「非殺傷(ノンキネティック)兵器」
「ペンは剣よりも強し」というが、文字どおり「三種類の戦い方」を意味する中国の「三戦」も、弾道・巡航ミサイルや空母艦隊などのどんな兵器よりも、中国の領土的野望の実現にずっと効果的だと判明するかもしれない。「三戦」は実際に非常に効果的だし、しかも今後エスカレートしていく可能性が非常に高いため、これについてもっと深く理解しておくことはわれわれの推理作業にとって重要である。
「三戦」が重要な戦闘能力として初めて公式に認められたのは、中国中央軍事委員会と中国共産党が正式にこの戦略を承認した2003年のことである。
ケンブリッジ大学教授で以前ホワイトハウスの顧問を務めていたステファン・ハルパーの『中国 ―― 三戦』は、三戦に関する最も信頼の置ける論文である。ペンタゴンへの報告書の中で、ハルパーは三戦を、「別の手段で戦争を構成する、動的・三次元的戦闘プロセス」と呼んでいる。
領土問題解決のためにキネティックな軍事力を使用することがますます困難になっている現代において、三戦はノンキネティックな攻撃形態としてきわめて効果的だ、とハルパーは言う(※「キネティック」とは本来「運動の、動的な」を意味する語だが、軍事用語として「殺傷能力のある」という意味でも使われる。たとえば「キネティック・アクション」とは「殺す」の婉曲語)。ロシアのウクライナヘの軍事介入で明らかになったように、違法な軍事力の展開は、直ちに国際社会からの非難とともに貿易相手国からの経済制裁その他の制裁を招くことになる。
景気低迷に苦しむ日本を威圧する「心理戦」
それでは、三戦、つまり三つの戦い方とはいったい何だろうか。一つ目は「心理戦」であり、その目的は、相手国とその一般国民を脅したり混乱させたり、あるいはその他の方法でショックを与え、反撃の意志をくじくことである。ハルパーは中国の心理戦の方法について、「外交圧力、風評、嘘、嫌がらせを使って不快感を表明し、覇権を主張し、威嚇する」と述べている。さらに、「中国は経済を効果的に利用する」とも述べている。
たとえば、中国は、日本へのレアアースの輸出を規制したり日本への観光旅行を禁止したりすることによって、景気低迷に苦しむ日本を威圧し、尖閣諸島に対する領土要求を認めさせようとしている。同様に、スカボロー礁やセカンド・トーマス礁といった紛争地域を取り囲むように大量の民間船を送り込んでいるのは、圧倒的な数を頼んでフィリピンを恫喝し、フィリピン軍に退却を余儀なくさせるためである。このようなやり方は「包心菜(キャベツ)戦略」と呼ばれる。
三戦の二つ目は「メディア戦」である。その目的は、国内外の世論を誘導し、欺されやすいメディア視聴者に中国側のストーリーを受け入れさせることである。ステファン・ハルパーは「現代の戦争を制するのは最高の兵器ではなく、最高のストーリーなのだ」と述べているが、中国のメディア戦はまさにこの格言に従っている。
ヘリテージ財団のディーン・チェンはこのようなメディア戦を、「感じ方と考え方に長期的影響を与えることを目的とした、持続的に進行する活動」と評している。ハルパーが述べているように、その目的は「味方の士気を維持し、国内外の世論の支持を取りつけ、敵の戦意をくじき、敵の状況判断を変更させること」である。
中国は書籍、映画、雑誌、インターネットなどさまざまな媒体を通じてメディア戦をおこなっているが、中でもテレビに力を入れ、大金を投じて中国中央電視台(CCTV)を国際的宣伝部隊に造り替えた。中国の政治と軍事の指導者たちが三戦を初めて正式に承認した2003年、CCTVは、国際世論の支持をBBCやCNNと直接張り合うため、24時間インチキニュースチャンネルの放送を開始した。
2011年、中国はメディア戦への出資金を大幅にアップし、CCTVはワシントンDCに立派なスタジオを開設した。このスタジオには、「白い顔」や「黒い顔」のアメリカ人アンカーやリポーターがうようよしている。こうしたニセCNNニュースを流す利点は、本物のニュースにプロパガンダを混ぜ込み、4000万人以上ものアメリカ人視聴者、及び世界中の何千万人、何億人という視聴者に送り届けられることである。
南沙諸島やセカンド・トーマス礁をめぐって中国とフィリピンの間でさらにまた問題が起きれば、CCTVがすぐに現れ、たいていは西側メディアがそのニュースを知る前に中国側のストーリーを広める。同様に、尖閣諸島をめぐって緊張が高まれば、CCTVはすぐに、どんな衝突やエスカレーションも「日本の右翼」のせいにして激しく非難する。
「三戦」の最後は「法律戦」である。法律戦における中国の戦略は、現行の法的枠組みの中で国際秩序のルールを中国の都合のいいように曲げる、あるいは書き換えることである。
たとえば、「国連海洋法条約に明示されているように、中国は200海里の排他的経済水域内の航行の自由を制限することができる」という中国側の主張について考えてみよう。実は、現行の海洋法条約にそんなことは一言も書かれていない。この点について、条約はかなり明快に規定している。だが、中国は「法的根拠がある」という嘘をこれまで繰り返し主張してきた。まさに、「嘘も繰り返せば真実になる」の精神である。
攻撃的「法律戦」には、インチキ地図を使って領有権を正当化するという方法もある。あるコメンテーターは、この戦術に「地図戦」というあだ名を付けた。たとえば、2012年、中国は南シナ海の紛争地域の多くを中国固有の領土として描いてある地図をパスポートの内側に掲載し、近隣アジア諸国の怒りを買った。中国は地図をこのように巧みに使い、領有権の主張を強化しようとしたのである。そして、三戦は続行される。
軍事力を行使せずに領土拡大
大局的見地からこの三戦という問題を見てみよう。ステファン・ハルパーやディーン・チェンなど専門家の意見が正しいとすれば、中国が現在おこなっている法律戦、メディア戦、心理戦は、「領土拡大・現状変更」を目標とする中国の新たな攻撃形態である。この観点から見ると、現代における三戦の利点は、以前ならキネティツクな手段によってしか実現できなかった目標を達成するための、新しい手段を提供しているという点である。さらに、三戦は互いに結びついて非常に高い相乗効果を生み出す。
第19章 「非対称兵器」が勝負を分ける
問題:中国の軍事戦略及び軍事能力は、アジアの平和と安定にとって脅威になるか?
①なる
②ならない
第二部の最後に、これまでに明らかになったことを簡単にまとめておきたい。中国の意図、戦略、新たに獲得した能力を検討した結果、われわれの推理作業がどこまで進んだかを振り返って見よう。
まず、中国の軍事的意図について言えば、国土及び国際通商路の防衛という正当な願望と、領土、領空、領海、海上交通路の拡大という、正当とはとても言えない攻撃的な願望とが不可分に結びついているように思われる。
たとえば、東シナ海・南シナ海を意のままにすることに成功すれば、中国の国土及び通商路防衛能力は大いに向上するだろう。だが、こうした防衛上のメリットは、日本やフィリピン、ベトナムなど自分よりも軍事力で劣る近隣諸国に対する攻撃的行動によってしか達成できない。
同様に、東シナ海の尖閣諸島や南シナ海のセカンド・トーマス礁を攻撃的行動によって奪取することに成功すれば、そこに駐屯地や滑走路やレーダー施設といった軍事施設を建設することによって防衛力を強化することができる。
さらに、このような領土拡大によって、中国は大量の石油や天然ガスを手に入れることにもなり、それはペルシヤ湾の石油への依存度を減らすことから「マラッカ・ジレンマ」の解決にもつながる。だが、このような防衛力向上はやはり攻撃的な現状変更行為によってしか達成できない。
経済的動機、膨張主義的動機、国家安全保障上の動機がこのように重なり合っていること、防衛と攻撃の境界がはっきりしないことを考えると、現在の状況の説明として、少なくとも一つの妥当な解釈が浮かび上がってくる。中国の軍事力は、最初は国土と自国の経済的利益を守るための純粋に防衛的な理由で増強されたのかもしれないが、今では近代的で攻撃的な軍事力へと危険な変貌を遂げ、いずれは世界的に展開する能力を持つようになるだろう。
中国の軍事能力については、中国の保有する兵器がお決まりの通常兵器(機雷、ミサイル、空母戦闘群、戦闘機)だけではないことをこれまで見てきた。中国は、アジアのパワーバランスをラジカルに変える恐れのある、破壊力のきわめて大きい軍事技術の数々をも保有している。
対艦弾道ミサイル(空母キラー)やさまざまな種類の対人工衛星兵器、F-35戦闘機などの戦闘機を墜落させたり、さらには航空管制や銀行ネットワークや地下鉄システムなど敵国内の民間施設を麻痺させる能力をも持つコンピュータ・マルウェアがそれである。
中国は間違いなく、アジアの平和と安定にとって脅威となる
このような状況から明らかに導き出される結論は、ほぼ間違いなく現状変更意図を持っている中国の軍事力が増大し続けるにつれて、紛争が起きる可能性も増大し続けるということである。言い換えれば、本章冒頭の問題の正解は、「中国の軍事戦略及び軍事能力は、アジアの平和と安定にとって脅威になる」でほぼ決まりだということである。
したがって、次に問題になるのは、「衝突の引き金や導火線や火種になりそうなものは何か」である。さらに具体的に言えば、中国と多くの国々(日本、インド、フィリピン、ベトナム、韓国、アメリカ、台湾)のいずれかとの間で衝突が起きるきっかけとなりそうな状況はどれだろう、ということである。
第三部では、そのような状況とそこから予想される展開を見ていく。第二部の最後に、チェスの元世界チャンピオン、ガルリ・カスパロフの警告を引用しておこう。
自由主義世界の多くの政治家や評論家は、自国が戦争状態にあることを認めなければ敗北を避けられると考えているように見える。だが、戦争の現実を無視すれば、訓練された兵士ではなく、より多くの罪もない人々を前線に立たせることになるのだ。
第22章 尖閣諸島の危機
問題:日本は今後、日米安全保障条約についてどんな判断を下し、中国にどう対処するかを選べ。
①弱体化した、もしくは決断力に欠けるアメリカはもう日本を守ってくれないと判断し、自前の核兵器を開発して独自路線を模索する ――「日本核武装」シナリオ
②弱体化した、もしくは決断力に欠けるアメリカはもう日本を守ってくれないと判断し、中国の覇権を受け入れて中国主導のアジア経済圏の一員となる ――「中国に乗り換える」シナリオ
③アメリカは今後も条約の義務を守り、日本に核の傘を提供し続けると信じ、通常戦力及びミサイル防衛能力を増強しつつ、アメリカやその他の同盟諸国との経済的結びつきを強化する ――「ぶれない同盟国」シナリオ
勃興する中国の挑戦に対して、あるいは没落するアメリカに対して、日本がどのような反応を見せるかは、当然のことながら、アジアの将来の戦争と平和に重大な影響を与えるだろう。日本が「核武装」すれば、アジアにおける核戦争のリスクは間違いなく高まるだろう。
日本が「乗り換え」て中国と同盟を結び、アメリカと敵対すれば、それは「大東亜共栄圏」と第二次大戦の再演となるだろう。ただし、結果と勝者はまったく違うものになるかもしれない。「ぶれない同盟国」シナリオでさえ、戦争にならないという保証はない。強固な同盟関係は中国を刺激し、すでにお馴染みの「安全保障のジレンマ」によって中国がさらに軍備拡張に励むだろうからである。それでは、帝国主義国家としての過去と、平和主義国家としての現在と、きわめて不透明な未来との間で進退窮まっている世界唯一の被爆国・日本は、どんな行動を取ると予想されるだろうか。
日米安保の義務を米国は遂行できなくなってきている
日本が進むべき道を選ぶ際に最初に障害となる厄介な真実は、日本が経済的に運命を共にしている中国という国の国民が根深い反日感情を抱いているということである。これは驚くには当たらない。中国の若い世代は、大日本帝国の残虐行為をことさら強調する歴史教科書や、年間200本も製作される反日映画によって常に反日を教え込まれて育ったのだから。
これと同程度に厄介な真実は、日本が安全保障上の運命を共にしているアメリカという国で、またぞろ伝統の新孤立主義が目立ってきたことである。これも驚くには当たらない。日本のような忠実な同盟国に対して安全保障条約の義務を遂行する上で、アメリカが現在直面している問題には、経済的な面と政治的な面の両方があり、この二つは複雑に絡み合っているからである。
経済的な面について言えば、アメリカはその慢性的な財政赤字を国防費の大幅削減によって解消しようとしている。国防予算削減に反対する声はほとんどない。アメリカ史上最長の二つの戦争、すなわちアフガニスタン及びイラクでの戦争に律儀に資金を提供し続けた結果、アメリカ国民は戦争に疲れ切っている。
政治的な面について言えば、アフガニスタンとイラクでの戦争をもっといい形で終わらせることができていれば、アメリカの納税者も「アジア重視政策」への資金提供にもっと前向きだったかもしれない。だが、イラクヘの派兵が失敗に終わり、アフガニスタンでタリバンが息を吹き返した今、アメリカ人の多くが(経済的余裕のない人々は特に)とにかくうんざりしてしまっている。
したがってアメリカは、少なくとも日本から見れば、もはや軍事的義務を果たす経済力のない、政治的に無気力な、国防予算の優先順位も正しく決められない国だということになる。だから、たとえアメリカの大統領や国務長官や統合参謀本部議長がアジアの同盟諸国に対する義務を必ず果たすと約束しても、当然のことながら、日本や韓国やフィリピンの政治指導者はその言葉に疑念を持つ。
有事の際、米国は本当に核の傘を日本に提供するのか?
それでは、最重要の同盟国にして守護者たるアメリカの約束を信じられなくなった日本は、今後どんな行動に出るだろうか。日本が中国の脅威を実感する機会が多くなっているだけに、これは特に重大な問題である。
実際、中国軍が自衛隊を挑発する行為は日常茶飯事と化している。軍艦で日本の領海すれすれを航行したり、戦闘機や偵察機で日本の領空を侵犯したり、民間船や準軍事船舶の大船団を使って尖閣諸島を取り囲んだり(包心菜作戦)、「軍国主義の復活」などと日本を非難する執拗なメディア戦を仕掛けたりして、中国はあの手この手でこの地域の緊張を高めている。
「日本が最終的にどんな道を選択するか」という問題を「日本が中国に攻撃されたとき、アメリカは安全保障条約という約束を守るだろうか」という問題から切り離せないのは、まさに日中間のこの緊張状態のせいである。だが、日本のこの選択について考える際には、日米安全保障条約に基づいてアメリカが履行しなければならない義務の真の範囲を正しく理解することが必須である。
ここで本当に重要なのは、この義務が、中国が尖閣諸島に侵攻したり紛争空域に入った日本の航空機を撃墜したりした場合に、アメリカが日本を助けるために軍艦や部隊を派遣するかどうかだけの問題ではないことである。日米安全保障条約に定められたアメリカの義務は、衝突が実際に勃発した場合に核の傘を(60年以上にわたって約束してきたとおりに)本当に提供するかどうかという問題にも直接関わってくるのである。ここで、日米安全保障条約の歴史について、もう少し詳しく説明しておこう。
日米安保条約が結ばれたとき、日本領内での紛争は想定されていなかった
1952年に日米が防衛条約を初めて結んだとき、これは双方にとって好都合な条約だと思われた。アメリカ側から見れば、これによって、アジアにおける自国の利益を守るための基地を日本領内に維持できることになり、日本が国土防衛だけを目的とした小規模な軍隊を持つと約束したことで、アメリカ国民は真珠湾攻撃の再来を心配する必要がなくなった。
日本側から見ても、これは悪くない取引だった。防衛費をアメリカの納税者に事実上肩代わりさせた結果、日本はその経済的資源を平和的発展と貿易に振り向けることができた。
60年以上の間、日米安全保障条約は現代史上最長の防衛条約として存続してきたが、日本もアメリカも、この条約が日本の領土への攻撃という理由で実行される日が来るとは考えてもみなかった。外交問題評議会上級フェローのシーラ・スミスは次のように述べている。
締結当初、日米同盟は第一に、当該地域へのアメリカ軍の前方展開を可能にして冷戦に対処するための条約だった。日本領内で紛争が起きることは想定されていなかった。アジア地域の紛争として想定されていたのは、朝鮮半島問題や台湾海峡の偶発事件だった。
だが現在、日米両国とも、(理論的にはその可能性は低いとは思われるものの)日中の直接的軍事衝突や、中国が紛争時に核攻撃や核攻撃の威嚇に出る可能性について懸念せざるを得なくなった。このような核攻撃シナリオを考えているうちに、日本は当然のことながらアメリカの真意を疑わざるを得なくなる。中国の核能力がロサンゼルスやシカゴやニューヨークヘの報復攻撃も可能な水準に達している現在、アメリカは日本防衛のために本当に自国の核兵器を提供するだろうか、と。
簡単に言えば、これが日本の抱える、「アメリカは、ロサンゼルスと引き替えに東京を救う用意があるだろうか」というジレンマである。実のところ、主要都市を核攻撃の危険にさらしてくれと同盟国に頼むのはたしかに大きなお願いである。東京もワシントンも、日米安保条約の根底にあるこの隠れた条文を意識せざるを得なくなってきている。いわゆるモラルハザードという付随的問題も生じるだけに、ワシントンにとってこれは一層悩ましい問題である。つまり、日本を確実に守るというアメリカの約束によって、それがない場合に比べて日本の行動はより大胆に(おそらくは、より無謀に)なるかもしれない、とワシントンとしては懸念せざるを得ないのだ。
もちろん、ここに問題の核心がある。「アメリカが約束どおり核の傘を提供するかどうかは疑わしい」と判断するや否や、日本は「ぶれない同盟国」シナリオに代わる少なくとも二つの選択肢を検討するに違いないからである。
日本が核武装する可能性はあるか?
一つ目の選択肢は、「中国に乗り換える」シナリオ、つまり「長いものには巻かれろ」的戦略である。中国をアジアの覇権をめぐる戦いの最終的な勝者と認め、あっさり寝返って今度は「中華帝国」と運命をともにする、ということである。
日本にとって明らかに不利な点は、そうなれば必然的に尖閣諸島を明け渡さざるを得なくなることである。その上、海洋権益についても中国の主張を認めざるを得なくなり、東シナ海における漁業及び石油・天然ガス権益の大半を失うことになる。さらに、中国が本気でいわゆる失地回復に乗り出すとすれば、日本は沖縄の領有権まで明け渡さざるを得なくなり、琉球諸島は中華帝国に帰属することになるだろう。
経済面では日中の「共同統治」ということになるだろうから、日本にとって領土問題よりは少しましな結果になるだろう。おそらく、日中両国はアメリカを貿易相手国とする保護貿易圏を形成し、アメリカドルに代わって中国人民元が準備通貨に採用されるだろう。
実際、日中両国の間にすでに高度の相互依存関係が存在することを考えれば、この「中国に乗り換える」シナリオは少なくともある程度は筋がとおっている。このシナリオがなぜ米中戦争の引き金になり得るかと言えば、中国主導の経済圏ができた場合、アメリカの経済的繁栄と安全保障の両面に深刻な悪影響を及ぼすと予想されるからである。
経済面では、アメリカは中国経済圏との貿易を不利な条件でおこなわざるを得なくなるというリスクを冒すことになる。これはアメリカの輸出とGDP成長率の両方に悪影響を及ぼすだろう。軍事面でも、三つの悪影響が考えられる。アメリカはアジアの基地を失い、アジア地域のミサイル防衛網は弱体化し、中国は次第に太平洋の広い範囲に戦力を投射してくるだろうから、それにつれて、シアトルからワシントンDCに至るまでのアメリカの諸都市はますます中国の核攻撃ないし核攻撃の脅しに対して無防備になるだろう。これらの理由だけでも、「日本が中国に乗り換える」シナリオは、いずれ米中間の軋轢を大きくすることにつながりかねない。
それでは、「日本核武装」シナリオはどうだろう。唯一の被爆国として、日本は核兵器の保有には強い拒否感を持っているが、同時に、高性能の核兵器を速やかに製造・配備するだけの技術力もほぼ確実に保有している。
過去60年以上にわたる原子力発電の経験から、日本は、速やかに原子爆弾を開発するだけの専門技術も核物質も充分に持ち合わせている。時間をかけて小さな原子爆弾を開発しているイランや北朝鮮などとは違い、日本なら、ほとんど一夜のうちに最大級の原子爆弾をいくつでも製造してのけるだろう。
この予測から浮かび上がってくるのは、アジア地域におけるアメリカの戦力投射の最も重要な機能は核抑止力による平和維持だという事実である。日本や韓国は核保有国にならずにアメリカの核抑止力に頼るほうが、アジアで核戦争が起きる危険は遥かに小さくなる、とほとんどの専門家が考えている。だが、いったんこのアメリカの核の傘の信頼性が疑問視されれば、核拡散に歯止めがかからなくなり、何が起きるか分からない状態になってしまう。
日本が戦争の引き金あるいは火種となる危険は大きい
「日本核武装」シナリオのほうが「日本が中国に乗り換える」シナリオよりもさらに悪いとなれば、残ったのは「ぶれない同盟国」シナリオだけである。このシナリオのほうがまだましかどうかは、日米間の経済・軍事同盟の強化に中国がどう反応するかにかかっている。
一方では、中国が現在のようなやり方で実利的に日米の決断力の限界を探ってくるだけなら、「ぶれない同盟国」シナリオは平和に貢献するはずである。ペンタゴンの元アナリスト、マイケル・ピルズベリーは、この「力による平和」主義についてこう説明する。中国は探りを入れ、弱点を見つければ前進してくる。だが、進んでみて相手が強いと分かれば、撤退するだろうと。
他方、国内で民族問題が噴出する危険が高まったり、アメリカの後押しを受けた日本の軍事力増強に脅威を感じたりした場合、中国は「安全保障のジレンマ」シナリオに従って軍拡の努力を倍加させるだろう。その時点で、当然のことながら戦争の危険性は高まっていく。
したがって、恒久平和を模索するには日米中の指導者が自国の能力と意図についてフランクに話し合うことが非常に重要である。だが、後述するように、アジアの平和にとって最大の障害は、交渉と透明性を拒否する中国の姿勢である。だから、今後数十年の間に日本が戦争の引き金あるいは火種となる危険は大きい。鍵となるのは、アジア地域に対するアメリカの熱意と決意の度合いである。
第41章 「戦わずして勝つ」唯一の方法
問題:次のうち、正しいと思われる記述を選べ。
①弱さは侵略を招く
②強さは侵略を抑止する
③アメリカが軍事力に頼ってアジアに平和をもたらそうとすれば軍拡競争を招き、戦争の可能性が増大する
④1~3のすべて
最初に、「弱さは侵略を招く」という明快な定理に賛同しよう。現代、中世、原始時代を問わず、常に強者は弱者を餌食にしてきた。ライオンは子羊とともに寝そべることはないし、弱者は領土拡張に余念のない強者の侵略を思いとどまらせることはできない。その昔、トゥキュディデスが『ペロポネソス戦争史』に書いているとおりである。彼は、何が「正しい」かという問題は「力の等しい者たち」の間でしか解決できない、と述べている。強い者は自分のしたいことをするし、弱い者は強いられたことを堪え忍ぶしかない、と。
しかし、「弱さは侵略を招く」のが真実だからといって、その逆、「強さは常に侵略を抑止する」は必ずしも真ならずである。この公式は単純化されすぎている。そこで、「軍事力だけに頼って平和を達成しようとすれば、かえって戦争の可能性を増大させるという予期せぬ結果を招く」という選択肢も考慮に入れる必要がある。
実際、「安全保障のジレンマ」を分析した際に紹介したように、このパラドックスの裏付けとなる実例には事欠かない。防衛力増強の試みが他国から攻撃力増強の試みと誤解されると、「安全保障のジレンマ」が軍拡競争を引き起こし、戦争勃発の可能性は急速に増大する。と同時に、このような軍拡競争によって、その費用を賄わなければならない国民の生活は苦しくなる。
中国は単なる軍事力ではなく「総合国力」の視点から世界を見ている
それでは、本章冒頭の難問をどのように解けばいいのだろう。力による平和に至る真の道筋をどのように見つけたらいいのだろう。そのためにはまず、真の国力とは何かについて理解を深める必要がある。真の国力は、単なる軍事力を遥かに超越したものである。
中国人自身が、このような真の国力について熱心に研究している。彼等はそれを、「総合国力」と呼ぶ。
総合国力という言葉の奥には、真の国力は軍事力や核兵器能力といった「ハードパワー」だけに根ざしたものではないという洞察がある。真の国力は、そういったハードパワーと同程度に、経済力、労働力の熟練度、政治体制の安定度、天然資源基盤の底深さと幅広さ、教育制度の質、科学的発見の状態やそれに伴うイノベーションや技術革新の程度、さらにはその国の外交的・政治的同盟の性質や強度といった幅広い「ソフトパワー」にも左右される。その昔、副首相だった頃の鄧小平がいみじくもこう述べている。「ある国の国力を測る際には、総合的に、あらゆる面から見る必要がある」
ペンタゴンの元アナリスト、マイケル・ピルズベリーによれば、中国は総合国力を信じられないほど正確に計算しているという。その最も注目すべき点はおそらく、軍事力が国力全体の10%程度にしか評価されていないことだ、として彼は次のように述べている。
総合国力を重視する中国の考え方は、「戦争でどの国が勝つか」についてペンタゴンが考える方法とは最初からまったく異なっている。測定対象だけでなく、測定基準も異なっているのだ。
ペンタゴンにしろアメリカ政府や議会にしろ、中国に対する防衛力を考える際にグローバルな視点が欠けている。アメリカが軍事力だけを問題にしているのに対して、中国は総合的な国力について考えている。ピルズベリーが言わんとしているのは、明らかにこういうことである。
「戦わずして人の兵を屈するは善の善なるものなり」
総合国力というコンセプトは、「戦わずして人の兵を屈するは善の善なるものなり」という孫子の格言に深く根ざしている。
中国人民解放軍軍事科学院の著名な戦略家・呉春秋の言葉に、孫子の時代から連綿と受け継がれた精神を見ることができる。呉は次のように言う。
戦わずして勝つとは、まったく戦わないことを意味するものではない。政治戦、経済戦、科学・技術戦、外交戦等々、戦わなければならない戦争は数々ある。これを一言でまとめれば、総合国力戦である。軍事力は重要なファクターではあるが、平時には、軍事力は通常は予備的な力であり、目に見えない力としての役割を果たしている。
ジョンズ・ホプキンス大学のデビッド・ランプトン教授は、総合国力が平和維持にとって重要であることを全面的に認め、アメリカが経済、教育、技術、人的資源、研究開発、等々の分野で健全な総合国力を保っていれば、中国はアメリカを尊重するだろうと述べている。しかしもしもアメリカの総合国力が衰退し始めれば、「中国はさらに手に負えない国になるだろう」。
元NATO軍最高司令官ウェズレー・クラーク将軍も、ニューヨークータイムズ紙に同様の意見を寄稿している。
アメリカが国際指導力を維持し、台頭する中国の建設的な対抗勢力になるためには、アメリカ独白の長期的戦略ビジョンが必要である。つまり、エネルギー自給を基礎とする強い成長経済、活力ある効率的な民主主義、同盟国の支持に裏打ちされた積極的かつ粘り強い外交、危機的事態において一対一で中国に立ち向かえる軍事力を維持していくこビが必要である。
ランプトン教授は、アメリカが「国内事情にもっと注意を払うべきときが来ている」のかもしれないと言う。「長期にわたって国力を維持するための基礎を築き上げることによって、アメリカはより効果的に」中国の攻撃的拡大路線を阻止することができる、と彼は言う。
ハードパワーとソフトパワーの相乗効果
「力による平和」を実現するために総合国力がどれほど重要かを真に理解するには、総合国力の個々の要素であるさまざまなハードパワー・ソフトパワーがどのように相乗効果を生み出し、その結果、中国(や北朝鮮、ロシア、イランなど)のあからさまな攻撃を永続的に抑止できるようになるのかをまず深く理解しておく必要がある。
それでは、一国の軍事力を構築するのに必要な相乗効果について考えてみよう。軍事力の構築にはまず、強い経済が必要である。強い経済は、実際に兵器を製造するためだけでなく、そうした軍事費を賄うのに必要な歳入を生み出すためにも必要である。だが、経済が強くなるためには、高度な技術を待った労働力とたゆみない技術革新が必要である。
また、質の高い労働力を生み出すためには、当然のことながら優れた教育制度が必要となる。同時に、迅速な技術革新には科学や数学や工学に特化した教育制度が不可欠だし、さらに、研究開発のための設備投資を可能にする金融制度、起業や技術革新を優遇する税制も必須である。
今日のグローバルな金融システムの中では、どの国の国内経済も、外国市場に自由にかつ迅速にアクセスできなければ繁栄することはできない。当然のことながら、こうした自由貿易には貿易相手国との強力な同盟関係だけでなく、世界通商路の自由な航行も必要となる。これがまた、海と空を通商のために聞かれた空間にしておくための、強力な軍事力の必要性へとつながっていく。
だが、相乗効果はこれで完結ではない。こうした相乗効果を生み出すための国家的基礎として、正常に機能する政治体制が必須である。このような政治体制は、社会に安定をもたらすだけでなく賢明な公共選択(※社会や政治による意思決定)をも生み出す。賢明な公共選択によって、近代的道路や橋、航空管制や公共交通機関や上下水道など、「公共財」やインフラが供給され、民間部門の成長が促進される。
「アメリカにはルールを守らせる能力がない」
しかし、こうしたさまざまなハードパワー・ソフトパワーの各要素がどのように相乗効果をもたらすのか、これらすべてがどのように総合国力に寄与するのかを考える際、常に念頭に置いておかなければならないことがある。それは、軍事力は国力の一要素に過ぎないかもしれないが、狼やドラゴンが戸口まで迫ってきたときには、軍事力は常に最も重要な要素だ、ということである。
この真理を数学的に表現すると、総合国力を構成する軍事力以外の要素がすべて真の国力を作り上げるための必要条件であるのに対して、その十分条件はとなると、それは結局のところ軍事力だ、ということになる。クラウゼヴィッツ流の用語を使って簡単に言えば、強い経済、優れた教育制度、安定した政治体制、豊富な天然資源、優秀な労働力を持っていても軍事力を持たない国は、悪意を待った軍事大国に対して完全に無防備だし、したがってたやすくその餌食になる、ということである。
これは、紀元前にローマがギリシヤに対して、その数百年後にゲルマン人がローマに対して、力ずくで教えた真実だった。これは、中央アジアの草原から襲来したモンゴル軍を迎え撃った宋が、大きな代償を払って学んだ教訓でもあった。
したがって、「米中戦争は起きるか」という問題に対する最終回答は、アメリカとそのアジア同盟諸国が取るべきさまざまな方策を検討し、総合国力という強力な抑止力を基礎とする力の連合によって平和を構築できるかどうかを見きわめた上でなければ出すことができない。この第六部では、アメリカン・エンタープライズ研究所のダン・ブルーメンタールと新アメリカ安全保障センターのパトリック・クローニンの次のような意見を参考にしながらこの問題を考えることにする。ブルーメンタールは言う。
思うに、これまでアメリカが戦争に巻き込まれたのは、他国に決断力と意志を疑問視されたときだった。この図式は、アメリカがおこなった多くの戦争に当てはまると思う。だから、戦争を回避する最良の方法は、非常に強力な軍隊を持ち、非常に強力な同盟関係を構築することによって、潜在敵国に、「両国間の論争の原因が何であれ、アメリカは本気だ。最後の手段として実際に武力を用いるだろう」と信じさせておくことだと思う。
クローニンはこう述べている。
アメリカにはルールを守らせる能力がない、とアジア諸国は感じている。これが現在の世界なのだ。それは、誰がルールを守らせるのか明確でない世界だ。そして、誰がルールを決めるのか分からなくなったとき、何か起きるだろう。誰もが勝手にルールを作るだろう。
第42章 経済力による平和
問題:次のうち、正しい記述を選べ。
①中国は、通貨操作、違法な輸出補助金、知的財産権侵害、自国の製造基盤を強化し輸出主導型経済成長を促進するための自国市場の保護など、数々の不公正な貿易方法に頼っている
②経済成長と強力な製造基盤が中国に、軍事力の強化及び近代化のための豊かな資源をもたらした
③中国は、その優勢な経済力を武器に、貿易や領土問題などさまざまな問題で日本、フィリピン、台湾、ベトナムなどの近隣アジア諸国を威圧してきた
④2001年に中国がWTOに加盟し、アメリカ市場に自由に参入できるようになって以来、アメリカは7万力所以上の製造工場を失い、経済成長率は半分以下に縮小した
⑤経済成長の減速と製造基盤の弱体化により、アメリカにとって、自国の安全保障を確実にするとともにアジア同盟諸国への条約義務を遂行するに足る軍事力の規模と質を維持することは次第に困難になりつつある
⑥1~5のすべて
6の「1~5のすべて」が本当に正しいとすれば(実際、それらの論点は本書の中でこれまで個別に検証され、事実と認定されている)、アメリカの国家安全保障とアジアの平和のために取るべき方策は明らかに、中国製品への依存度を減らすことだと思われる。何と言っても、このような方策によって中国との貿易関係の「リバランス」を図れば、中国経済とひいてはその軍拡は減速するだろう。さらに、アメリカとその同盟諸国が強力な経済成長と製造基盤を取り戻し、総合国力を向上させることもできる。シカゴ大学のジョン・ミアシャイマー教授は、この点について次のように述べている。
現在、中国を恐ろしい存在にしているのは、膨大な人口を抱える中国が、巨大な香港と化すのではと危惧されるほど豊かな国になりつつあるという事実である。そして、一人当たりのGDPが香港のそれに近くなれば、中国は手強い軍事大国になるだろう。したがって、ずっと魅力的な戦略は、中国の経済成長を減速させる方策を積極的に打ち出すことである。経済が成長しなければ、中国は富を軍事力に変換することもできないし、アジアにおける潜在的覇権国になることもできない。
私たちは中国製品を買うたびに、中国の軍事力増強に手を貸している
こう言うと単純明快な方策のように思われるが、言うは易く行うは難し、である。その実行には、さまざまな経済的・政治的・イデオロギー上の障害が伴う。
アメリカが相殺関税を賦課するなどして中国の不公正な貿易方法を是正し、中国製品への依存度を削減しようとすれば、確実にインフレ率の上昇を招くだろう。消費者が安い中国製品の代わりにもっと値段の高い国産品や他の国々からの輸入品を買うようになれば、必然的にものの値段は上がる。
この経済的障害の他に、政治的な問題も生じるだろう。安い中国製品が市場に入ってこなくなれば、社会の中で最も深刻な打撃を受けるのは貧困層である。貧困層に負担が偏るというこうした不公平は、少なくとも左派からの激しい批判にさらされるだろう。
イデオロギー上の問題も、中国製品の流入を食い止めようという運動の足かせになるだろう。自由貿易をこれまでずっと信奉してきたアメリカ人、特に右派は、「保護主義」と見なされかねない政策を支持することに後ろ向きなのである。しかし、米中委員会メンバーで共和党支持者のダン・スレインは、「防衛関税」政策を支持してこう述べている。
アメリカの景気は後退している。それは対中貿易赤字を放置しているからだ。……貿易赤字を解消し製造業を復活させなければ、国内に大きな経済問題を抱えることになるだろう。
対中貿易のリバランスが模索される中で、こうした経済的・政治的・イデオロギー上の障害が克服されるかどうかは未知数である。しかし、はっきりさせておかなければならない事実がある。それは、中国製品を買うたびに、われわれ消費者(「われわれ」には、アメリカ国民だけでなく、インド、日本、フィリピン、シンガポール、韓国、台湾といった、中国との間に問題を抱えている国々の国民も含まれる)は、自分と自分の国に危害を加えようとしているかもしれない中国の軍事力増強に手を貸しているのだ、という事実である。
投票箱の前とレジの前で、われわれ一人一人がこの認識を具体的な行動に変換し、中国への経済的依存度を減らしていかなければ、実際に弾丸やミサイルが飛び始めたとき、あるいは、中国が意のままに振る舞うのを黙って見ているしかなくなったとき、われわれは自分を責めるほかなくなるだろう。
この重大な点を踏まえ、米中委員会の元メンバー、パット・ムロイは、アメリカのアジア重視政策が軍事にのみ偏っているのは大きな誤りだとして次のように述べている。
大統領は、これからはアジア重視だと言う。それはなぜか。中国が台頭しているからだ。それなら、なぜ中国はこれほど急速に台頭してきたのだろう。それは、アメリカが巨額の貿易赤字を抱え、投資と技術を急速に流出させているからだ。向こうの能力が強化されるにつれて、こちらの能力は弱体化している。だから、アジア重視には賛成だ。同盟諸国を安心させるため、(軍事の)軸足をアジアに移そう。だがそれなら、対中貿易のリバランスを図リ、アメリカの消費者にこれ以上中国台頭の後押しをさせないようにするほうがさらに理に適っているのではないだろうか。これが、アジア重視の真に賢明な方法だろう。
米中委員会のマイケル・ウェッセルは、経済面に重点を置いたアジア重視政策を実行に移すためには、アメリカ政府上層部に「中国政策通」を据えるべきだとして次のように述べている。
第一に、アメリカは本気を出すべきだ。アメリカ政府内には、米中関係を専門に担当する人物がいない。これまでは、「中国も、世界経済の善良な一員という点で、われわれと同様の関心を持っている」という前提の下、何事も中国10億人の民にモノを売る機会だと単純に考えられてきた。だが、過去10年から20年の間に、中国がわれわれとはまったく違う関心を持っていること、他者を排除してそれを押し進めようとしていることが分かってきた。それは彼等の勝手だが、問題はわれわれがそれに異議を申し立てるかどうかだ。
だからまず、米中関係の経済面と国家安全保障面の両方に明るく、この二つが不可分に結びついていることを認識している責任者が必要だ。たとえば、中国に自国通貨の操作を許せば、中国は予算留保を増やし、そのカネでアメリカを打ち負かすための兵器システムを外国から買うだろう。そんなことが毎年のように起きているのだ。
世界一高い法人税のせいで米国の金と技術が流出している
対中貿易の不均衡の是正はたしかに、アメリカとアジア同盟諸国の経済を強化し、それと同時に中国の軍拡資金調達能力を弱体化させるための最も直接的な方法の一つではある。だが、このような貿易不均衡の是正だけが、唯一の「経済力による平和」戦略ではない。
第二の戦略とは、税制改革である。これも、貿易不均衡の是正と同じく政治的論争を巻き起こすものと思われる。だがこのような改革は、現在、法人税率が世界一高いアメリカには特に重要である。この法人税率の高さが、アメリカの製造業と雇用がどんどん国外へ流出する原因になっている。理由は単純である。工場と雇用を海外に移すだけで、企業はアメリカの高い法人税を免れ、納税額を減らすことができる。
第三の戦略は、現在中国に略奪されるがままになっている、軍用及び民間の知的財産権の保護を大幅に手厚くし、企業秘密や軍事機密の窃盗を中国に一切許さないようにすることである。
もちろん、アメリカの知的財産を守るための最も直接的な方法は、中国で営業しているアメリカ企業に自社技術の譲渡を強制するという中国の違法な政策に対してアメリカ政府が断固たる措置を取ることである。この強制的な技術移転は明白な世界貿易機関協定違反だが、最大級のアメリカ企業でさえ、中国市場からの締め出しを恐れ、このような被害に遭っても抗議の声を上げることには消極的である。ダン・スレインは次のように述べている。
優れた軍事力を保有するには、優れた技術力が不可欠だ。だから、ボーイングやゼネラル・エレクトリックといった(アメリカ)企業に中国への技術移転を許せば、わが国は甚大な不利益を被ることになる。アメリカがこれほどの超大国になったのは、わが国の技術力と技術革新と兵器システムが世界中のどの国よりも遥かに優れているおかげなのだから。
最後に、教育制度の再建(というか再構築)という厄介な問題もクリアする必要がある。アメリカの教育制度は義務教育から高校、大学に至るまで混乱状態である。国が繁栄するためには、奨学金という多額の負債を学生自身に負わせることなく将来の職業人を育てる必要がある。本書では教育改革まで論じることはできないが、教育制度改革も喫緊の問題であることは確かである。
「経済を健全化しなければ、アメリカは中国に対抗できない」
以上、経済力を高め、それによって総合国力と抑止力を高めるための方法を考えてきたが、そのすべてに共通するのは、どんな改革が必要であるにせよ改革には政治的合意が必要だということである。これについては、最終章でもう一度取り上げることにする。さて次は、「力による平和」を考える上で欠かせないもう一つの力、つまり軍事力について検討することにしよう。だがその前に、元国務次官補カート・キャンベルとヘリテージ財団のディーン・チェンの、不気味なほど似通った言葉を引用して本章を締めくくることにする。キャンペルは言う。
私はよく、「アメリカが国際舞台でリーダーシップを維持するために最も重要なことは何ですか」と聞かれる。そんなときは、どこそこの軍事作戦をどうするとか、どこそこの地域をどう扱うといった答えを期待されていることが多い。言っておくが、最も重要なことは、アメリカ本国をきちんとしておくことだ。
ディーン・チェンも同意見である。
何よりもまず必要なことは、アメリカ経済を健全化することだ。その他のことは自然についてくる。経済を健全化しなければ、つまり赤字を削減しなければ、アメリカは中国に対抗できない。これは、他の何よりも、われわれ自身の努力次第でできることだ。これはアメリカ国民とアメリカ政府の努力次第で成し遂げられることだし、中国政府はそれをどうすることもできないのだ。
第43章 軍事力による平和
問題:現在、米中どちらのアジア軍事戦略がより優れているか?
①中国
②アメリカ
「軍事力による真の平和」をアジアにもたらすために必要とされる軍事力とは、中国が直接的な脅威と感じるほどではないが、その一方で、中国軍の最大限の威嚇にもびくともしない程度の軍事力である。この微妙なバランスは、軍事力による平和を模索する際の判断基準になるに違いない。どちらも暴力に訴えることなく中国の拡張主義を抑止できるのは、このような状況しかあり得ない。
そのようなバランスを見つけて維持できるかどうかは、少なくとも二つの理由で疑わしい。まず、最も明らかな理由は、中国の軍事能力が急速に増大するにつれて、アメリカと同盟諸国のそれが相対的に弱体化するということである。二番目の、もう少し微妙な理由は、アメリカと同盟諸国がこれまでのところ、一枚上手の中国の軍事戦略に対して何ら明確な手を打っていないように見えるということである。
誤解のないように言うと、中国の戦略は実は戦略ではない。戦略というより、むしろ対抗戦略と言ったほうがいいようなものである。これはまさに、孫子の「上兵は謀を伐つ(最高の戦い方は、敵の戦略を見破ってそれを封じることだ)」を地で行くやりかたである。
米中それぞれの「三本柱戦略」
中国の対抗戦略(中国側の用語では反干渉作戦という)は現在、アジアにおけるアメリカの優位を支えている戦略の三本柱に狙いを定めている。戦略の三本柱とは、①圧倒的な戦力によって制空権・制海権を確保している空母戦闘群、②第一・第二列島線上に数力所配置されている、攻撃の起点及び後方支援の拠点となる大規模な基地、③最先端の「C4ISR」システム(指揮(コマンド)、統制(コントロール)、通信(コミュニケーション)、コンピュータの頭文字のC4つと、情報(インテリジェンス)のI、監視(サーベイランス)のS、偵察(リコネサンス)のRを表す)によって戦場の状況認識を可能にする人工衛星システム、の3つである。
中国側も、独自の三本柱戦略に基づいてアメリカの三本柱を破壊する計画を進めている。中国の三本柱とは、①アメリカの非常に高額な空母戦闘群及び基地(固定された「ソフトターゲット」)を破壊ないし無力化する能力を待った、比較的安価な非対称兵器を大増産する、②将来的にアメリカ軍を量的にしのぐことを目的として、空母戦闘群を大量生産する、③アメリカの人工衛星システムの破壊及び中国自身の人工衛星ネットワーク構築によって制宙権を握り、アメリカのC4ISR優位を打破する、というものである。
現在のところ、中国がこの対抗戦略を的確にかつ整然と遂行しているのに比べて、この急激な変化に対するアメリカ及び同盟諸国の反応は非常に鈍い。このままでは、数十年のうちに(さらに早いかもしれない)アジアの軍事バランスは逆転してしまうだろう。当然のことながら、これはきわめて危険な傾向である。中国がアジアで優位に立てば、あるいは、「優位に立った」と中国自身がある段階で判断しただけでも、それはさらなる侵略行為につながるだろう。考えるべき問題は当然、「このまま昔ながらの予測可能な駒の動かし方を続ければ確実にチェックメイトが待っているゲームに、ペンタゴンはどう対処すべきか」である。
この重大な問題に答えを出し、ひいては軍事力による平和への正しい道を見出すため、これから、中国の対抗戦略のターゲットにされているアメリカの戦略の脆弱性を一つ一つシステマチックに検討していこう。その過程で必然的に、これまで本書で述べてきた主張の多くを繰り返すことになるだろうが、それは、これまでのそうした主張が、力による平和への道を模索するためのものだったからである。
中国軍の司令官は北京の指示を仰がなければ動けない
それでは、最も簡単に、さらに比較的安価に対処できる弱点から見ていこう。それは、固定されたソフトターゲット、つまりアジアのアメリカ軍基地のことである。すでに述べたように、第一に基地の「強化」が必要である。これは、燃料タンクや兵器庫を地下深部へ移動させる、航空機をサイロに格納する、膨大な量のコンクリートと鉄筋で滑走路や建物や兵舎や埠頭を要塞化する、といった方法によって実行できる。
同時に、この「基地=ソフトターゲット」問題解決のためには、現在グアムや沖縄の嘉手納基地などに集中しているアメリカの兵力を、アジア中に点在するずっと小規模の基地に分散する必要がある。この分散・多様化戦略の目標は、ターゲットを絞り込みにくくすることである。
基地と同じように、人工衛星資産も「強化」する必要がある。基地の多様化と同じ意味で、宇宙通信中継点の数を大幅に増やし、そのサイズを縮小する必要がある。このような宇宙資産の多様化は、「キューブサット」と呼ばれる小型衛星や高高度気球や、近年急速に普及したドローンなどのさまざまな新技術によって比較的簡単かつ安価に実現することができる。
しかし、結局のところ、紛争時の通信能力を確保するための最上の方法は、人工衛星にまったく依存しない代理機能システムを構築することかもしれない。具体的には、これは、紛争が勃発した際には水上捜索レーダーや高周波無線機といった昔ながらの技術を使って通信をおこなえるようにしておくということである。
人工衛星資産について最後に指摘しておきたいのは、アメリカはほぼ間違いなく、中国の人工衛星ネットワーク撃墜を目的とする対人工衛星兵器の開発をさらに進めなくてはならなくなるだろうということである。これは、軍拡競争の観点から残念ながら避けがたいことである。戦略上興味深いのは、アメリカ軍の衛星通信依存度が高まるにつれて、将来的には中国のほうがさらにその依存度が高くなるかもしれないということである。
その原因は、中国の中央集権化された指揮統制体制にあると言えるかもしれない。このような集中化は、中国の独裁的政治体制の副産物である。中国軍は、アメリカ軍の司令官らが公海上や上空で通常有しているような分権的裁量権を軍司令官に与えることを毛嫌いする。中国軍の司令官らが細かいことまで北京の指示を仰がなければならないことを考えると、もしアメリカが紛争時に衛星通信の主要中継点を見つけてこれを破壊することができれば、より迅速に中国軍司令部にダメージを与えたり麻痺させることができるかもしれない。
第五世代戦闘機の製造機数は中国のほうが遥かに多い
基地及び人工衛星の脆弱性はどちらも対処可能で、その解決法も比較的安価だと思われる。これに対して、空母戦闘群の脆弱性が近年とみに高まっている問題についてはそうは言えない。この脆弱性の原因は、中国の非対称兵器及び従来型兵器の量が増えているだけでなく、中国の兵器全般の技術的な質も急速に向上していることにあるものと思われる。
第8章ですでに述べたように、航行中の空母に1600キロ彼方から対艦弾道ミサイルを発射して命中させる能力を中国が獲得したことは、明らかにゲームの流れを変える出来事だった。すさまじい力でアメリカの艦船を文字どおり海から吹き飛ばす、最高速度マッハ10の超音速滑空ミサイルも同様である。
数と量で圧倒する中国のやり方についてはすでに何度も述べたが、中国が現在すでに記録的な数の最新式非対称兵器を製造している事実は、改めてもう一度述べておく価値が充分あると思う。このまま製造量が増えていけば、中国はミサイルの大量一斉射撃によってついにはアメリ力の防衛システムを圧倒できるようになるかもしれない。1000発のうちたった。1発の弾頭が命中するだけで、任務阻止には十分なのである。
中国が大量生産しているのは非対称兵器だけではないことも、ここでもう一度述べておきたい。「世界の工場」は、自前の空母戦闘群を出動させるのに必要となるあらゆる航空機や艦船を大量に製造している。
さらに、中国は今では、盗み出した技術を使って、第五世代の戦闘機まで製造している。その製造機数は、予算不足に悩まされているアメリカのF-35やF-22のそれよりも遥かに多い。アメリカン・エンタープライズ研究所のマイケル・オースリンは、アメリカ議会がF-22の製造中止を決定したことを嘆き、数の力を侮ってばならないと警告する。
F‐22は高高度を高速で飛行し、ステルス性が高いためレーダーに捕捉されにくい。だがいつか、彼等(中国)の防空技術は今よりも向上するだろう。彼等のレーダーは、より高高度をより高速で飛行する対象をも捉えるようになり、感度も向上するだろう。F-22をはっきり捉えることはできなくても、今より早く発見できるようになるだろう。これはあらゆることに影響を及ぼす。だから、やはり数も大切なのだ。F-22が2機しかなければ、それは大した脅威にはなり得ない。第二次大戦時のように敵の上空を大編隊で埋め尽くすことができれば、確実に大きな脅威となる。残念ながら、今のアメリカにはそんなことはできないし、これからもできないだろう。
空中戦でアメリカが圧倒されるかもしれないとなれば、当然のことながら、「アメリカは太平洋の制空権を維持できるのか」というさらなる問題が生じる。ヘリテージ財団のディーン・チェンは、「制空権があっても勝てるとは限らないが、なければ確実に負ける」と警告している。
潜水艦戦と機雷戦が抑止力の鍵を握る
このような厳しい見通しを踏まえた上で、「問題点に対処するためにアメリカは何をすべきか」という問題に戻ろう。アメリカ海軍大学校のトシ・ヨシハラは、非対称戦と領域拒否をそっくりそのまま中国へお返ししてやればいいと考えている。つまり、孫子の助言「上兵は謀を伐つ」に従って、中国自身の戦略を攻撃してやればいいのだ、と。
ヨシハラの言うような「やられたらやり返せ」戦略を実行に移すとすれば、まずはアメリカ軍の再編成が必要となるだろう。ヨシハラのアイディアは、第一・第二列島線のおもなチョークポイントに攻撃用潜水艦を並べ、有事の際に中国の軍艦及び商船の太平洋へのアクセスを管理できるようにする、というものである。つまり、潜水艦を建築ブロック代わりに使って、難攻不落の水中「長城」を建造するのである。
「潜水艦を槍の穂先として使う」この戦略は、中国の侵略行為に対する強力な抑止力になる、とヨシハラは言う。そんなことをしても自国の経済と軍事力がダメージを受けるだけだと悟れば、中国も侵略行為を控えるだろう、と。アメリカ海軍大学校のジェームズ・ホームズ教授も、こうした戦略に賛成して次のように述べている。
潜水艦戦は、アメリカの長年の得意分野だ。冷戦時代もそうだったし、現在でもそうだ。中国はなぜか今まで対潜水艦戦にあまリカを入れてこなかった。したがって、潜水艦戦でアメリカが有利な状態は、今後かなりの間続くと考えて差し支えない。
しかし、水中「長城」の建造を潜水艦だけに任せておいてはならない。アメリカも同盟諸国も、機雷戦能力を向上させる必要がある。
そうすれば、中国が台湾や尖閣諸島や南シナ海の島々などを機雷によって孤立させようとした場合、アメリカと同盟諸国はその報復として上海や大連や福建省の港を簡単に封鎖することができる。
機雷や潜水艦の配備が進むにつれて、対潜水艦戦と対機雷戦の分野でもかなりの能力の向上が求められるようになる(アメリカは、歴史的に対潜水艦戦は得意だが、対機雷戦のほうは現在ほとんど無視している)。ここでも、目標は抑止力の向上と現状維持である。これが、アメリカにとっての「戦わずして勝つ」なのである。
「これらの兵器を製造する理由はこれらを使用するためではない」
アメリカの戦略上の脆弱性を是正するためのこうしたさまざまな方策の他にも、軍事力によ
る平和への道を模索する上で実行すべき措置はまだいくつかある。第一に、停滞している宇宙計画をもう一度軌道に乗せることがきわめて重要である。でないと、アメリカはそれこそ戦わずして、戦略的高地を中国に譲ることになる。そして、一度失ったら、取り戻すことは難しいだろう。
第二に、第五世代の戦闘機F-35や現在空軍が開発中の長距離攻撃爆撃機を大幅に増産することも非常に重要である。どちらも非常にカネのかかる計画だが、それぞれが独自の方法で抑止力を高め、力による平和の実現に大きく貢献する。
F‐35について言えば、太平洋戦域における制空権を維持するためにはその優れた性能が不可欠である。この航続距離の比較的短いジェット戦闘機を、アジア地域全体に分散して周到に配備する必要がある。この場合、ものを言うのは数である。中国が自前の第五世代戦闘機を大量生産していることを考えればなおさらである。
長距離攻撃爆撃機について、アメリカン・エンタープライズ研究所のマイケル・オースリンなど推進派は、中国やロシアやイランなど潜在的敵国が配備を進めている統合防空システムや自動防空システムに対処するためにこれが不可欠だと主張している。この爆撃機は、戦時に空母戦闘群や基地が中国に無力化ないし破壊されたときのための重要な保険というだけではない。これは、無人の大陸間弾道ミサイルに代わる、遥かに安全な兵器でもある。オースリンは言う。
現在、アメリカには、中国領空にまで無事にたどリ着けない爆撃機を送り込むという選択肢しかない。それでは、どうする? 潜水艦やアメリカ中西部のサイロからミサイルを打ち上げるのか? 中国はそのミサイルにどんな弾頭が搭載されているか分かる前に撃ち返してくるだろう。だから、こんなことを言うと冷戦時代に戻ったように思われるかもしれないが、長距離攻撃爆撃機のような、中国領空やロシア領空にまで深く侵入できる爆撃機は、実は事態を安定化させる要素なのだ。爆撃機なら、送り込むこともできるし、送り込んでから呼び戻すこともできる。戦闘機ははっきりと目に見える。これに対して、ミサイルは一度発射してしまえば取り返しがつかない。
新アメリカ安全保障センターのパトリック・クローニンは次のように述べている。
21世紀には、海軍力と空軍力のバランスの取れた軍事力と、充分な数の従来型資産が必要だ。たとえば、空母が必要だ。航空機も必要だ。潜水艦もいる。ステルスもほしい。海岸線をパトロールする艦船も必要だ。それと同時に、サイバー技術や宇宙技術、無人航空機や長距離無人システムに投資し続けることも必要だ。それらはゲームチェンジャーになる可能性があるからだ。だから、最新技術と従来型の技術のバランスが大切なのだ。
これらすべての兵器システムにかかる多額の費用を考える際には、抑止力に関するオースリンの金言「これらの兵器を製造する理由はこれらを使用するためではない」を思い出すべきかもしれない。オースリンは言う。
B-52が50年間現役だったのは驚くべきことだ。祖父、父、息子、と三世代のパイロットがこの同じ爆撃機に乗ってきたのだ。B-52は素晴らしい爆撃機だが、現代の自動ミサイル防衛システムの前ではひとたまりもない。その上、現役のB-2ステルス爆撃機は20機しかないし、しかも時代遅れにもなりつつある。だから新しい爆撃機が必要だし、必要な場合に地上と上空の障害物を除去できるようにしておくためには、F-35を大幅に増やす必要がある。軍事的な理由だけでなく、政治的な理由からもそうする必要がある。F‐35の増産は、実際にはアジアの(不安定化ではなく)安定化に貢献するだろう。
ジョージタウン大学のフィリップ・カーバー教授は、抑止力構築のためにはこうした具体的な方策の他に次のような原則が不可欠だと述べている。
必要なのは、中国に対して(他の国々に対しても同様だが)それ相応の対応を取るという原則だ。そっちが戦力を削減するなら、こっちも削減しよう。ミサイル配備を強化してこっちの基地や同盟諸国を脅かすような挑発的な真似をするなら、こっちも相応の対応を取る。そして、肝心なのはこうした原則をちゃんと相手に伝えることだ。今まで、われわれは基本的に、中国にただ乗りを許してきてしまった。
第45章 中国の脅威を直視する
問題:本書のこれまでの内容を踏まえて、「急激に軍事大国化する中国は、アジアの平和と安定にとって脅威である」という主張に対する最終的判断を選べ。
①国防費の大幅増額への支持を煽るために右派が考え出した、偏執狂的妄想である
②中国の現状変更的意図、急速な軍事力増強、次第にエスカレートする侵略行為を合理的に判断した結果に基づく、当然の懸念である
「団結すれば栄え、分裂すれば倒れる」というよく引用される格言があるが、新約聖書にも「どんな町でも家でも、内輪で争えば成り立って行かない」(新共同訳)と書かれているように、これは昔も今も変わらぬ真実である。ここで重要なのは、経済力と軍事力によってアジアに平和を構築し、同盟関係の堅持によってこれを守るためには、まず「中国はアジアの安全保障にとって大きな脅威となり得る」という政治的合意が不可欠だという事実である。
もちろん、このような合意はなかなか得られるものではない。なかなか意見がまとまらないという、特にアメリカで深刻なこの問題の根には、民主主義そのものの性質と民主主義体制ならではの利害の競合がある。
中国の通貨操作を取り締まる法案はなぜ米国で否決されたのか?
たとえば、中国との貿易によって、アメリカの製造業界は真っ二つに割れてしまった。一方の側には、中国の違法な輸出補助金によって大打撃を被っている無数の中小企業が存在する。これら中小企業は、中国に通貨操作をやめさせ、相殺関税を導入し、その他にも適切な救済策を取るべきだと主張してきた。
その一方で、アップル、ボーイング、キャタピラー、ゼネラルモーターズ、IBMといった、アメリカに本部を置く一握りの多国籍大企業が存在する。これら大企業は生産拠点を中国に移し、製品をアメリカ市場に輸出することによって、中国の違法な輸出補助金や搾取労働や税金の抜け穴や大甘な環境規制を利用して大儲けしている。
それで、製造業界のこのような利害の衝突を解消するために、政治はどのように対応してきただろうか。全米製造業者協会や事業者協会といった有力圧力団体は多国籍大企業に牛耳られているため、結局は中国の重商主義に反対しない。これら「中国は脅威ではない」と主張するロビイストらは、中国の違法行為を取り締まろうとするホワイトハウスや議会の努力をことごとく公然と妨害する。
こうした分裂は、各業界レベルで見られる。不当に安い値段でアメリカ市場になだれ込んでくる、違法な補助金を受けた中国製ソーラーパネルに相殺関税をかけるべきだとソーラーパネル製造業者が声を上げたとき、最も強硬にこれに反対したのは中国ではなかった。それは、ソーラーパネルの価格上昇によって仕事が減ることを恐れた、ソーラーパネル設置業者たちだった。
分裂は州レベルでも見られる。たとえば、オハイオ州は中国の経済攻撃によって製造業に壊滅的被害を受けている州だが、大統領選挙の激戦州として知られるこの州の有権者は真っ二つに割れてしまっている。アクロン、クリーブランド、デイトン、ヤングズタウンなどの工場労働者(その多くは現在失業中である)は全員、違法な中国の補助金に対して政府が断固たる措置を取るべきだと考えている。一方、ダーク郡、マディソン郡、ウッド郡など農業地域の農民は、トウモロコシや大豆を大量に中国へ輸出して儲けているため、貿易不均衡是正策に公然と反対している。
オハイオ州の分裂は、自由で聞かれた民主主義が中国の国家資本主義に立ち向かうときに直面する政治問題の縮図である。一例として、オハイオ州選出の民主党下院議員ティム・ライアンが中国の通貨操作を取り締まるための法案を提出したときのことを挙げておく。
ライアンの地盤は、ヤングズタウンやアクロンといった製造業の盛んな都市である。ライアンの法案は否決されたが、そのときほとんど一人で否決に持ち込んだと言っていいほど強硬に反対したのは、皮肉なことに同じオハイオ州選出の多数党(当時は共和党)院内総務ジョン・ベイナーだった。
ベイナーにとってこの政治的勝利は、まさに「一粒で二度美味しい」結果となった。地元オハイオ州最大の農業地域を大いに喜ばせただけでなく、中国に生産拠点を移している多国籍大企業から彼自身と共和党への多額の選挙献金を得ることができたからである。
労働組合や環境保護団体や人権団体などにも、同様の分裂が見られる。たとえば、雇用をさらに外国に奪われるのではという懸念から、労働組合は日本や韓国など同盟国との自由貿易協定に強硬に反対している。しかし、適切に結ばれさえすれば、このような自由貿易協定はアメリカと同盟諸国双方の経済成長を後押しし、総合国力の増大と経済力及び軍事力による平和の構築に貢献するだろう。
環境保護活動家や人権活動家らはとかくペンタゴンを目の敵にし、国防費増額には何が何でもとにかく反対という立場を取る。皮肉なことに、彼等のそういった行動は回り回って、アメリカの国家安全保障に危険をもたらす可能性があるだけでなく、間違いなく世界で最も環境を汚染し人権を抑圧している独裁的政権を援助しているのである。
ペンタゴンの元アナリスト、マイケル・ピルズベリーは、利益団体が作り出すこのような分裂状態について次のように述べている。
アメリカに8ないし10ある重要な利益団体と、それらの団体の利益を代表する議会勢力は協力し合おうとはしない。それどころか、お互いに反目し合い、さまざまな哲学的理由で対立している。減税に賛成、減税に反対。企業は悪だ、組合は悪だ、等々。中国の脅威に対して結束するどころか、小さな問題で言い争ってばかりいる。この有様を見て中国は、「ワシントンで大きく取り上げられないように気をつけよう。目立たないようにしていよう。ああいう諸団体が一つにまとまることがないようにしておかなければ」と考えているのだ。
ワシントンで巨額のカネをばらまいている中国勢力
アメリカのような民主主義国が力による平和を模索する際に直面する問題は、残念なことに、利益団体が共通の脅威に対して団結するより足の引っ張り合いに熱心なことだけではない。独裁的な中国と民主主義国アメリカとの間には、著しい不均衡が存在する。開かれたアメリカの政治プロセスに中国が影響を及ぼす方法はいくらでもあるが、著しく不透明で閉鎖的な中国の政治プロセスにアメリカが影響を及ぼす方法はほとんどない。
中国がアメリカの政治プロセスに入り込んでいることについて、米中委員会委員マイケル・ウェッセルは次のようにずばりと述べている。
中国はあらゆる方面で総合国力を伸ばしている。ここワシントンでは、彼等は政治力を伸ばそうとしている。中国企業はカネをばらまき、法律事務所を雇い、ロビー団体を雇い、パーティーを主催するなど、ふつうの特定利益団体がワシントンで勢力を伸ばすためにやるようなことをすべておこなっている。しかも、非常に効果的におこなっている。
「カネをばらまく」作戦の一環として、中国に対するマスコミの論調を和らげるために中国政府は巨額の広告費を注ぎ込んでいる、とウェッセルは警告する。
多くの全国紙に、チャイナデイリーやチャイナニュースといった、英語版インチキ中国紙が折り込み広告として定期的にたっぷりと折り込まれている。これを目にするアメリカ人はそれがただのプロパガンダとは気づかず、本物のニュースだと思い込んでしまう。
中国の圧力に屈した米国メディア
自分の言い分を西側に押しつけるために中国政府がやっているのは、ロビイストや広告費を使って発信することだけではない。中国政府は、自分に都合の悪いことが報道されないよう世界中のジャーナリストに圧力をかけている。
西側の報道機関に自主規制が広まったおもな原因は、中国政府の圧力である。中国国内のニュースを報道するためには特派員を中国に派遣することが必要だが、中国政府はビザの発給を利用して、中国政府の方針に批判的すぎたり、政治腐敗や環境汚染、民主化運動や労働者の暴動といった「避けたい話題」を掘り下げすぎるジャーナリストの入国を長年にわたって制限してきた。
元『ニューズウィーク』誌北京支局長で、現在は『コンデナスト・トラベラー』誌で世界情勢を担当している長年の中国通ドリンダ・エリオットの告白を聞いてみよう。「恥ずかしい話だが、私は微妙な問題を報道するリスクを心配していた。入国を拒否されたらどうしよう、と」
『アトランティック』誌のジェームズ・ファローズの証言もある。中国脅威論に対して長年ハト派の立場を貫いてきたファローズだったが、その彼でさえとうとう、自分は「中国政府の怒りっぽさを知っていた」ためそれに配慮した記事を書いていたと認めたのである。
だが、西側ジャーナリストが直面する問題はビザ発給拒否だけではない。中国国営メディアの御用記者は自由に世界中を渡り歩けるのに、西側の記者たちは中国の至るところで立ちいりを禁止され、取材現場でそれこそ日常的に嫌がらせや干渉に悩まされ、ときには身体的暴力まで受けることがある。
こうした圧力がどれほど効果的に自主規制を引き出すかを理解するためには、ブルームバーグ・ニュースの実例を見るだけで充分である。中国共産党幹部の腐敗をブルームバーグが報道すると、中国政府はブルームバーグのドル箱である金融市場情報端末(その売り上げは、ブルームバーグの収益の80%以上を占める)の不買運動を仕掛けた。すると、ブルームバーグは中国に関する硬派のニュース報道事業から撤退してしまった。中国の圧力に屈したブルームバーグ会長ピーター・グローアーは中国市場の重要さを認め、「われわれは中国に残る必要がある」と語った。
ハリウッド映画も中国をネガティブに描けなくなった
中国の脅威を正しく知らされていない人々が世界中に存在するのは、ニュース報道だけの責任ではない。自主規制は、ニュースと並んで世論形成に大きな役割を果たしているエンターテインメント産業にも広がっている。
中国市場への参入を望んでいるテレビ局や映画会社は、中国政府を怒らせないように細心の注意を払わなければならない。映画やテレビ番組の中で一作でも中国をネガティブに描いたものがあれば、その会社の作品すべてが中国でボイコットされる危険がある。これが暗黙のルールである。その結果、少なくとも、自主規制をおこなう経営者の頭の中では、中国という巨大市場で成功したければすべての作品で中国をポジティブに描かなければならないということになる。
映画会社やテレビ局がそんなことを本気で心配しているのだということを理解するためには、MGMスタジオが『若き勇者たち』(※原題は『Red Dawn』(赤い夜明け)。リメイク版の邦題は『レッド・ドーン』)を2012年にリメイクしたときのことを知るだけで充分である。1984年のオリジナル版は、ソ連がアメリカの小さな町に奇襲攻撃を仕掛け、勇敢な少年たちが赤い脅威(原題はこれに由来する)を撃退するために立ち上がる、というストーリーだった。
リメイク版では、すでに崩壊したソ連に代わって、中国を侵略者として描くことが想定されていた。ところが、中国でこのリメイク版について否定的な報道が出始めると、MGMは映画プロデューサーに指示して侵略者をデジタル処理で「非中国化」してしまった。この自主規制の最も興味深い点は、MGMが中国政府からの公式な抗議によって変更を加えたわけではないことである。実際、抗議は一切なかった。MGM広報によれば、それは単に「今やアメリカ映画の主要なマーケットとなった中国での興行収入を上げるため」の変更だったという。
研究・教育機関にも自主規制が広がっている
最後に、自主規制が思いもよらない分野にまで及んでいることを明らかにしておこう。思いもよらない分野とは、研究や教育である。米中委員会委員ウェッセルはこう述べている。
学術研究はビジネスの要素を増しつつある。大学は常に研究費を探し求めている。残念なことに、研究費が中国系団体から出ているケースが次第に増えてきた。研究費を出すことによって、中国はアメリカの大学に効果的に広告を出していることになる。その結果、残念なことに、大学が多額の人民元に手を差し出すようになるにつれて、中国批判を控えるという微妙な自主規制が生まれた。
しかし、研究・教育機関の倫理的堕落は、研究費ほしさの自主規制だけに留まらない。いわゆる孔子学院が大学のみならず小学校から高校に至るまで、さまざまな学校に入り込んで増殖していることも頭の痛い問題である。
中国政府から資金を得ている孔子学院は、資金難に苦しむアメリカの公立学校に中国語や中国文化の授業や中国語のカリキュラム開発や交換学生プログラムなどを無償で提供しているが、「中国のプロパガンダや主義主張をアメリカの子供たち、つまり、最も影響を受けやすい世代のアメリカ国民に植え付けようとしている」として厳しい批判にもさらされている。ウェッセルは言う。
こうしたプロパガンダは、教授たちの著作や、将来の社会政策の担い手である学生たちの意見に劇的な影響を与えてきた。これは巧妙で効果的な、アメリカの利益にとってはきわめて有害なプロパガンダだ。
現実から目を逸らしてはいけない
締めくくりに、この最終章のテーマをおさらいしておこう。急速に台頭する中国によって引き起こされた深刻な安全保障上の脅威に平和的に対抗するには、第一に、経済的・軍事的その他の対抗策について政治的な合意ができていなければならない。だが、自由で聞かれた民主主義国家においてこうした政治的合意に到達するのは至難の業だと思われる。経済的利害は対中貿易との関わり方によって異なるし、利益団体は大義のために団結するより対立し合う道を選びがちである。独裁的な中国政府は外国の中国報道に強力なメディア統制を敷き、西側のジャーナリストや大学は一貫して自主規制をおこなっている。
この分裂状態こそが、「対中戦争の可能性について考えるべきだ」という政治的合意の形成を西側の民主主義国、特にアメリカで長い間阻んできた元凶である。言うまでもないことだが、現実から目を逸らすというこうした状態がこのまま続けば、物語の結末はわれわれ全員にとって苦いものになるだろう。
もちろん、今ならまだ間に合う。戦争よりも遥かにましな、遥かに平和的な方法で問題を解決する道はある。真実が明らかになり、リスクの大きさ、壊滅的被害の及ぶ範囲の大きさを中国人とわれわれの双方が完全に理解できるようになりさえすれば、希望は見えてくる。
平和が栄えるためには、この真実が自明の理となる必要がある。この真実を探究することこそが本書の目的だった。この精神に則って最後に、スペインの哲学者ジョージ・サンタヤーナの格言「過去を記憶できない者は、過去を繰り返すよう運命づけられている」を逆にした言葉を掲げ、本書を締めくくることにしよう。「将来どんなことが起こり得るかをすべて想定できる人間には、その中から最善のものを選び、最悪のものを避ける、最上のチャンスが与えられている」
「日本の安全をどう守るのか」
日本の自衛隊がソ連軍による着上陸を念頭に置いて、北海道を中心にして展開していたのは、今は昔の話である。
現在、陸・海・空の各自衛隊は、東アジアの海洋でプレゼンスを強化している中国軍を睨みつつ、南西地域に重点を置いた展開を推進している。
本書は、近年の中国の海洋進出にともなって、変化する太平洋地域の戦力バランスを分析しながら、「米中戦争はあるか」「あるとすれば、どのように防ぐことができるのか」を、一般読者に向けてわかりやすく論じた優れた地政学の本である。
本書ではもちろん尖閣諸島をめぐる日中のつばぜり合いや日本に展開する米軍の基地(佐世保、横須賀、横田、嘉手納など)の脆弱性などが、米国の立場から書かれているが、日本の自術隊がどのような戦略のもとに、中国の海洋膨張政策に対峙しているかにはあまり紙幅が割かれていない。本稿では、「解説」の形をとりながら、日本から見た防衛戦略について記したいと思う。
尖閣諸島周辺の日本の領海に、中国の公船が初めて姿を現したのは、2008年12月のことである。ほぼ同じころに、中国が島嶼の領有権や海洋権益をめぐってフィリピンやベトナムなどと争っている南シナ海でも中国公船の活動が活発化していることから、この時期から中国の海洋膨張政策が、様々な衝突をうみながら、国際社会に立ちあらわれたということがいえるだろう。
尖閣諸島周辺に莫大な石油が埋蔵されている可能性を指摘する調査結果が、1968年に発表された。急速な成長の結果として、中国経済は、中東やアフリカから輸入される石油への依存を強めており、その輸送には、米国の制海権下にあるマラッカ海峡をとおらねばならない。この「マラッカ・ジレンマ」を緩和することも、中国が尖閣と東シナ海にまたがる海底に存在している石油の確保を目指す、理由の一つになっている。
その尖閣の領有を実現するために、本書にもあるようにまずは地図を書き換え、漁船を送り込み、サラミをスライスするように徐々に支配を拡大していくというのが中国の戦略である。
中国は、1996年の台湾における総統選挙に際して、中国が独立派と見なしている李登輝に投票しないようメッセージを送るために、台湾の近海に弾道ミサイルを撃ち込む演習を行った。これに対して、米国は空母インディペンデンスと空母ニミッツを中心とするふたつの艦隊を派遣し、中国は矛を収めざるをえなかった。
この時の蹉跌が、中国に、アメリカの空母打撃群に対抗する対艦弾道ミサイルなどの「非対称兵器」の開発を促したという本書の見方は的を射たものである。
ハッキングによって先進諸国から軍事技術の主要部分を盗み、そのコピーによって高性能な国産兵器をつくりあげる。黄海、東シナ海、尖閣諸島、南シナ海を内側に含む第一列島線への進出を、本書に書かれてあるように、移動式で精密攻撃が可能な弾道・巡航ミサイル、潜水艦などの強化によってなしとげつつある中国に対して、自衛隊はどのような対応をとってきているのだろうか?
冒頭で書いたように、もともと自衛隊はソ連による侵攻を念頭に置いていた。しかし、冷戦の崩壊と、経済成長にともなう中国の海洋進出が顕著になった2000年代以降、自衛隊の態勢は北から南へと重点をシフトしてきている。
福岡の築城(ついき)基地に所属していた主力戦闘機F‐15、約20機からなる飛行隊を沖縄に移転したのはそのひとつである。これは、東シナ海上空における中国軍機の活動が活発化していることに伴って、南西空域におけるスクランブル(緊急発進)の回数増大に対応するためである。また、陸上自衛隊は与那国島に沿岸監視隊を設立しており、今後は南西諸島への地対艦ミサイル部隊の配置が検討されている。佐世保には、海上からの上陸作戦を主たる任務とする水陸機動団が新設されるなど、陸自は離島奪回能力を向上させつつある。
海上自衛隊は、保有する潜水艦を16隻から22隻へと増加させつつある。より多くの潜水艦を南西海域で運用することにより、中国の潜水艦や水上艦艇などに関する情報収集や偵察監視能力が向上することが期待される。また有事においては、南西海域での海上優勢を確保するうえで、これらの潜水艦が重要な役割を担うことになろう。海上自衛隊は、高性能のレーダーを装備し、多数の敵戦闘機や対艦ミサイルなどに同時に対応できる高い防空能力を有しているイージス艦の改修も進めている。特に弾道ミサイル防衛能力の強化が図られており、日本本土に対する弾道ミサイル攻撃への対処能力の向上につながるだろう。
拡張する中国に対して、米国は、アジア太平洋地域における同盟国との防衛協力を強化している。その結果、日米の防衛協力はこの数年で顕著に進展している。たとえば、東京都の府中にあった航空自衛隊の航空総隊司令部を、在日米空軍の司令部がある横田に、2012年に移転したのもそのひとつだ。陸上自衛隊で有事における初動対処を担うことになる中央即応集団も、その司令部を、在日米陸軍司令部があるキャンプ座間へ移転した。米軍と自衛隊が、主要な部隊の司令部を同じ場所に置くことで、作戦時における相互の連携強化が目指されている。
本書は、米軍が日本や韓国などアジア地域で運用する基地が固定されているために、中国のミサイル攻撃に脆弱である旨を指摘している。これは鋭い指摘で、PAC3などの地対空ミサイルを配備し、迎撃しても、異なる方向から多数のミサイルが飛来した場合、その全てを打ち落とすことは難しい。したがって、そうしたミサイルが着弾しても基地が稼働できるよう、主要な施設や装備を非常に厚いコンクリートで保護することや、破壊された滑走路などの施設を早急に復旧させる能力の向上といった、「抗堪化」の推進が必要になっている。
本書の中ではもうひとつの戦略思想の転換が提示されている。すなわち空母主体の現在の米海軍の態勢を改め、潜水艦を主体にし、第一列島線の海峡(チョークポイント)で中国を封鎖するという「オフショア・コントロール」の考えである。
この潜水艦への戦略移行は、たしかにアメリカにとっては安上がりな解決かもしれないが、第一列島線上に位置する日本にとっては死活問題になる。これは第一列島線で、石油などの輸入を阻止することで、中国を干上がらせるという発想だが、そうした事態まで中国を追い込むには相当の時間がかかる。その間に中国は、封鎖の突破を目指して、本土で無傷のまま温存されているミサイルなどの兵器を用いて、第一列島線に存在する敵の軍事基地や政経中枢への攻撃を行うことが想定される。
また、中国領内に進入できる長距離爆撃機を米側が持つことが、事態の安定につながるという本書の主張の妥当性はどうだろうか?
中国の内陸部にある軍事的なアセットを着実に破壊できる能力を持つことによって、中国による挑発的な行動、挑戦的な行動を抑え込む。それが「エアシーバトル」の抑止の考え方だ。そのためには長距離を高速で飛行し、敵のレーダーから探知されにくいステルス性能を備え、中国の内陸部も攻撃できる爆撃機を持つというのは合理的な結論である。実際、ステルス性の高い長距離爆撃機をアメリカは保有しており、それが中国本土を叩くことができるという事実が、抑止力の一部となっているのである。
それでは日本も持てばいいではないか、と読者は思うかもしれない。しかし、日本がこうした長距離爆撃機を持つことは想定できない。なぜならば、憲法9条の下で、性能上専ら他国の国土を壊滅的に破壊するような攻撃的兵器を日本は持てないからだ。自衛隊は「専守防衛」の思想のもと、攻撃されないための防衛的な兵器のみを所有しているということになる。
こう考えていくと、米軍のアジア太平洋地域におけるプレゼンスは、日本にとっては文字通り死活的に重要な傘ということになる。
第二次世界大戦では、アジアの覇権国になろうとした日本を、アメリカは石油の禁輸などの手段をつかって抑止しようとしたが、結局は失敗し、戦争になった。その後のアジアで、強力な海軍力をもった国は、中国が2000年代に南シナ海や東シナ海に進出するようになるまでは、出現しなかった。
その意味で、現在アジア地域は、戦後初めてアメリカ以外の国が覇権国たるべく拡張してきたその試練をうけている。
本書が記す、フィリピンが領有権を主張しているスカボロー礁を失った経緯に愕然としたかたもいるのではないか。2012年4月に「中国漁船団」の侵入によって始まったこの奪取劇。中国は、フィリピン製品の輸入制限や、フィリピンヘの事実上の渡航制限によって中国経済に依存していたフィリピンを追い込む。アメリカの仲介で、2012年6月に両国は当該地域から撤退することが決まったにもかかわらず、中国はそのまま居すわり続け、礁のコントロールを握ることになった。
本書『米中もし戦わば』は、米国、中国のみならず、ベトナム、フィリピン、台湾、韓国、北朝鮮、そして日本といった国々のパワーバランスのなか、中国が何を狙い、何が同盟国の側に足りないのかを、わかりやすく書いている。
沖縄の基地問題や集団的自衛権の問題も、こうした大きなコンテクストのなかで考えていくと、その糸口が見つかるかもしれない。
本書の筆者であるピーター・ナヴァロはトランプ政権の中枢に入り、米中貿易戦争を主導するなど、トランプ政権の対中政策に大きな影響力を発揮している。今後の米中関係を見通すうえでも、本書は重要な示唆を与えてくれるだろう。
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/18ee3a30.4414d26a.18ee3a31.c19ed0eb/?me_id=1251035&item_id=17388966&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fhmvjapan%2Fcabinet%2F9614000%2F9613983.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
