日中友好侵略史
門田隆将さんは「はじめに」を、安倍晋三元首相がテロリストによって暗殺されたことから書きはじめています。
テロリストの動機が解明されることを望みつつ『真の動機を解明するには、想像以上の時間が必要かもしれないし、あるいは、永遠に明らかならないかもしれない。しかし、たしかなのは、安倍晋三元首相は、覇権国家・中国にとって「最大の難敵」だったという事実である。習近平中国国家主席、いや、中国共産党にとって「安倍晋三」ほど厄介で、巨大な壁は、ほかに存在しなかった』と指摘しています。
さらに『本書で七十年前から始まり、現在に至る中国共産党の「対日工作」の実態を描かせていただく。日本の政界、官界、財界、マスコミ……日本の主要分野は、ほとんど中国の工作で自在に操られ、自由民主党ですらおよそ八割を「親中勢力」が占めると言われている。』『
政治家・安倍晋三は、中国支配の日本政界にあってこれに疑問を呈し、真っ向から勝負し、卓越した理論と独特のキャラクターで親中派が自由に動けない政治状況をつくろうとした。』と書き、『多くの読者に安倍元首相の、そして私の“本気の危機感”を共有していただけたなら、本書を世に問うた意味があるのではないかと思う。』と結んでいます。
門田隆将さんの「日中友好侵略史」を紹介するために、以下に目次や目を留めた項目をコピペさせていただきます。
興味が湧いて、他も読んでみたいと思ったら、本書を手にしていただければと思います。
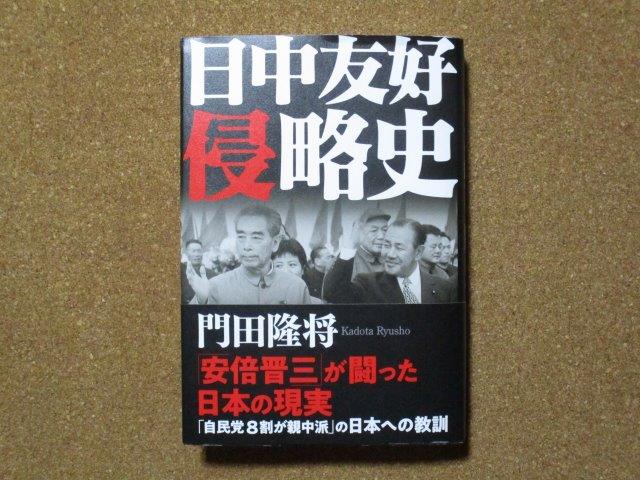
目次
はじめに 1
プロローグ 8
第一章 始まった「対日工作」 15
第二章 自民党工作のスタート 37
第三章 公明・創価学会への中国工作 48
第四章 権力抗争はこうして始まった 65
第五章 世界の流れが変わった 84
第六章 もう一人のキーマン 97
第七章 「中国」巡って政界大動乱 118
第八章 日華断交は可能なのか 131
第九章 「椎名特使」をめぐる攻防 161
第十章 台北の怒りと混乱 179
第十一章 “丸裸”だった日本 208
第十二章 始まった「日中友好絶対主義」 253
第十三章 世界を驚愕させた人権弾圧 263
第十四章 変貌する中国 279
第十五章 ハニートラップの凄まじさ 288
第十六章 「破壊者」登場の悲劇 303
第十七章 不可避だった“米中激突” 324
第十八章 「友好」に踊った五十年 339
エピローグ 360
おわりに 372
参考文献 378
はじめに
日中国交正常化五十周年まで二月余りとなった二〇二二(令和四)年七月八日、奈良県奈良市の近鉄大和西大寺駅の近くで参院選の応援演説をしていた安倍晋三元首相(六七)が背後から銃撃されて帰らぬ人となった。
世界を震撼させた衝撃事件だった。
犯人は奈良市在住の山上徹也(四一)である。旧統一教会(世界平和統一家庭連合)に母親が全財産を取られたことを恨みに思い、同教会と安倍元首相が親しいと思い込み、「犯行に及んだ」というのである。
安倍元首相と旧統一教会は、何の関係もない。しかし、逮捕直後から山上は、ぺらぺらと動機をしゃべり、「政治目的ではない」とわざわざ明かしている。
本当の動機を知られたくない場合、容疑者が別の動機を語り、捜査を違う方向に持っていこうとするのは、捜査の関係者からすれば常識だ。
しかも、山上は犯行前日未明に同団体の施設に銃弾を撃ち込むという“アリバイ”づくりをしており、「動機」には多くの専門家が首を傾げた。
真の動機を解明するには、想像以上の時間が必要かもしれないし、あるいは、永遠に明らかならないかもしれない。
しかし、たしかなのは、安倍晋三元首相は、覇権国家・中国にとって「最大の難敵」だったという事実である。
二〇二一年八月、イギリスの最新鋭空母「クイーン・エリザベス」が日本に来て、日本、アメリカ、イギリスに加え、オランダも参加した画期的な合同軍事演習がおこなわれた。それについて述べた安倍元首相の言葉が印象的だ。
「かつて“ABCD包囲網”がありましたが、その“C”が“J”に代わったという意味があるのかな、と思いました」
日本の戦後レジームと戦い、これを脱却させるために突き進んだ安倍元首相は、“ABCD包囲網”の中の「C」、つまり中国の代わりに「J」、すなわち日本が入ることを念頭に置いていたことがわかる言葉である。
この言葉は重い。習近平中国国家主席、いや、中国共産党にとって「安倍晋三」ほど厄介で、巨大な壁は、ほかに存在しなかったからだ。
防衛省や自衛隊の幹部と情報交換していると「安倍さんほど“本気の危機感”を持っていた政治家はいなかった」という話が返ってくる。そして「自由主義圏の首脳たちの認識を変え、大戦略まで変えてしまった政治家こそ安倍さんだ」と。
まさに中国が安倍を嫌がった理由がそこにあった。
今では自由世界の基本戦略となっている「自由で開かれたインド太平洋」戦略。アメリカにも、欧州にも、中心的な戦略として受け入れられているこの基本構想を、ほかの言葉で言い換えるなら、「対中包囲網戦略」である。まさに「ABJD包囲網」なのだ。
アメリカのオバマ大統領をはじめ、ヨーロッパの首脳たちが、それまで疑いなく信じていた「中国は責任ある大国として付き合っていける」という考え方を根本的に変えたのがこの安倍構想である。
「中国をみくびってはいけません。中国共産党が目指すものは何か。その本質は何か。このままでは日本も、世界も大変なことになります」
世界のリーダーたちは、安倍の“本気の危機感”に次第に揺り動かされていった。口で言うだけでなく、支持率がたとえ十ポイント以上、下がっても、安倍は危機に真っ向から向き合うために「平和安全法制」を成立させ、世界の指導者たちを驚愕させた。
オバマを説得し、さらにそのあとのトランプ大統領も説得に成功した。まだ大統領就任前にトランプ邸に乗り込み、中国の脅威について話し込んだのだ。
初対面なのに、話のほとんどを中国問題に費やし、なおかつ安倍はトランプを「取り込んだ」のである。
安倍が首相に返り咲いた二〇一二(平成二十四)年、ほぼ同時に国家の領袖になった習近平は最初からこの厄介な敵・安倍晋三と対峙しなければならなかった。安倍が着々と進める対中包囲網に対して、指をくわえて見るしかなかった習近平の焦りは相当なものだっただろう。
中国の横暴を放置するなら、日本の防衛、そして地域の平和と安定は維持できない。南シナ海の力による現状変更に止まらす、習近平は必ず台湾を併合しようとする ―― 安倍晋三の“本気の危機感” は、吉田茂以来の「軽武装 経済重視」国家として歩んできた戦後日本を「根本から変えた」のである。
前述のように二〇一五年九月、「平和安全法制」を成立させ、日米同盟をそれまでの片務的なものから双務性のあるものに進化させた安倍は、これまでにないアメリカの信頼を獲得し、明確に安全保障政策を国家の「一丁目一番地」に据えた。
そして二〇二二年、ロシアのウクライナ侵略という戦後秩序の破壊がおこなわれた中、防衛費をGDP(国内総生産)比ニパーセントヘと導く道筋を着実に整えていった。
だが、東アジアのみならず世界の安全保障に欠くことのできない政治家・安倍晋三は、考えられないほど杜撰な奈良県警の警備によって「命を奪われた」のである。
私は、本書で七十年前から始まり、現在に至る中国共産党の「対日工作」の実態を描かせていただく。日本の政界、官界、財界、マスコミ……日本の主要分野は、ほとんど中国の工作で自在に操られ、自由民主党ですらおよそ八割を「親中勢力」が占めると言われている。
そこまで築き上げるのに中国共産党がどれほど努力し、執念をもって「対日工作」をつづけたか、私は詳細にお伝えしたい。その過程で籠絡されていった日本の政治家や経済人の情けないありさまを、しっかりと脳裡に焼きつけて欲しいと思う。
政治家・安倍晋三は、中国支配の日本政界にあってこれに疑問を呈し、真っ向から勝負し、卓越した理論と独特のキャラクターで親中派が自由に動けない政治状況をつくろうとした。
私は、同じ思いを共有し、この本を書き上げた。しかし、本書を最も読んで欲しかった安倍元首相は、この世にいない。
安倍の死で、台湾への中国の軍事侵攻の危険度は確実に上がった。平和を愛する多くの人々の努力によって押しとどめられてきた中国による台湾軍事侵攻は、「あるかないかではなく、いつあるかの問題」となっている。
したたかな中国共産党は、いま現在もあらゆる工作を、日本で、台湾で、そして全世界で展開している。そのやり方はどんなものなのか、防ぐにはどうしたらいいのか、多くの日本人に本書を手にとってもらい、過去の日本でどんなことがあったのか、その目で確かめて欲しい。
そして政治家・安倍晋三が、なぜそうまでして中国と対峙しようとしたのか、是非、知っていただきたい。本書は、日本政治史上、比類なき功績を残した安倍晋三元首相に捧げる日中友好の「侵略史」である。
多くの読者に安倍元首相の、そして私の“本気の危機感”を共有していただけたなら、本書を世に問うた意味があるのではないかと思う。
日中国交正常化五十周年 盛夏
門田隆将
周恩来はすべてを知っていた <第十一章 “丸裸”だった日本 の一節>
到着から一時間が経った午後十二時半、田中首相一行は中南海にある迎賓館に到着した。
長安街通りに面した豪壮な新華門を入ると、そこは要人たちの住まいや執務所、外国賓客を迎える賓館など、人民が一歩も踏み込むことができない特別エリア「中南海」になる。
故宮の西側を占めるこの広い敷地には「中海」「南海」と呼ばれる池よりは大きい二つの“湖”があり、景色は抜群だ。毛沢東の居住する家も、周恩来の家も、そしてその執務室もすべてこの中にある。
ちなみに北側には「北海」があり、ここは人民にも開放されており、今でも貴重な憩いの場・北海公園として、ボートに乗る中国人の姿が見ることができる。
宿舎は迎賓館の「第十八楼」。黄色いタイル張りで、瓦葺きの重層な建物である。玄関には、日の丸が掲げられていた。
一行は、ダムの風景画がかけられている広い応接室に案内された。足元には、赤い花模様の絨毯が敷き詰められている豪華な部屋である。
ここで一行は、そのまま代表団の紹介に臨んだ。周恩来が訪中をねぎらって、日本の政府関係の一人一人と握手をしていったのである。
マスコミは長安街通りに面する民族飯店が宿舎となっており、そちらに案内されている。ここにいたのは、田中、大平、二階堂といった政治家や官僚、秘書官など、コア・メンバーのみである。その時、驚くべきことがあった。
明かすのは小長啓一秘書官である。
「迎賓館に着いた私たちは、代表団の紹介というので一列に並んで、周恩来さんの挨拶を受けることになりました。周恩来さんが一人一人握手をしてまわるという感じです。最初に田中さん、そして大平さん……という感じで、私たちは末席の方でした。十数人だったと思いますが、順番に一人一人をまわって周恩来さんが握手をしていったんです」
やがて小長の番が来た。驚いたのは、その時だ。
「私の顔を見て、周恩来さんがいきなり“あなたが列島改造論のゴーストライターですね?”と仰ったんです。えっ? と思いました。私は、頷くような、頷かないような、そんな感じで、びっくりしてしまったんです。そこまで調べているのか、と。“まずいな”というよりも“すごいな”という感じの方が強かったですね。周恩来さんの言葉はすべて中国側の通訳の人が訳していました」
大平の秘書官、森田一もこの時、周恩来と握手した。
森田も同じ体験をしている。
「中国側は秘書官の名前も全部、わかっていたんですよ。だって、周恩来さんは、僕に“森田さん”と言ったんです。事前に勉強しているんですよ。一人一人について全部わかっているような感じでしたね。途中で、この交渉を通じて、なにか仕組まれているような気がしたのは事実ですね。でも、そう思ったのは、あとからのことですよ。この時は、まだ全然、気づきませんでした」
周恩来の挨拶を受けた十数人は、前述のように日中国交正常化のために動いたコア・メンバーである。そのメンバーが集合して周恩来の挨拶を受けた時、一人一人のことがすべて周恩来には「頭に入っていた」ということになる。
これは、何を意味するのだろうか。
すべてを調べ上げて国交正常化に向けて緻密な戦略を練っていた中国。一方の日本は、中国の事情を知ることもなく、この場に「飛び込んできている」のである。
私は、森田に尋ねた。
「中ソ対立が極限まで達し、北京や上海では、当時、ソ連の核攻撃に備えて避難訓練もおこなわれていました。また、文化大革命による破壊で、あらゆるものが機能不全になり、中国全土“荒野”と化していたことはご存じでしたか」
森田の答えは、こうである。
「いま分析すると、中ソ対決の情報が欠けていたと思いますね。それに文化大革命で中国が荒廃しつくしていることも知りませんでした。橋本中国課長がそういう情報を取っていなかったか、上げていなかったかということでしょう」
国交を樹立しようという時に、田中政権はすでに“決定的な失敗”を犯していたのである。
中国側の調査は訪中記者団にも、及んでいた。
記者たちもまた、似たような経験をしているのだ。この時、訪中記者団の一員として北京に来ていた中日新聞の大林主一は、こう語る。
「記者団は全部で八十人ぐらいいたと思います。記者たちのことも全部調べていましたよ。中日新聞は五人で行きました。そこに新華社の女性記者がついたんですが、その記者が私たちの経歴を全部、知っていたんです。よく調べているなあ、と思いました。
もちろん、こっちが原稿を送るのも、全部、見られていましてね。当時はファックスがまだなくて、ようやく直通電話ができた頃なんですよ。だから原稿は読み上げて電話で送るわけです。原稿は膨大だから全部やるのは時間がかかるんです。その電話を聴いているわけです。向こうはこっちが送っている中身は全部わかっているな、という感じでした」
人民大会堂の「安徽省の間」で第一回の首脳会談が聞かれたのは、午後三時からだ。
いきなり一時間四十分にわたる会談となった。用意周到な中国と準備不足の日本との差は、この第一回会談から、すぐに明らかになった。
この時の模様は、情報公開法に基づき読売新聞が外務省に開示を求めて公開された文書「田中総理・周恩来総理会談記録」が詳しい(政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所 データベース「世界と日本」より)。
参加者は、日本が田中、大平、二階堂官房長官、橋本恕(外務省中国課長)、中国側は周恩来、姫鵬飛外交部長、廖承志(外文部顧問)、韓念龍(外交部副部長)だ。
冒頭から田中はこう発言している。
「日中国交正常化の機は熟しました。今回の訪中を是非とも成功させ、国交正常化を実現したい。これまで国交正常化を阻んできたのは台湾との関係です。日中国交正常化の結果、自動的に消滅する関係とは別に、現実に起こる問題に対処しなければなりません。
これをうまく処理しないと、国内にゴタゴタが起こります。日中国交正常化を実現するときには、台湾に対する影響を十分考えてやるべきです。国交正常化は、まず共同声明でスタートし、国会の議決を要する問題はあとまわしにしたいと思います」
すでに台湾のことを“自動的に消滅する関係”と表現しているから驚く。さらに、これを受けて大平が重要発言をおこなった。
「国交正常化をなしとげ、これをもって、日中両国の今後長きにわたる友好の第一歩としたいと思います。国交正常化が、わが国の内政の安定に寄与するよう願っています」
そう前置きした大平は、二つの問題点を挙げた。日華平和条約の問題と第三国との関係である。
「中国側がこの条約を不法にして無効であるとの立場をとっていることも十分、わかります。しかし、この条約は国会の議決を得て政府が批准したものであり、日本政府が中国側の見解に同意した場合、日本政府は過去二十年にわたって、国民と国会をだまし続けたという汚名を受けねばなりません。そこで、日華平和条約は国交正常化の瞬間において、その任務を“終了した”ということで、中国側のご理解を得たいのです。
第二点は第三国との関係です。特に日米関係は日本の存立にとり極めて重大です。また、米国が世界に多くの関係をもっているが、日本の政策によって、米国の政策に悪影響が及ぶことがないよう注意しなければなりません。つまり、日中国交正常化をわが国としては対米関係を損ねないようにして実現したいと思います。日中国交正常化後の日台関係については、日台の外交関係が切れた後の現実的な関係を、やることと、やらないこととのケジメをはっきりさせて処理したいと思います」
日本側は、冒頭から台湾との関係を清算し、日華平和条約は日中国交正常化が成った瞬間に「終了する」と申し出たのである。
周恩来は、この時点で“勝利”を確信しただろう。
なんとか国交正常化を成し遂げたい日本。国交正常化で利益を得たい中国。恩を着せる形で交渉を進める中国側の基本形は、最初の会談から明らかだった。周恩来は、自国の疲弊がばれないように内心は汲々としていたに違いない。しかし、そんなことに気づく訪中団の人間は一人もいなかった。
共同声明は発表された <第十一章 “丸裸”だった日本 の一節>
一九七二年九月二十九日午後十一時二十分 ―― 。
日中両国は、日中共同声明を発表した。その後の日中関係を決定づけるものである。
〈日中両国は、一衣帯水の間にある隣国であり、長い伝統的友好の歴史を有する。両国国民は、両国間にこれまで存在していた不正常な状態に終止符を打つことを切望している。戦争状態の終結と日中国交の正常化という両国国民の願望の実現は、両国関係の歴史に新たな一頁を開くこととなろう。
日本側は、過去において日本国が戦争を通じて中国国民に重大な損害を与えたことについての責任を痛感し、深く反省する。また、日本側は、中華人民共和国政府が提起した「復交三原則」を十分理解する立場に立って国交正常化の実現をはかるという見解を再確認する。中国側は、これを歓迎するものである。
日中両国間には社会制度の相違があるにもかかわらず、両国は、平和友好関係を樹立すべきであり、また、樹立することが可能である。両国間の国交を正常化し、相互に善隣友好関係を発展させることは、両国国民の利益に合致するところであり、また、アジアにおける緊張緩和と世界の平和に貢献するものである。 〉
妥協を許さない中国側の姿勢によって、まさに“全面勝利”の文言が並んだのである。
その後、中国がくり返し起こす「歴史認識問題」で、中国が居丈高に日本を責め、“指導”する図式の根源は、ここにに起因する。ここでは省略するが日中共同声明には「九項目」の合意事項が並んでいる。これもまた、日本側の全面譲歩によって成立したものである。
そこでは、日本は中華人民共和国政府が「中国の唯一の合法政府」であることを「承認」し、中華人民共和国政府が「台湾が中華人民共和国の領土の不可分の一部」であることを「重ねて表明」し、日本はその立場を「十分理解し、尊重する」ことを明らかにしている。
日本が命脈をぎりぎり保ったのは、台湾を自分の領土と主張する中国に対して、その立場を「理解」し、「尊重」するものの、「認めた」わけではない、ということである。
簡単にいえば、「あなたの主張は尊重するし、理解していますよ」ということであって、それを「承認」するわけではない、ということだ。
日本側は、そこだけは「譲らなかった」のである。
九月二十九日、調印式終了後、大平正芳外相と二階堂進官房長官は民族飯店に設けられていたプレスセンターでの記者会見に臨んだ。紆余曲折の末の共同声明である。記者たちの注目は、最後まで攻防が続いた台湾問題にあった。
「四日間にわたる日中両国首脳会談の成果として、本日、日中国交正常化が実現することになりました。長らく日中間に存在していた不正常な関係に終止符が打たれたのです」
大平外相は、記者会見でそう語り始めた。いつも無表情な大平にしては、やや上気した雰囲気が記者たちには印象的だった。
共同声明の重要な部分を大平は順を追って話していった。やがて話が台湾問題に及んだ。
「台湾問題に対する日本政府の立場は、第三項に明らかにされておるとおりであります。カイロ宣言において、台湾は中国に返還されることが謳われ、これを受けたポツダム宣言、この宣言の第八項には、カイロ宣言の条項は履行されるべし、と謳われております。このポツダム宣言を日本が承諾した経緯に照らせば、政府がポツダム宣言に基づく立場を堅持するのは当然のことであります」
そして、大平は姿勢を正して宣言した。
「なお、共同声明の中には触れられておりませんが、日中関係正常化の結果として、日華平和条約は、存続の意義を失い、終了したものと認められるというのが日本政府の見解でございます」
大平の表情がテレビを通じて会見を見守る国民の目に飛び込んできた。存続の意義を失い、終了した ―― その瞬間、細い大平の目がカツと見開いた。
記者たちもたじろぐ迫力だった。記者たちの質問が飛んだ。
「台湾の在日大使館、台北の日本大使館、これらは閉鎖し、引き揚げるということだろうと思います。これの具体的な期限、あるいはこいう措置はいつ、おこなわれるのですか」
大平が答える。
「日中国交正常化の結果といたしまして、台湾と日本との間の外交関係は維持できなくなります。従って、在台日本大使館は閉鎖せざるを得ないと思います。その具体的な時期はそう遠くない将来である、とご理解いただきたい」
田中角栄の政治家としての「功名心」、そして大平正芳の戦前からの「贖罪意識」―― この二つが創り出した“成果”は、やがて「日中友好絶対主義」へと発展し、日本の存続すら懸念される事態へと発展していくことを誰がこの時、想像し得ただろうか。
すべてを変貌させた江沢民 <第十四章 変貌する中国 の一節>
そのスピーチが始まった時、宮中晩餐会の出席者、いや、テレビの中継を見守っていた日本国民は、わが耳を疑った。
一九九八(平成十)年十一月二十六日、天皇の歓迎スピーチのあと、黒い中山服をまとった江沢民・国家主席が“常識外”のことを言い始めたのである。
「中国と日本は“一衣帯水”の隣邦であり、両国人民は二千年余りの往来の中で厚い友情を結びました。長年、両国人民はお互いに学び合い、お互いの長所を参考にし合いながら、それぞれ自国の発展を促しました」
そう前置きした江沢民は、こう言ってのけたのである。
「不幸なことに、近代史上、日本軍国主義は対外侵略拡張の誤った道を歩み、中国人民とアジアのほかの国々の人民に大きな災難をもたらしました。日本人民も深くその害を受けました。“前事を忘れず、後事の戒めとする”という言葉があります。われわれは、この痛ましい歴史の教訓を永遠に酌み取らなければなりません」
えっ? なんだって? 驚いた国民は言葉を失った。
何というスピーチか。宮中晩餐会は、政治や外交交渉の場ではない。天皇・皇后両陛下が日本国民になり代わって国の賓客をもてなす場である。心のこもった天皇の歓迎スピーチのあと、招かれた側の客が、
「あんたの親父には、ひどい目に遭った。過去にあんたたちはこんな過ちをしたんだ。そのことを忘れず、今後はこういうことのないように心せよ」
そう言っているのである。
常識のある大人として、どこかの家に食事に招かれた時、“お前の親父にこんな迷惑を俺たちは受けたんだ”などと言う人がいるのか。
しかも、その場に、中国人が決然とした意志を示す時に着る「中山服」で出てきて、この“非礼”をやってのけたのである。
心ある日本人は呆れ、怒り、騒然となった。日本中を怒りの中に放り込んだ江沢民は、自らが巻き起こした波騒を気にすることもなく、精力的にスケジュールをこなしていった。
江沢民は、早稲田大学での講演会や、各種の記者会見など、都合六日間の滞在でさまざまな言葉を残していった。どの場でも強調したのは、以下のことだった。
「日本軍国主義は全面的な対中国の侵略戦争をおこなった。このことを日本人は忘れてはならない。中国では軍民あわせて実に三千五百万人が死傷し、六千億ドル以上の経済的損失を被った」
「日本は軍国主義の考え方を否定し、軍国主義の再度の台頭を絶対に防がなければならない。日本は、平和と発展の道を歩み、正しい歴史観によって国民と若い世代を導いていくべきなのである」
ありかたい言葉を拝聴するかのごとく、江沢民の言葉に耳を傾ける人々もいた。しかし、多くの日本人は、中国に対してはっきりと不快感を抱いた。日本人の中国への見方が決定的に変わったのは、この江沢民訪日だった。
あの荒野の中から日本のカネ、技術、ノウハウによって、着々と力を蓄えてきた中国。もうこれまでのように「日本の力は必要ない。お前たちは俺の言うことを聞け」 ―― 中国にかかわってきた日本人には、江の言葉がそう聞こえた。
江沢民はこう言うのも忘れなかった。
「日本では、地位の高い一部の人々が、しばしば歴史を歪曲している。日本の侵略を美化し、中国とアジア人民を傷つけているのである。日本はこれらの間違った言論と行動を抑え、正しい歴史観で青少年を教育すべきだ。これが、日中関係の発展に最も有効なことである」
この時、中国は、巧みな交渉によって「二年間で三千九百億円」という過去最大の円借款を勝ちとったばかりだった。日本側が用意した、江沢民訪日へのお土産である。
そんなことを江沢民はオクビにも出さす、ひたすら日本を“属国扱い”して帰っていった。
江沢民が始めた反日教育 <第十四章 変貌する中国 の一節>
天安門事件以後、鄧小平の抜擢によって国家主席に上り詰めた江沢民は、学生たちの民主化運動に激怒した鄧小平の指示を忠実に守った。
「失敗したのは教育だ。政府は思想政治教育を完全に怠っていた」
最高指導者の怒りを江沢民は着実に政策に生かした。「愛国教育」を始めたのである。一八四〇年のアヘン戦争以降の屈辱の百年(注=中国では「百年国恥」と呼ぶ)の悔しさを徹底して教え、中国共産党が抗日戦争と解放戦争(注=国共内戦のこと)に勝利し、人民に幸せをもたらしたことをあらためて教育していったのである。
民主化運動の中心になった大学では、特に締めつけが強化された。当時、現役の大学生だった中国人はこう回想する。
「天安門事件であっという間に大学が変わりました。入学した頃は、大学の中は自由だったんですよ。『ミッドウェイ』とか『トラ・トラ・トラ!』とかの映画を大学で観たりもしました。大学の中はすごく自由で、これが一九八九年の自由化運動に繋がっていったんです。その頃は思想教育も段々なくなっていました。ところが天安門事件があり、さらに東欧のありさまを見て、当局は“想教育をしないといけない”ということになったんです。
天安門事件の三か月後、一九八九年九月の新人生から、解放軍が学校に来て一年間の軍事教練をやるようになりました。私は夏休みに二週間訓練をやりましたので、二週間遅れで新学期が始まったんです。行進したり、銃弾を撃ったりもしました。私も実際に五発、撃ちましたよ。中国軍というのは志願制で三年間です。大学を卒業した人は少尉からですよ。しかし、いきなり思想教育が始まり、軍事教練もやるようになったんですから、本当に激変でした……」
胡耀邦時代の自由な大学キャンパスは一瞬にして「姿を消した」のである。胡耀邦とコンビを組んでいた趙紫陽は失脚し、首相にのし上がった李鵬の強権政治、そして国家主席となった江沢民が推し進めた愛国教育が中国を変貌させていく。
問題は、愛国教育とは、同時に「反日教育」であったことだ。中国を最も破壊し、侵略したのは日本であって、そこから祖国を立て直したのが中国共産党であるとの教育が徹底された。
史実に基づかない、立証もされていない行為が日本の「戦争犯罪」として糾弾され、誇張された。中国人は、子供の時から徹底的にこの日本=悪玉論を教え込まれていったのである。
江沢民は、教育部門だけでなく、思想宣伝部門を強化し、教育の場だけでなく、全党を挙げて社会全体でこれをおこなうべく、くり返し鼓舞する演説をぶっている。江沢民は、父親が日本の傀儡政権といわれた汪兆銘政権の官吏で日本軍のスパイ ―― と政敵から攻撃されたことがある。そのため、日本に敵対するのは自分自身の潔白を表わす意味もあったとされる。
社会全体が「反日」に染まる中、たとえばドラマや映画も「日本人をいかに悪く描くか」が主体となり、どのチャンネルをひねっても反日ドラマ、どの映画館に行っても反日映画ばかりという時代を迎えるのである。
二〇〇六年八月、中国では江沢民の講演録を集めた全三巻の『江沢民文選』(中国人民出版社)が刊行されている。その第二巻には、「当面の国際情勢と我々の外交工作」という講演録が収められている。
対象は、世界各国に駐在している大使たちである。彼らが「大使会議」で中国に帰国した際、北京に一堂に会した場で江沢民がおこなったものだ。時期的には、江沢民の訪日の直前にあたる。江沢民はこの時、こう語っている。
「日本とは歴史問題を重視し、これを永久に議論することが必要だ。二つの最重要課題はこの日本との歴史問題と、台湾問題である」
いかに江沢民が対日の歴史問題を意識していたかがわかる。日本にやってきた江沢民が、天皇皇后両陛下に歓待を受けたからといって、にこにこするわけにはいかなかったのである。
総理を“落とした”中国女性工作員 <第十五章 ハニートラップの凄まじさ の一節>
「このことはお断りしておきます。私は、橋本(龍太郎)総理のプライバシーを問題にするわけではありません。しかし、あなたが総理にご就任になる前後から、あなたに関する中国人との親密な交際の記事は出ておりました。その次元で、私は何も申し上げることはない。それはプライバシーの問題である。しかし、今年に入ってその女性が中国の情報部員であったという記事が出ている。したがって、私は、この民主主義国家における対外的な信頼、そして民主主義国家における国家機密というものの管理の仕方から、あなたに聞かざるを得ない」
一九九七(平成九)年十月三十日、衆議院予算委員会で新進党の西村眞悟議員がそう質問を始めた時、委員会室に独特の空気が漂った。「ついに出た」という思いと、「まさか本当に出るとは……」という相反する思いが与野党議員の間に交錯したのである。
前年からマスコミを賑わせていた橋本首相と中国の女性工作員・林玉蘭(仮名)との男女関係が、ついに国会の場で質疑されることになったのである。西村は、こうつづけた。
「橋本総理に質したいのは、くだんの中国人女性との男女の関係の話ではない。第一には、彼女が中国の情報部員だったことを知った上で接触していたのか。第二に、もし知らなかったとしたら何を彼女に話したのか、あるいは何かを依頼されたのか。そして第三に、情報部員と交際していた場合、どういう責任を感じているのかという点である。
火のないところに煙が立っているならば、国家の威信としてその煙に対処しなければならない。これは放置しておいてはならない。もし交際されておったならば、正直にお答えください。情報部員であるということを知らなかったのであれば、正直にお答えください。そして、何をしゃべったかをこの場でお答えいただきたい」
西村の口調には、有無をいわせぬ迫力がある。日頃から憂国の士として知られる西村の言葉に予算委員会は静まり返った。立ち上がってマイクの前に進み出る橋本の姿を、委員たちも、いや、テレビの前で見守る国民も、固唾を呑んで見守った。
「ただいま特定の女性と云々というお話をいただきました。確かに、中国に参りました時、衛生部の通訳として会議に列席をし、その出張もともに動き、会合すべてに同席をしておりましたから、何を話したかではなく、その席上の議論は彼女がすべてを通訳いたしております」
橋本はそう答えた。その女性を「知っている」ことをまず認めたのである。そして、
「日本に中国衛生部の関係者が参りました時にも通訳として同行しておりますから、私は確かに、本当に苦労をかけましたから、自分でご飯をご馳走したこともあります。そういう時に話したこと、これはむしろ通訳という職分からすべてを聞いております。そして当時、ベチューン医科大学の日本語教育の問題、あるいは中国医科大学の日本語教育の問題が衛生部との間で議論になっておったと私は記憶をしております」
本当か ―― 委員会室はざわめいた。「本当に苦労をかけましたから、ご飯をご馳走したこともある」と、橋本首相が自ら林玉蘭との接触を認めたのである。さらに橋本はこう語った。
「情報部員であったかどうか、知っていてつき合ったか、あるいは接したか、と。私にとりましては、中国衛生部の通訳としての存在でありました。情報部員というような思いを持って接してはおりません。むしろ情報部員だなんて思っていたら、通訳として使えないでしょう。ですから、完全に通訳として衛生部関係のすべての会議にその人は存在をいたしました」
前年から橋本と中国の女性工作員との男女の関係が何度も週刊誌の誌面を賑わせていた。その女性の前夫による「橋本との不倫関係が原因で離婚に追い込まれた」との告発も掲載され、その中で離婚に至った際、妻が橋本との関係を詳細に語ったことなどが明らかにされていた。
別の週刊誌もこの女性が中国の情報部員であることを報じ、「いつ」「どんな形で」これが国会で追及されるのか、大きな関心事となっていたのである。
西村はさらにこう追及した。
「情報部員というものは、情報部員であるということで接触してくるはずがない。だから、私は、火のないところに煙が立っているのならば、今の答弁では不十分で、彼女がどういう者であって、あなたが彼女の素性を調べたのか否かまで発表をいただかねばならない。
さらに言うなら、これはすでに国民が知っていることだ。国民が、国家の国益の観点から、あなたに答弁を求めているということである。情報部員であるということを知らずに、つき合うはずがないでしょう、という次元では、答弁にはならないのです」
西村の発言の途中で、橋本は「委員、大変恐縮でありますが、ひとつこれはお許しいただきたい」と言葉を発して、無理やり答弁に立った。
「会議に通訳として出席する人間を事前に身元を調査しろ、と言われても無理であります」
橋本はそう言った。だが、西村は納得しない。
「それはわかる。だが、プライベートでつき合ったその人のことを聞いておるのだ」
西村はさらに語気を強めた。
「通訳はすべてにある。このことで週刊誌というものを軽視してはなりません。根拠を持って書いているはすだ。そして、これは世界が見ている以上、あなたはやはり、もう少し調査の上、ご答弁をいただきたい。国益のためです。これをお願いして、私の質問を終わります」
橋本が答弁に立った。
「議員のお話は承りました。そして、最初、通訳として、そして最後まで通訳の立場で、その間、日本に来たときに、確かに私は慰労をいたしました。そして、最後に彼女が来られたのは、結婚されて、そのご主人と一緒に事務所を訪ねてくれた。そのときは通訳ではありません。結婚してご主人と来られた。そして、任地に出ていかれた。
私は、情報部員であったかどうか、全く知りません。調べるといったって、それは私、調べようがありませんけれども、通訳という仕事の性格上、初めから終わりまで、会議のその場にいるわけでありますから、すべてを知るという意味では、すべてを知る立場にあります。私は中国語はできませんから、その場におったことは全くそのとおりであります」
苦しい答弁だった。西村は最後にこう言った。
「最後に申し上げます。総理大臣のご意見は承りました。しかし、ご交際なさっていた、通訳として始めて、お食事もということは述べられた。尖閣であれ、靖国問題であれ、申し上げたあなたの、タフネゴシェーターと言われるあなたの対中国萎縮、この事態を総合すれば、国民の一人として、また議員として、危惧の念を持ってこれを質さざるを得なかったのです。
したがって“わかりません”ということよりも、日本の警察機構は非常に優秀でございまして、あなたが通訳として挨拶に来られたという方がどういう方であるか、つかんでいると私は思う。したがって、確かめてください。それをお願いいたします。質問を終わります」
日本の総理と中国の女性情報部員との関係が国会で質疑される ―― 前代未聞の事態だった。橋本は、これまでに報道されてきたことをある程度、認めた。通訳として知り合った中国の女性と個別に食事をする、その後、新しいご主人と挨拶に来て、任地に去っていったことなど、自らの口からこれを明らかにしたのである。
一国の総理になる有力な政治家にまで、中国の女性工作員の手が及んでいることを国民は思い知った。しかし、中国の不利に働くようなこのような案件が一般のテレビや新聞で報じられることは、ほとんどなかった。
あとを絶たないハニートラップの影 <第十五章 ハニートラップの凄まじさ の一節>
中国のハニートラップは、思いがけず「事件化」した時だけ、国民の耳目を集める。もちろん、それは氷山の一角である。何千件、何万件の中で、ごく稀に明らかにされるに過ぎない。
天安門事件後、国際社会の経済制裁を突破するために中国が用いた例として橋本首相の事例を紹介したが、中国が欲しいのは、カネ、技術、軍事情報、企業機密……等々、業界や分野を問わす、あらゆるジャンルに及ぶ。しかも日本はどの国よりも情報漏洩に対して、つまり、スパイ行為に寛容な国であり、一般的な国が持つスパイ防止法もない。中国にとって、これほど活動しやすい国はほかにない。
中国の怖さを日本人に突きつけたのは、二〇〇四年五月、中国・上海の日本総領事館に勤務し、外務省と総領事館の暗号通信を担当していた四十代の男性領事の自殺だろう。
「一生、あの中国人たちに国を売って苦しまされることを考えると、こういう形しかありませんでした」
領事は「中国側から外交機密に関連する情報などの提供を強要されていた」という内容の遺書を残して、総領事館内で自殺した。外国公館では、公電通信を担当する領事は、本国とのやりとりの中で、重要案件の決定事項や行方を最も早く知る立場にある。
では、どのように領事が「情報提供を強要されていた」のか、遺書には多くのヒントが残されていた。領事は、上海の虹橋地区にある「かぐや姫」というカラオケ店で知り合った中国人女性と深い関係になっていた。虹橋地区は上海市西部にあり、日本総領事館はもちろん、日系企業の支店や事務所が集中するエリアで、多くの駐在ビジネスマンが知る有名店だ。
ドアを開けると薄暗い静かな廊下を歩いて個室へと案内されるシステムである。二十室以上の個室があり、それぞれが個室でカラオケを楽しむのである。個室に入ると間髪を容れず十人近いミニスカートの女性たちが部屋にやってくる。
「どうぞ、お好みの子を選んでください」
案内の中国人にそう言われて、女性を指名する。指名は何人でもいいが、日本円で一人五千円ほどのチップを払わなければならない。こうしてカラオケを楽しみながら、そのままカップルヘと発展していく場合もあるのである。
上海にはこの手の店は多い。なかには体育館のような広さの店もあり、ひな壇に女性たちがずらりと座っており、気に入った女性を指で差して、個室へと消えるシステムの店もある。
「かぐや姫」のような有名店には、当然、情報機関も目を光らせている。
狙いを定めた客には、女性スパイたちが二重三重で“包囲”してくるのである。領事は、その網に搦めとられたと思われる。機密情報に実際に接触している領事と女性を通じて情報提供を求める中国 ――
まじめな領事は、その悩みを誰にも明かすことなく、この世から去った。
長年、上海の日本企業で働く日本人は、こう語る。
「聞いた瞬間、ああ、やられたと思いました。『かぐや姫』は有名な店で接待でよく使われます。二次会でカラオケに行くと“あっち”が好きな人と嫌いな人はすぐわかりますよ。好きな人を見つければ、女性が男性を誘うように持っていく。まず抜き差しならない写真を撮られるんですよね。男は弱いから、気に入っだ子であれば、“まあ、いいか”ということになるんですよ。
かぐや姫は公安のOBが経営している店なんです。公安がやっているということぱ必ず“裏”がある。みんな“公安がやっているから大丈夫だ”なんて言っていましたが、結局、公安に“丸裸”にされているんです。逆ですよね。うちの社員も、あそこは安心して行ける、などと言っていますが、なにをバカなことを……という感じです。
店では、客の正体がわかってくると、女の子は“この資料をもらえ”とか、上から言われるようになるそうです。かぐや姫に限らす、それ以外の店だって、大使館の人とか、企業のトップの人とかは、必ず狙われる。それで騙されてトラブルになっている日本人は結構多いんですよ。
日本人は、わかってないんです。日本人は性善説に立っていますからね。私は“名刺を出しちゃだめだよ”と口を酸っぱくして言いました。日本人は、飲み屋の女性にすぐ名刺を渡すでしよ。あれがいけないんです。名刺を出せば、会社名から何から全部バレバレなんですよ。たちまち公安に目をつけられるんです。甘すぎます」
・・・中略・・・
ちなみに、「かぐや姫」は、二年後にも情報漏洩事件の渦中に放り込まれている。
今度は、長崎県の上対馬警備所に勤務していた四十代の自衛隊一等海曹が二〇〇六年八月、「無断で海外旅行を繰り返していた」ことを理由に停職十日の懲戒処分を受けたのである。
一等海曹は、「かぐや姫」に入り浸っていた。処分を決めた海上自衛隊によれば、「一年二か月の間に八回にわたり、計七十一日間も、上海に渡航し、親密になった『かぐや姫』の女性に会っていた」というのだ。女性に数百万円の送金をしていたことも発覚している。
産経新聞(二〇〇六年八月三日付朝刊)は、この事件を〈海自内部資料持ち出す 上海に無許可渡航 1等海曹処分〉と題して、こう報じている。
〈海上自衛隊が収集した外国潜水艦などに関する内部資料を、対馬防備隊上対馬警備所(長崎県対馬市)の1等海曹(45)が複製して職場から持ち出し、口頭注意処分を受けていたことが2日、明らかになった。1曹は交際相手の中国人女性に会うため中国・上海に無許可渡航を繰り返しており、情報が中国側に漏洩した可能性もあるとみて、長崎県警が捜査を始めた。
1曹が交際していた女性は、中国当局から情報提供を強要されたとする遺書を残して平成16年5月に自殺した在上海総領事館員も出入りしていたカラオケ店に一時勤めていた。海上幕僚監部によると、1曹は今年2月、職場で周辺国海軍の水上艦艇や潜水艦の写真を収集した「識別参考資料」をCDにコピーしようとし、同僚に注意された。その後、同僚から警備所長あてに「内部資料を無断でコピーしている。無許可で中国に渡航している」との内部告発があり、佐世保地方総監部が調査。その結果、部隊内にある1曹の自宅隊舎から「注意文書」の指定を受けた識別参考資料の複写CD1枚が見つかった。
1曹は昨年1月から今年3月までの間、中国・上海に計8回、無許可で渡航。現地で中国人女性と親しくなり、複数回にわたり総額計350万円を送金していた。このため海自は今年4月、1曹を佐世保総監部管理部付に異動させて調査を続行。6月13日に「無断資料複製」で口頭注意処分、7月4日に「無断海外渡航」で停職10日の処分うを行った(一部略)〉
中国側からすれば、ハニートラップに面白いように引っ掛かる日本人が滑稽でならないだろう。
トランプを抱き込んだ「安倍晋三」 <第十七章 不可避だった“米中激突” の一節>
中国を自由で聞かれた市場にするためにアメリカは二〇〇一年十二月、中国をWTO(世界貿易機関)に加盟させ、真の意味の「経済開放」を促したが、それも失敗した。中国は経済開放ではなく、WTO加盟国であることを利用して世界中の国々との貿易額を増やしていったが、自らの体制を改革することはまったくなかったのである。
中国加盟から十七年後(二〇一八年)、USTR(米通商代表部)は中国のWTO規則の順守状況に関する「年次報告書」の中でこう記している。
「中国では、聞かれた市場志向型の貿易体制の導入が進んでいない。わが国が中国のWTO加盟を支持したことは明らかに誤りだった。市場を歪める中国の行為を抑制するために、WTO規則が十分でないことは明らかだ」
これもまた、アメリカが中国の真の姿を見誤りつづけた結果なのである。
真の専門家は、常に対象の「本質」を見る。第十一章に登場した佐藤慎一郎のように「中国共産党の本質」から目を逸らさないのである。アメリカの中国専門家が「中国はやがて民主的で平和な大国となる。しかし中国は大国となっても、地域支配、ましてや世界支配を日論んだりはしない」などという幻想は、絶対に抱かないのだ。
「中国はなぜ人権弾圧をやめないのか」
よくそう問う人がいる。これには、わかりやすい答えがある。
「それが中国共産党の本質ですから」
そう答えると、怪訝な表情で、
「中国共産党の“本質”が人権弾圧なのですか」
そう再度、問われる。ここで、こう答えるとわかってもらえるだろう。
「中国共産党に弾圧されたり、非業の死を遂げた人たちはどのくらいいるんですか? 数千万人? 数億人? これほどの非道を続けた中国共産党は、他者に政権を譲ることができると思いますか? もし、譲ったら、たちまち殺されます。これまでに酷いことをやってきた分だけ、民衆の反発はすごい。だから言論も、人権も封じて、強権で支配をつづけるしかないのです。権力を失うことは、彼らにとって物理的な死、つまり惨殺をもたらすのです。
彼らはルーマニアのチャウシェスクや、リビアのカダフィ、イラクのフセインたちの末路を知っています。だから、絶対に権力を手放すことができない。弾圧をつづけ、権力を永遠に維持しつづけなければならない理由がそこにあります」
アメリカの中国専門家は、この本質を理解できなかった。そのために“騙されつづけた四十年”があったのである。そして、オバマのあとを受けた大統領、ドナルド・トランプの登場によって、米中の激突は凄まじいものになっていくのである。
トランプを先に押さえるのは日本か中国か ―― ニ○一六年十一月、予想を覆してトランプが大統領選でヒラリー・クリントンを破った際、国際関係の専門家は、まずこのことを考えた。
政治家の経験がないトランプは、外交関係も、もちろん素人である。果たして日本や中国にどんな考え方をする人物なのか、この時点ではほとんど明らかになっていなかった。
しかし、まだ世界の指導者が誰ひとり連絡もとっていない中、日本の安倍晋三首相が面会の約束をとりつけ、ニューヨークのトランプタワーにある自宅で、会談にこぎつけるのである。
安倍は、話のほとんどを「中国」に費やした。就任前のトランプの心を掴んだ安倍は、その後、二人の個人的関係を軸に、歴史上、最も良好な日米関係を構築していく。
「シンゾーが言うなら、それでいい」
のちにそんな言葉を国際会議の席上で連発するほどトランプは安倍を頼った。
安倍の指南を受けて、トランプは、中国の実情を深く理解することになる。「中国は不公正な商取引と知的財産権の侵害をしている」という意見を表明したこともあるトランプにとって、まさに「安倍晋三」、そして「日本」の存在は、このうえない援軍、いや同じ価値観を共有する仲間に思えたことだろう。ホワイトハウスのスタッフがトランプを説得できない案件が生じた時、安倍に説得を頼んだというエピソードはあまりにも有名だ。
やがてトランプ政権は、高速大容量の第五世代(5G)移動通信システム時代を見据えて、中国の華為技術(ファーウェイ)などの中国製品を「安全保障上の脅威がある」との理由から締め出しを図るのである。
二〇一八年十二月一日、香港からメキシコに向かっていた華為技術の副会長兼CFOの孟晩舟は、乗り換えのカナダのバンクーバー空港でカナダ当局によって逮捕された。
アメリカからの要請だった。すでに四か月前に米ニューヨークの連邦地裁から「孟晩舟は国際機関を欺く陰謀をおこなった」として逮捕状が出されており、カナダはその拘束要請に応じたのである。この逮捕劇をきっかけに米中は、さらなる貿易戦争に突入。お互いに数千億ドル規模の関税をかけ合う対立へとエスカレートしていく。
そして、世界は二〇一九年十二月に武漢で始まった「新型コロナウイルス」という中国生まれの“怪物”との戦いを余儀なくされるのである。
「中国に感謝せよ」でキレた米国 <第十七章 不可避だった“米中激突” の一節>
「道理を正して、世界は中国に感謝すべきなのだ」
二〇二〇年三月四日、世界にコロナ禍が波及する中、中国国営の「新華社通信」が世界に配信した記事に国際社会は絶句し、唖然となった。
湖北省・武漢で発生した新型コロナウイルスの発生源である中国が、よりによって世界に対して「我々に感謝すべきだ」と言い放ったのである。
すでに世界に広かった武漢肺炎は、ヨーロッパを呑み込み、イタリアやスペインを皮切りに甚大な被害を生み始めていた。そんな中で新華社はこう主張したのだ。
〈中国が早く世界に謝罪すべきではないのか、という話がある。なんとばかげたことか。中国は、この新型肺炎に対して、巨大な犠牲を支払い、さらには、莫大な経済的コストを費やして、新型肺炎の“感染ルート”を断ち切ったのである。この肺炎の流行でどの国も中国ほどの犠牲を支払ってはいないのである〉
大きな疫病が発生した国は、普通は、ます犠牲になった人々と遺族にお悔やみを伝え、謝罪の言葉を添えるものである。
しかし、中国は違った。彼らは、ひと言のお悔やみや謝罪もないまま、逆に「中国に感謝せよ」と言い放ったのである。それだけではない。
新華社の記事は、ウイルスの発生起源が「中国ではない可能性がある」と伝えていた。
〈多くの研究成果が、中国ではないほかの国が起源であったと差し示している。現に、アメリカ、イタリア、イランなどの国々では、アジアとの接触がない感染例が見つかっている。中国には、そもそも「謝罪する理由」などないのである。
今、私たちは道理を正して訴えていこう。米国は中国に謝罪すべきなのだ。世界は、中国に感謝すべきなのだ。中国の多大な犠牲と努力がなかったならば、世界中が、この新型肺炎と戦うための時間的猶予が得られることは決してなかっただろう。
中国の力によって、この新型肺炎は長い時間、拡散をストップすることが可能となったのである。これは、まさに世界を驚かせ、鬼神をも泣かせる中国の偉業というべきなのである〉
国際社会はこの時まで、多くの死者が出ている中国に対して謝罪要求を控えていた。生きるか死ぬか、の患者を抱える国に、アクションを起こすことは止めていたのである。
だが、当の中国が、自分たちに「感謝せよ」と言い始めたのだ。しかも、発生起源は中国ではなく、自分たちは被害者だという主張なのである。
世界は驚愕した。特にアメリカの怒りは、凄まじかった。
被害が拡大するにつれて、事態が深刻化していったのはアメリカだったのである。当初、アメリカは素早く中国からの入国者をストップし、水際作戦に成功していた。だがアメリカは、中国からの直接流入ではなく、ヨーロッパ経由でのウイルス侵入を許してしまう。
中国という正面の感染国からの流人を止めたのに、欧州という“うしろから”のウイルスの侵入を許したのはアメリカにとって痛恨事だった。
武漢病毒研究所の研究室からのウイルス漏洩という問題に入り込ませたくない中国は、「外交は力がすべて」「攻撃こそ最大の防御」の鉄則どおり、加害者ではなく被害者を装い、他国に罪をなすりつける手段をとったことになる。
西側が反発を強める中、トランプ政権の怒りは国際社会の思いをそのまま表わすものとなった。
「中国は世界中の何十万人が亡くなるのを防ぐことができたはずなのにそうはしなかった。彼らは感染の発生を隠したのだ」
五月六日、ポンペオ国務長官は極めて直接的な表現で中国を糾弾した。極めつけは、五月二十日、トランプ大統領が自身のツイッターを通じて放った言葉だろう。
「パンデミックは世界規模の大量殺人だ。これをもたらしたのは“中国の無能さ”にほかならない」
大量殺人と中国の無能さ ―― これ以上はないほどの強烈な言葉だった。トランプのツイッターを見た中には、「これは中国への宣戦布告なのか」と首をすくめた人間もいたほどだ。
アメリカのコロナの犠牲者は信じがたいスピードで増えていった。
「第二次世界大戦のアメリカの戦死者数を上まわったらトランプはもたない」
「大統領選の行方は、どこでコロナ死者の数が落ちつくかにかかっている」
再選を日指す共和党・トランプの前に立ちはだかったのは、民主党候補者のハイテンではなく、コロナだったのである。
やがてベトナム戦争の戦死者数を超え、第二次世界大戦での戦死者数も超えたアメリカは、パンデミックの制御がつかなくなった。
そしてトランプはホワイトハウスから去った。習近平は最大の敵・トランプをコロナによって倒すことに成功したのである。
「無知と無関心が一番危険」 <第十七章 不可避だった“米中激突” の一節>
元在沖縄米軍海兵隊政務外交部次長で政治顧問も務めた政治学者、ロバート・エルドリッヂはこう語った。
「中国が豊かになれば世界の価値観の共有ができると思っていたアメリカには、たとえ思想的に合わない国でも、つき合えばつき合うほどよくなっていくという期待があった。しかし、それは希望に過ぎませんでした。一番転換期になったのは冷戦が終わった時。天安門事件があって、例えば東ヨーロッパは民主化したけれども、中国はますます独裁化した。
中国は一九六九年以降、旧ソ連を敵国として見ていました。冷戦が終わって、共通の敵であった旧ソ連がなくなったので、アメリカと中国はお互いに警戒するようになったと思います。しかし、アメリカは依然として中国に期待していました。それは世界がみんな仲良くなるとの期待でしたが、これが無理であることがわかり、そこからどんどん離れていったのです」
中国がどうなっても“変わらなかった”ことをエルドリッヂはくり返し強調する。
「中国と最初に仲良くしたのは共和党です。これは超党派の政策だったんですが、少しずつ脱落していく。そして脱落組が多くなって、次第にそっちの意見が強くなっていきました。WTOの加盟でも結局、中国は国際的な約束を守らなかった。企業がどんどんやられて、信頼できなくなって、さらに、この二十年間は中国の軍拡がものすごく進んだんです。だから防衛問題を見ている人たちが“これはもう明らかに脅威である”となっていきました。
軍事的にも以前の中国には質的問題があったんですが、WTOも利用され、それ以外にも、政治家を買収したり、軍事機密や産業機密を盗んでいく手法をとった中国は、どんどん強くなりました。二〇一五年の段階で、ついに中国は台湾を攻略できる力を身につけました。
二十年前とか三十年前は、中国には台湾侵略の意図はありましたが、能力が伴っていませんでした。しかし、二〇一五年、オバマ政権の時には、その力が身についたんです。意思があって能力が備われば、これはもう脅威です。ちょうどその頃に、ピルズベリーとナヴァロの書籍が相次いで出ました。この書籍は非常に大きかったと思います。それから、習近平が“何をしたいのか”を言葉でも出すようになったので、アメリカの危機感は増大していったのです」
しかし、日本と同じようにアメリカにも蔓延する“平和ボケ”が中国の増長を許した、とエルドリッヂは指摘する。
「この時はまだ、民主党が平和ボケから抜けられていなかったと思いますね。中国が、民主党系の公務員、要するに任命されている官僚、そして政治家を買収していたんです。私は中国の賄賂には三種類あると思います。一つは政権につく前にあげるお金。要するに“投資する”もの。二つめは政権中に具体的な取引をするもの。これは一番わかりやすいですね。最も違法なものです。政権前の場合は、これがわかりにくいですよね。しかし、政権中はわかりやすい。最後の三つめは、政権後に何か“美味しいもの”が待っている、というものです。
たとえば株を先にあげておき、株が上昇した場合はボロ儲けするというもの。あるいは、将来いい仕事が待っているというものもあります。中国はこういう手法を使いますよね。アメリカは二つの政党しかないので、必ず政権交代があります。政権から降りた人はその間、仕事が必要です。その世話をするのです。何かつき合いをすれば、恩が生じますよね。次、必ずその政党に政権は戻るので、その人は前の仕事より、もう一つ上の階級で次の政権に入ります。中国はそういう人物に恩を売るのがうまいんです。
実際に安全保障に携わっていた有力者にアジア貿易をする会社をつくらせ、中国共産党の許可のもとに儲けを上げさせている例があります。中国は“いまこれをしてあげるから、君がまたアメリカの政権に戻る時は、これをやってくれ”というわけです。オバマ政権の時の有力者の一人がこれを受け、いま実際にバイデン政権に高位で戻っている例もありますよ。カート・キャンベルというインド太平洋調整宮です。中国は、こういう細かなやり方が本当にうまいんです」
エルドリッヂ自身が中国の危険性に気づいたのは、いつ頃だろうか。
「私か最初に気づいたのは、やはり沖縄に勤め始めた二〇〇九年九月以降ですね。この頃、中国はますます軍拡し、膨張主義を強めていました。日本に対して威嚇をおこない脅威となっていました。二〇一〇年の尖閣での中国漁船衝突事件が象徴的です。
私は、二〇〇〇年代半ばまでは、まだある程度は中国と協力できるだろうと考えていました。そういう論文を書いたこともあるほどです。しかし、その論文も今では“甘かった”と言わざるを得ません。中国漁船衝突事件でもわかったように、中国との協力の可能性があったとしても、向うには、その意思がないんです。中国はもう日本と協力したいわけではない。そのことを知らなければならないと思いました」
エルドリッヂは日本政府に是非、お願いしたいことがあるという。
「それは、日本に入る中国男性たちを全て調べて欲しいということです。荷物を開けて、チェツクすることをやって欲しい。肉や珍しいものを持ち込んだおばあちゃんたちじゃなくて、男たちを調べてほしいのです。彼らはお金を沢山、運んでいます。例えば、日本国内で中国の総領事館に相当のお金を渡している。これが沖縄にばら撒かれている。
政界でも、自民党の有力者のところに中国大使館がスーツケースを持っていく。宿舎の方にそのまま持って行ったという話も聞きました。私は、日本の状況を見て、強い不安を感じているんです。理由は何か。それは、国家に対する尊敬とか、国家を守る覚悟、意識とか、見識とかノウハウとかもない。だから愕然とします」
国民も同じです、とエルドリッヂは指摘する。
「日本は多くの国民が政治に無関心ですよね。無知と無関心。これが一番危険だと思っています。尖閣が中国に盗られ、軍事化されれば、沖縄、フィリピン、台湾がアウトです。それほど重要な位置に尖閣はあります。いってみれば、インド・太平洋地域は日本の尖閣にかかっているんです。しかし、国民には、その危機感も、関心も、ありませんよね。日本が尖閣になんらかの行政的措置をとれば、国際社会は“尖閣は日本”と扱い、中国から守ります。しかし、日本人が関心もなく、また守る意思もなければ、もうそれで終わりです。外の敵の行動を黙認するのは最も危険なことですよ。アメリカの危機と日本の危機は両方深刻なんです。
日本経済の中国への依存は極めて深刻ですね。加えて政治の世界は問題です。永田町の少なくとも半分ぐらいは中国寄りですね。日本にいる中国人は、だいたい八十万から九十万人ぐらいになっており、要するに百万人時代です。これは実際に戦える自衛隊員の四倍ですよ。中国は国防動員法を施行していますから、彼ら在日の中国人には動員に応じる義務があります。だから、中国と戦争が始まる前に、日本は“無力化”される可能性が十分あるんです。沖縄も一挙に無力化されます。そういう危機感が日本にはない。そこが私は恐ろしいんです」
日本がいかなる状況にあるのか。浮き彫りになる話である。
エルドリッヂ米太平洋軍司令部元政治顧問の警鐘を「無」に終わらせるのか否か。すべては、日本国民次第である。
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1583936b.847a7192.1583936c.2d77a722/?me_id=1213310&item_id=20754493&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F4172%2F9784819114172_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
