「戦争と平和」の世界史
「世界史で学べ! 地政学」に続いて2冊目の茂木誠さんの著書を手にしました。「世界史で学べ! 地政学」もそうでしたが、本書でも同様、茂木さんは「現実主義(リアリズム)」に立った見方考え方をする方だと思います。
それだけに説得力のある考察がなされているので、私も含めて戦争を知らない読者も本書を読みながら「戦争と平和」について、己のこととして考えることが出来るのだと思います。
「はじめに」で『第二次世界大戦後の歴史教育は、戦争を悲惨なもの、あってはならないものとしてタブー視し、戦争について語ることさえはばかられるという風潮を作ってきました。サッカーの公式試合にぼろ負けしたチームが、敗因の分析をまったく行わず、「二度とサッカーはしない。ボールを持たない」と誓いを立てたのです。しかし現実の世界では苛烈な「試合」が今も続いており、日本が望むと望まざるとにかかわらず、巻き込まれる危険性が高まってきました。』と理想主義・お花畑的思考に警鐘を鳴らしています。
とても面白く勉強になった、茂木誠さんの『「戦争と平和」の世界史』を紹介するために、以下に目次や目を留めた項目をコピペさせていただきます。
興味が湧いて、他も読んでみたいと思ったら、本書を手にしていただければと思います。
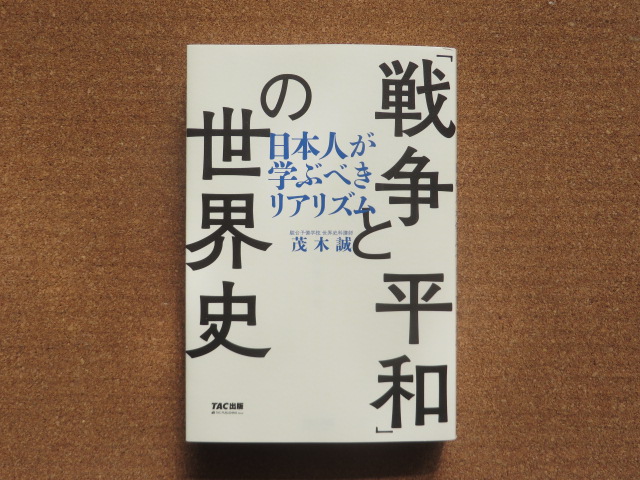
目次
はじめに 1
第1章 人類はいつから戦ってきたのか?
人類とチンパンジーは仲間同士で殺し合う 14 / 石器時代の戦争 16
第2章 古代国家と戦争
儒家は理想主義で戦争を捉えた 22 / 墨家の徹底したリアリズム 25 / 古代ギリシアの戦争観 29 / 「記紀」から抹消された不都合な真実 34 / 古の日本列島統一戦争の謎 36 / 白村江の戦いと壬申の乱で「日本国」が誕生した! 41
第3章 中世の戦争と兵農分離
中世とはいつを指すのか? 48 / 中世における戦争のルール 50 / 常備軍の廃止と民兵組織「武士団」 53 / 将門の乱と純友の乱の衝撃 55 / 刀伊の入寇にみる「平安時代」の現実 57 / モンゴル帝国のユーラシア統一戦争 59 / フビライの日本遠征と南宋遠征 62 / 日本がモンゴルに蹂躙されなかった理由 66
第4章 大義に支配された宗教戦争の時代
マサダの戦いにみる宗教戦争の苛烈さ 70 / 「武装巡礼団」だった十字軍 72 / 異端者に対する十字軍 75 / スペインの「正義」―― 対異教徒戦争 79
第5章 ウェストファリア体制と「徳川の平和(パクス・トクガワーナ)」
戦争がビジネスになった三十年戦争 84 / 「主権国家」間の絶え間ない戦争が「戦時国際法」を生んだ 86 / 日木版宗教戦争のルーツは鎌倉仏教にあった!? 89 / 比叡山と一向一揆を灰燼に帰した織田信長 93 / 秀吉の朝鮮出兵のヒントを与えたイエズス会 97 / わが国最後の宗教戦争となった島原の乱 101 / なぜ江戸時代は250年も平和が維持されたのか? 103
第6章 国民国家の成立と「戦争の民主化」
古代ギリシア人にとっての「国家意識」 108 / 武士の官僚化、傭兵の主流化 ―― 日欧戦士の比較 111 / フランス革命が引き起こした「戦争の民主化」 113 / 世界を塗り替えたナショナリズム 115
第7章 『万国公法』と植民地支配
国際法の構築に影響を与えた思想家たち 124 / アヘン戦争における「文明の衝突」 127 / アジア・アフリカは国際法の枠外だった 133 / 東アジア再編を促した伝説の名著とは? 135 / 勝海舟も坂本龍馬も『万国公法』を読んでいた 139 / 日本初の海難審判「いろは丸事件」 144 / ヨーロッパの思惑で進められたアジアの内戦 146 / 江戸城無血開城を国際法の視点から再評価する 151 / 榎本武揚が箱館戦争を生き延びた幸運 159
第8章 ビスマルク体制と明治日本の国際デビュー
ビスマルク直伝! 日本が実践した「小国の生き残り戦略」 166 / 樺太と千島列島に見る日露国境紛争の歴史 172 / 本邦初の国際裁判、マリア・ルス号事件 176 / 日清領土の画定 ―― 琉球と台湾の帰属問題 179 / 明治時代、朝鮮半島の地政学的リスク 182 / 陸奥宗光という傑物と領事裁判権の壁 183 / 大津事件が不平等条約改正につながった 187
第9章 明治日本の戦争
なぜ日清戦争は起こったのか? 192 / 「高陞(こうしょう)号」事件 ―― 中立国の船を撃沈するのは合法か? 193 / 朝鮮半島、遼東半島をめぐる日露の攻防 198 / 義和団事件が日本の国際的地位を向上させた 201 / 「第0次世界大戦」と日英同盟 205 / 日露戦争の日本海海戦における勝利の条件 210 / ギリギリの交渉だったポーツマス条約と小村寿太郎 216 / 韓国併合の国際的な合法性とは? 220 / 大正デモクラシーは平和をもたらしたのか 222
第10章 第一次世界大戦と国際連盟体制
第一次世界大戦の功罪 226 / モロッコ事件とバルカン危機 227 / 仁義なき秘密外交が第一次世界大戦の雌雄を決した 229 / 日本が「欧州大戦」に参戦したのはなぜか? 233 / 金融資本の都合とロシア革命 236 / 対等な日米交渉「石井・ランシング協定」の意義 237 / 共産主義の脅威が一変させた国際情勢 240 / 世界初の集団安全保障体制「国際連盟」 242 / ワシントン会議に隠されたアメリカの本音 249 / ケロッグ・ブリアン協定の偽善 255
第11章 昭和の軍部はなぜ暴走したのか?――
満洲事変~日中全面戦争
「あの戦争」を何と呼ぶべきか? 260 / 政党の失政と元老不在が軍部の跋扈を招いた 262 / 張作霖爆殺事件の謎と陸士エリートの台頭 268 / 陸軍の教育システムはこうなっていた! 271 / 参謀本部における学歴主義と情報の軽視 275 / 「昭和維新」のカリスマ、北一輝と井上日召 277 / 世論の暴走 ―― 満洲事変とリットン報告書 281 / 国際連盟の崩壊と日中全面戦争への序曲 286 / 陸軍の「統制派」の台頭が日本の運命を決した 291 / 石原莞爾も反対した日中全面戦争 297 / 近衛首相を戦争に引きずり込んだ者たち 305
第12章 日米戦争 破局への道
「天才的戦略家」石原莞爾をつぶした「凡人官僚」東條英機 312 / アメリカ政府が対日戦争を望んでいた理由 320 / ノモンハン事件が独ソ不可侵条約を生んだ 324 / 死闘のカギを握ったのは「国際金融資本」 330 / 松岡洋右の「四国軍事同盟」構想とその挫折 334 / 野村吉三郎と幻となった「日米諒解案」 343 / 対日経済制裁という「劇薬」 349 / 「ハル・ノート」を書いた黒幕 358 / 山本五十六の短期決戦論に海軍が押し切られる 366 / 真珠湾攻撃の最後通告が攻撃開始後になったわけ 370 / 早期終戦工作はことごとくつぶされた 377 / 北欧における日本陸軍のスパイマスター、小野寺信 384 / ヤルタ密約のソ連参戦情報を日本は知っていた? 387 / 実らなかったスイスにおける対米和平工作 392 / 「本土決戦」の思想とは何だったのか? 394 / 彼らはソ連軍による「解放」を望んでいた 402
第13章 アメリカ幕府のもとで
「国連による平和」という虚構 410 / パクス・アメリカーナの本質 415 / 東京裁判とは何だったのか? 418 / 吉田親米政権と日米安保体制 421 / 日本における「戦争と平和」の未来 427
あとがき 435
はじめに
日本国憲法改正の機運が高まっています。
改憲推進派は、「今の憲法では日本を守れない。今やらなかったら、永久に改憲できない!」と気合が入ります。一方で、改正に反対する護憲派は、「憲法改正で戦争に巻き込まれる。平和憲法を守れ!」と悲壮感を漂わせています。
憲法改正の焦点は、日本国の「戦争放棄と戦力の不保持」を定めた第9条です。つまりこの改憲問題は、日本人が「戦争」とどう向き合ってきたのか? という根本的な世界観に関わるものだから、国論が二分されているのです。
世界196力国のほとんどが、第二次世界大戦ののちに植民地からの独立を達成した新興国です。国家として一人立ちしてからの歴史が浅く、過去の経験から学べることは少ないのです。
しかし日本国は、千数百年の長きにわたって独立を維持し、江戸時代には250年余にわたる平和を維持してきた類まれな国家です。それがなぜ可能だったのか、を考えること自体が戦争観につながるでしょうし、その長い歴史の中で実際に日本国が関わった戦争を客観的に理解しておくことは、改憲論議を深めるためにもきわめて重要だと考えます。
第二次世界大戦後の歴史教育は、戦争を悲惨なもの、あってはならないものとしてタブー視し、戦争について語ることさえはばかられるという風潮を作ってきました。サッカーの公式試合にぼろ負けしたチームが、敗因の分析をまったく行わず、「二度とサッカーはしない。ボールを持たない」と誓いを立てたのです。
あの軍民合わせて300万人もの日本人を死に至らしめた満洲事変から第二次世界大戦に至る戦争についても「そもそも間違っていた」と断罪するだけで、「なぜ負けたのか? 今後二度と負けないためにはどうすればよいのか?」という議論は封殺されてきたのです。
しかし現実の世界では苛烈な「試合」が今も続いており、日本が望むと望まざるとにかかわらず、巻き込まれる危険性が高まってきました。北朝鮮の核兵器搭載可能な弾道ミサイルが日本列島の上空を通過し、中国海上警察の公船が日本の領海侵犯を繰り返しているのです。武力紛争に巻き込まれないためにはどうすればいいのか、もし巻き込まれた場合はどうするのか、を真剣に議論しないのは、あまりにも無責任だと思います。
本書では、世界の戦争の歴史を振り返り、人類がいかにして戦争を抑止するシステムを構築してきたかを考えます。
次に日本の戦争の歴史を振り返り、「サムライの国」がなぜ二世紀におよぶ「徳川の平和」を生み出したのか、「国際法を学んだ」明治日本が、どうして昭和には「軍国主義の国」となり、さらに敗戦後の「平和憲法の国」に転換したのかを考えます。
最後に、近未来の東アジアで起こりうる危機を予測し、日本がこれに巻き込まれないためにはどうしたらいいのかを、「改憲」「護憲」の立場の違いを超えて、冷静に考えていきましょう。
人類とチンパンジーは仲間同士で殺し合う P14
戦争と殺人・傷害はどう違うのでしょう?
暴力で他者を殺傷し、屈服させることでは同じです。
個人または集団が他者を殺傷し、社会的に罪とされるのが殺人・傷害であるのに対し、戦争は個人ではできません。また社会的に罪とされないどころか、英雄的行為として賞賛されることが多いのが戦争です。合法化された暴力行為ということもできます。ここでは仮に、こう定義しておきましょう。
「ある社会集団が、別の社会集団と武力で闘争すること」
「国家」ではなく「社会集団」というあいまいな表現をしたのは、「国家」が成立するはるか以前から戦争はあったからです。また、一つの国家の内部で社会集団同士が抗争する「内戦」も、戦争に含まれるからです。
人類(ホモ・サピエンス)のDNAの98%はチンパンジーと同じです。人類の行動の多くは類人猿でも確認されています。それでは、類人猿もまた、人類と同様に集団で殺し合うのでしょうか?
類人猿(ゴリラ・チンパンジー・ボノボ・オランウータン)のうち、単独行動をとるオランウータンは除外されます。ゴリラやチンパンジー、ボノボは群れを作りますので、彼らの生態を調べてみれば何かわかりそうです。
動物園にいるチンパンジーはバナナを食べる穏やかな生き物というイメージですが、野生のチンパンジーはかなり凶暴です。普段は果実を食べていますが、ときには集団で小形のオナガザル(アカコロブス)を襲撃し、食べてしまうのです。
いやいや、他の生物を捕食するのは肉食獣で、チンパンジー同士は殺し合わないはずだ、と思われるかもしれません。
しかし、タンザニアやウガンダでの観察によれば、チンパンジーは集団で殺し合いをします。原因はえさ場の奪い合いだったり、メスの争奪だったりします。血縁関係にあるオスたちが徒党を組んで、他の集団を襲うのです。人間のように武器こそ使いませんが、ツメでひっかき、歯で噛みつき、相手の体を引き裂いて殺します(山極寿一『暴力はどこからきたか』NHKブックス)。
見かけによらずおとなしいゴリラやボノボ(ピグミーチンパンジー)には、このような行動は確認されていません。同種間で殺し合いをするのはチンパンジーと人間だけです。
余談ですが、チンパンジーは子殺しもします。一頭のオス(ボス)が複数のメスを引き連れて群れを作るのですが、若いオスが台頭して、ボスの座を奪い取ることがあるのです。クーデタが成功すると、新たにボスになったオスは授乳中の前のボスの子供を噛み殺します。もちろん母親は抵抗しますがなすすべもありません。さらに驚くべきことには、子供を殺されたメスは発情し、我が子を殺した若いオスと交尾するのです。このような行動はライオンでも見られます。
力のある個体が優れた遺伝子を残すというダーウィンの進化論、適者生存の原理に従えば、合理的な行動であるともいえます。人間社会で犯罪や病理とされるいくつかの行動は、実は進化の過程にさかのぼる原初的な衝動に基づいている可能性があるのです。
儒家は理想主義で戦争を捉えた P22
古代中国の思想家といえば、儒学を開いた孔子が有名です。
殷王朝を滅ぼした周の武王は一族を各地に派遣して諸侯とし、血縁関係でゆるやかに治める封建制を実施しました。信頼する弟の周公旦(しゅうこうたん)を山東半島に遣わして魯(ろ)という国を建てさせます。これらの諸侯は完全な自治権を認められ、時の経過とともに周王朝の統制を離れて自立していきます。そして、異民族の侵入を機に無政府状態におちいり、さらには諸侯同士が争うようになるのです(春秋戦国時代)。
孔子に代表される中国古代の思想家たちが戦争について何を語っているか、見てみましょう。
魯は周公旦に始まる由緒ある諸侯として一目置かれていましたが、戦乱の時代になると隣国の斉(せい)に侵略され、国内では家臣がクーデタを起こして政権を奪います。
魯の下級貴族に生まれた孔子は、王と諸侯が血縁関係で結ばれていた周王朝を理想国家と仰ぎ、家族関係をモデルとした他者へのいたわりの情(仁)、道徳的に正しく生きるモラル意識(義)を再建すれば、失われた国家秩序は再構築できる、と説きました。要は、みんなが清く正しく生きれば、戦争は回避できるという理想主義を説いたわけです。
衛の霊公が兵法を問うた。孔子は答えていった。「祭祀のことは学びましたが、兵法のことはまだこれを学んでおりません」と。翌日、孔子は衛を去った。(『論語』第十五衛霊公篇/著者が口語訳)
孔子の理想主義を「性善説」として理論化したのが孟子です。孟子は軍事力による政治(覇道)を戒め、仁義による政治(王道)を説きました。魏(梁)の恵王(けいおう)と孟子の問答は「五十歩百歩」の故事で有名ですが、こういう話もあります。
恵王がいった。「わが国は東方では斉に敗れて長男が戦死し、西では秦に七百里の領土を奪われ、南では楚に敗れた。私はこれを恥じ、死者のため雪辱を果たしたい。どうすればよいか?」
孟子は答えた。「四百里四方の小国となっても、王であることは変わりません。王が仁政を施し、刑罰を軽くし、農業に専念させ、人民に徳を積ませたとすれば、杖を持つだけで敵の甲冑を撃ち、武器を待った敵の兵士を打ち倒せます。敵国が人民を酷使すれば、その人民は飢えて離散します。そのとき王が出征すれば、いったい誰が王の敵となりましよう。だから仁者は敵なし、といわれるのです。」(『孟子』巻第一 梁恵王章句上/著者が口語訳)
国防の具体的なアドバイスを求めた恵王に対し、「仁政を敷けば自然に国力は強化され、敵は退散します」とだけ孟子は説いたのです。これが儒家の理想主義です。
道徳的に正しい戦争(義戦)はあるのか、と問われた孟子は答えます。
春秋に義戦なし。「あの戦いは、この戦いよりはましだった」、といえるのみである。(『孟子』巻第十四尽心章句下/著者が口語訳)
春秋とは、魯の歴史書『春秋』に記録された時代(春秋時代、前770~前403)を指しますが、「年月」「歴史」という意味もあります。歴史上、真の「義戦」といえるものなどない、と孟子は考えたのです。
同じ儒家ですが孟子を批判して性悪説を説いた荀子は、道徳的に正しい戦争(義戦)というものがある、といいます。
殷の紂王は、暴君として有名でした。「酒池肉林」の贅沢に溺れたとされる人物です。
この紂王の圧政に耐えかねた臣下の一人、周の武王が挙兵し、牧野(ぼくや)の戦いに勝利して殷を滅ぼしたのです。しかし武王の挙兵は、「主君である紂王に対する反逆では?」と弟子に問われた荀子は、こう答えます。
人義の士が行う戦争は、利益が目的ではない。非道を抑えて人民の苦しみを取り除くことが目的なのだ。……武王は紂王を討伐した。この戦いは仁義に基づいていた。だから近隣の人民が善政を喜び、遠方の人民も武王の徳を慕った。干戈(かんか)を交えなくとも、各国が服属してきたのだ。こうして世界が徳に包まれたのだ。 (『荀子』巻第十議兵篇第十五/著者が口語訳)
仁義(愛や正義)に基づく戦争は「義戦」であるから正しい、という論法です。けれども、ある戦争が仁義に基づくかどうかを、誰が判定するのでしょう?
中世における戦争のルール P50
ゲルマン法では、私人の身体・財産・名誉が侵害された場合、被害者が属する氏族は、実力をもって加害者に報復すること(血の報復)が義務とされました。報復された側は、今度は被害者となって再び報復します。こうして私闘が繰り返され、慢性的に戦争状態が続いたのです。
彼らは国家から一定の俸給をもらう官僚ではなく、自分の領地を経営する領主として、農民を使役して自活していたのです。私領を脅かす敵が現れれば剣を抜いて戦い、農民を保護しました。農民は、領主の保護を受ける見返りに、領主に年貢を納め、労役に服したのです。
プロの戦士階級がいるかいないかという問題は重要です。それによって戦争のルールが左右されるからです。
中国の場合は、職業的な兵士(傭兵)と徴兵された兵士(農民兵)がいましたが、都市全体が城壁に囲まれていたため、都市の住民は戦闘に参加せざるを得ず、落城したときには住民も無差別に殺されました(これを「屠城」といいます)。戦闘員と非戦闘員の区別がないのです。古代ギリシアの戦争も中国型で、メロス島の成年男子が「屠城」されたのは、彼らが戦闘員だったからです。
西欧諸国や日本では、戦闘は幼少期から訓練を積んだ騎士階級・武士階級がやるもので民衆の多くは避難し、ときには高みの見物を決めこんでいました。戦闘に勝利した領主は、敗者の領地を奪いますが、そこに住む人民まで殺戮してしまっては領地経営ができなくなります。中世は「暗黒時代」といわれましたが、それなりのルールはあったわけです。インドでも、ヒンドゥー教徒のそれぞれの身分の義務を記した『マヌ法典』に次のような規定があります。
87 王はその人民を保護し、……(敵より)挑戦せられたる時は、クシャトリヤ(戦士)の義務を想起し、戦闘を回避する勿れ。
91 (敗走中)高處に攀登する者、去勢者、合掌(し懇願)する者、毛髪をふり乱(し遁走)せる者、坐す者、「吾は汝のものなり」と言ふ者は(これを攻撃する勿れ。)
(『マヌの法典』第七章岩波文庫P189)
中世社会が無差別の殺戮を抑制できた理由として、領主階級の経済的得失のほかに思想的要因があります。
戦乱が続いた西欧諸国では、人々はキリスト教に救いを求めました。まもなくやってくるという「最後の審判」ですべての苦しみは終わり、イエス・キリストの救いを得られると説く教えは、この時代にヨーロッパ人に深く浸透し、伝統的な多神教を駆逐していきました。
キリストの一番弟子であるペテロが、皇帝ネロによる迫害で殉教した地であるローマのヴァチカンの丘は、イエス殉教の地であるエルサレムに次ぐ聖地とされました。ローマ・カトリック教会の成立です。
その指導者であるローマ教皇は、「地上における神の代理人」と位置付けられ、西欧各国の王たちの上に君臨しました。王や貴族がカトリック教会に反逆する場合には、教皇は「破門」という最終手段を取ることができました。
「破門」とは、キリスト教徒コミュニティーからの排除、徹底的な「村八分」を意味します。いっさいの人間関係を絶たれ、生活の糧を失い、死んでも墓に入れません。夫婦親子とは絶縁され、主従関係も絶たれます。
聖職者の任免権(叙任権)をめぐってカトリック教会と対立した神聖ローマ皇帝(ドイツ王)ハインリヒ四世が教皇グレゴリウス七世に破門された結果、ドイツ諸侯たちは皇帝ハインリヒを見捨て、別の皇帝を立てようとしました。ハインリヒは、教皇が滞在するカノッサ城を単身訪れ、城門の前に三日間、立ちつくして許しを請い、ようやく破門を解かれます(カノッサの屈辱、1077)。
このような絶大な権威を持つに至ったカトリック教会は、領主階級の私闘を抑制し、教会や聖職者、巡礼者、女性や子供など非戦闘員を殺傷することを禁止する布告(神の平和令)をたびたび出しています。これは10世紀に南フランスで始まり、ドイツ諸国に拡大しました。違反者は破門により罰せられたので、一定の効果がありました。
マサダの戦いにみる宗教戦争の苛烈さ P70
「戦う人」である騎士階級が一定のルール(騎士道)に基づいて勝敗を決し、一般民衆の無差別殺戮を回避する、というのが中世の戦争でした。戦争ですからもちろん死傷者は出ますが、指揮官クラスの貴人は生け捕りにし、身代金を支払わせて釈放する、というのも一般的なルー
ルでした。
しかし例外があります。「神の敵」である異教徒や異端者と戦い、神のために死に、天上での永遠の命を得られるという「聖戦」の場合です。
宗教戦争の苛烈さは、古代のユダヤ王国で記録されています。唯一の神であるヤハウェを信仰し、神の裁きである「最後の審判」ではユダヤ人だけが救われ、天国に導かれると固く信じたユダヤ人は、いかなる異民族の支配も受け付けず、抵抗を続けてきました。
ローマ帝国に併合されたユダヤ王国では、皇帝ネロの時代(一世紀)に大規模な独立運動が起こりました。首都エルサレムがローマ軍の攻撃で陥落したあと、異教徒ローマ人に屈することを拒否した約1000人のユダヤ兵が、妻子を連れてエルサレム郊外のマサダ要塞に立てこもりました。マサダは周囲を絶壁に囲まれた丘であり、難攻不落でした。
ローマ軍は2年がかりでマサダの丘を囲む谷間に大量の土を運んで通路を作り、総攻撃を開始しました。ところが抵抗はまったくありません。要塞の中に踏み込んだローマ兵が見たものは、集団自決したユダヤ人のおびただしい遺体でした。
ユダヤの男たちはまず妻子を殺し、次に円陣を組んでくじを引き、くじに当たった者から仲間の手で殺していきました。そうして、最後に残った者は自害し、ローマ兵に捕らえられて奴隷として売られるという屈辱を回避したのです。
『ユダヤ戦記』の著者フラウィウス・ヨセフスはこう伝えます(フラウィウス・ヨセフス『ユダヤ戦記』3ちくま学芸文庫)。
「生き残っていたのは2人の女と、5人の子供だけだった」
第二次世界大戦末期の沖縄戦でも、女性や子供を巻き添えにした集団自決の悲劇が起こりました。敵を悪魔化し、それに屈するくらいなら死を選ぶ。こういう心理状態は、いつでもどこでも起こりうるわけですが、これに宗教が絡むと人は死を恐れなくなり、むしろ天上界、来世での永遠の命を求めて、進んで死地に赴くようになります。
このような悪魔化された敵に対する攻撃性が外に向かえば、民衆を巻き込んだ容赦なき殲滅戦が展開されます。十字軍がその代表的な例です。
「主権国家」間の絶え間ない戦争が「戦時国際法」を生んだ P86
「主権」とは、ユグノー戦争中にフランスの法学者ジャン・ボダンが唱えた概念で、何者にも従属しない最高権力を意味します。中世以来、ローマ教皇や神聖ローマ皇帝といった超国家的な権威があったことを否定し、国家の君主が最高権力を持つ、と決めたのです。
同時にこれは、主権国家の内部での私闘を禁じ、主権者が軍事力を独占していく過程でもありました。
これ以後、欧州では世俗化が進み、国家が教会を管理する国教会制度により、カトリック教会は政治権力を失っていきました。
ウェストファリア条約以後、欧州全体をまとめる帝国は存在しなくなり、各国の君主がそれぞれ「主権」を持ち、対等な外交関係を結ぶというルールが生まれました(ウェストファリア体制)。
今の世界も、国連総会を例にとると各国一票ですから、ウェストファリア体制の枠組みが続いているわけです。
世界の他の地域、たとえば中東ではオスマン帝国、インドではムガル帝国、東アジアでは中華帝国(明・清)が君臨し、他の小国は帝国に朝貢するという形で安定した国際秩序を維持してきました。帝国は、臣下となった小国に朝貢を要求する一方、恩恵として莫大な金額の下賜(お返し)を与え、必要に応じて軍事援助も与えました。日本の豊臣秀吉が朝鮮に攻め込んだとき、朝鮮王から援軍要請を受けた明の万暦帝は朝鮮に出兵し、秀吉軍と戦っています。「世界の警察」、国際平和維持軍の役割を帝国が担ったのです。
欧州の場合、「各国対等」というと聞こえがいいですが、要は超国家的な帝国が不在となったため、国家間で戦争が起こっても調停者がいないのです。ですからウェストファリア条約後も絶え間なく戦争が続き、やがては世界大戦へ至るのです。
これを見通していたのがオランダの法学者フーゴー・グロティウスです。彼は主権国家の法の上に自然法(神の法)があると仮定しました。
自然法は、人間の生命・自由・平等・財産を保証する法のことです。国家と国家がぶつかり、国家の法の保護を受けられない戦争状態においても、自然法が守られるような仕組み、国際的な取り決めをすべきだとグロティウスは説いたのです(『戦争と平和の法』1625)。
また、国家主権が及ばない「公海」という概念を唱えたのもグロティウスです(『海洋自由論』1609)。スペインとポルトガルの世界分割協定(トルデシリャス条約)を否定し、オランダ船の航行の自由を擁護したのです。公海を私物化して軍事基地を建設し、航行の自由を脅かす大国が今もありますが、すでに17世紀にこの問題は決着がついているのです。
凄惨極まりない宗教戦争を経験し、ウェストファリア体制下で戦争を常態化させてしまったヨーロッパ人が、最後にたどり着いたのが国際法という知恵だったのです。
しかし、グロティウスの時代に国際法が整備されたわけではなく、さらにたくさんの戦争を経て、個々の条約や戦時慣習法の積み重ねの結果、徐々に国際法ができあがっていったのです。これらの戦時国際法の集大成が、第一次世界大戦の直前にハーグ万国平和会議で結ばれたハーグ陸戦条約(1899)なのです。
古代ギリシア人にとっての「国家意識」 P108
「お国のために戦う」という発想は、いつ頃始まったのでしょう?
人間の想像力には限りがあります。自分や家族を守るために戦う、先祖伝来の土地を守るために戦う、主君を守るために戦う……目に見える人やモノを守るために戦うのなら理解できます。しかし「国」とは何でしょう?
日本語(ヤマト言葉)の「くに」とは、故郷や出身地を意味します。「お国はどちらですか?」と聞かれて、「日本国です」と答える人はまずいないでしょう。
古代においても、支配層や知識人は国家意識を持っていたと思います。白村江の戦いに軍勢を送る中大兄皇子の胸中には、「祖国ヤマトを守る」という気概があったと思います。しかし、動員された兵士たちの胸中はどうだったでしょう。
白村江の敗戦のとき、筑紫の住人・大伴部博麻(おおともべのはかま)という兵士が唐軍の捕虜になり、長安へ送られました。
唐の日本侵攻計画を知り、帰国を急ぐ遣唐使4人の渡航資金を得るため、博麻は自らの身を奴婢として売り、その資金で4人を帰国させたのです。
その博麻が、30年後にようやく帰国します。伝え聞いた持統女帝はこれを喜び、「朝を尊び国を愛し、己を売りて忠を顕せることを嘉(よみ)す」という勅語とともに土地と位階を与えています(『日本書紀』巻三十 持続天皇4年10月22日)。ここでいう「国」とは日本国のことで、これが「愛国」という言葉の初出です。
その一方で、『万葉集』には九州防衛の防人として動員される兵士の、望郷と慟哭の歌が多く残されています。彼らは地方長官や地元の豪族の命令で動員されただけで、祖国愛に燃えていたわけではないでしょう。
中国でも、オリエントでも、古代における戦争とはこのようなものでしたが、ギリシアはやはり特別です。指導者が兵士一人ひとりに戦争目的を明示し、そこには明確な国家意識があったのです。
第2章で紹介したアテネの歴史家トゥキュディデスは、スパルタとの大戦争の第一年目(前431)の冬に行われた戦没者追悼式における将軍ペリクレスの演説を紹介しています。
われらの政体は他国の制度を追従するものではない。ひとの理想を追うのではなく、ひとをしてわが範に習わしめるものである。その名は、少数者の独占を排し多数者の公平を守ることを旨として、民主政治と呼ばれる。わが国においては、……すべての人に平等な発言がみとめられる。
……たとえ貧窮に身を起こそうとも、国に益をなす力をもつならば、貧しさゆえに道を閉ざされることはない。……
かくのごときわが国のために、その力が奪われてはならぬと、いまここに眠りについた市民らは雄々しくもかれらの義務を戦いの場で果たし、生涯を閉じた。あとに残されたものもみな、この国のため苦難をもすすんで耐えることこそ至当であろう。
かれらは公の理想のためにおのが生命をささげて、おのが名には不朽の賞讃を克ちえたるのみか、衆目にしるき墓地に骨をうずめた。……かれらの英名は末ながく、わが国に思いをいたすものの言葉にも行ないにも、おりあるたびに語り伝えられる。 (『戦史』巻二P66、P70、P72)
古代アテネで、庶民レベルまで国家意識が浸透していたのはなぜか?
ペリクレスの追悼演説でも言及されていますが、彼らには等しく参政権を与えられ、彼ら自身が都市国家運営の担い手だったからです。18歳以上の成年男子で構成される民会こそが国家の最高機関であり、開戦も、講和も、民会での承認(挙手による多数決)が必要だったからです。
指導者は市民の賛同を得るため開戦(あるいは講和)の必要を熱く語りました。市民は国家の運命をわが身同様に考えて真剣な討議を繰り返し、いざ開戦となれば、まさに「お国のため」に死地に赴いたのです。
国際法の構築に影響を与えた思想家たち P124
一世紀の間、西欧諸国を苦しめた不毛の宗教戦争 ―― その深淵をのぞき込んだヨーロッパ人は、神のためではなく人間のために生きることを決意しました。
最後の宗教戦争である三十年戦争の結果生まれたウェストファリア体制では、各国は主権国家として完全な独立を認められ、内政の不干渉と対等な外交関係という大原則を定めました。さらに条約という形で国家間の関係を維持し、一定のルールのもとに戦争の被害を抑制しようとしました。
・そもそも主権国家の成立要件とは何か?
・A国からB国が独立を求める場合、何を条件として独立を認めるのか?
・革命で政権が交代した場合、前の政権が結んだ条約は有効なのか?
・戦争はどのように開始し、どのように終わらせるのか?
幾多の戦争と講和の積み重ねにより、これらの細かいルールが、国際慣習法としてヨーロッパで集積されたものが国際法(万国公法)なのです。
第5章で紹介したグロティウスの唱えた近代国際法を具体的に構築した人物が、18世紀のスイスの法学者でドイツのザクセン公に仕えたエメリヒ・ヴァッテルでした。
ヴァッテルは『国際法』(1758)を著し、「無差別戦争観」を提唱したことで知られます。これは無差別に他国を侵略していい、という意味ではありません。
個人が神から与えられた自然権の一つとして生存権を持ち、正当防衛の権利を持つように、あらゆる国家はウェストファリア体制下で対等な主権を持ち、自衛の権利を行使できる。国家が生き残るために発動する戦争にはもはや「正義」も「不義」もなく、「正戦論」自体が無意味である、という意味です。
突きつめればすべての戦争は合法であるが、その被害を最小化するため戦争のルール(戦時国際法)を定め、ルール違反を罰するしかない、というのがヴァッテルの無差別戦争観なのです。
戦時国際法は、三十年戦争のようなだらだら続く戦争を回避するため、時間的・空間的に戦争を制限し、戦闘員(兵士)と非戦闘員(捕虜・一般市民)とを明確に区別します。このため、開戦と停戦を明確に宣言し、戦闘員には軍服の着用を義務付け、降伏の意思表示の方法や、捕虜の扱いを明文化しました。
フランス語で書かれたヴァッテルの『国際法』は英語に翻訳され、アメリカ合衆国の建国の父であるジョージ・ワシントン、ベンジャミン・フランクリンらに影響を与えました。彼らはイギリスに対する独立戦争の過程で、アメリカを主権国家として承認させるためにヴァッテルの『国際法』を援用したのです。
なお、ワシントンはニューヨーク社会図書館から『国際法』を借りたまま亡くなり、221年後の2010年に「返却」されて話題になりました。
建国間もないアメリカ合衆国は、ナポレオン戦争に巻き込まれます。欧州大陸をフランスのナポレオンが席巻すると、敵対するイギリスがアメリカ合衆国と欧州諸国との通商を妨害したため、米英戦争(第二次独立戦争)が勃発したのです。
ナポレオン戦争はフランスの敗北で終わり、ウィーン議定書(1815)でヨーロッパの秩序が再建されました。これと同時に、条約の締結手続きや特命全権大使・公使の常駐など、外交儀礼(プロトコル)がほぼ確立されました。ニューヨーク海事審判所の判事で、のちに合衆国の駐プロイセン全権大使も務めたヘンリー・ホイートンは『国際法原理』(1836)を著し、ウィーン体制下の国際法を集大成しました。
この本は各国語に訳され、特筆すべきはアヘン戦争(1840~42)後の東アジア各国が主権国家体制に参入する際のガイドブックとして学ばれたのです(後述)。
ビスマルク直伝! 日本が実践した「小国の生き残り戦略」 P166
フランス革命とナポレオン戦争は、ヨーロッパ諸国にナショナリズムの嵐を巻き起こし、スペインからロシアまで全ヨーロッパを巻き込む大戦争でおびただしい命が失われました。
戦後のウィーン会議では、戦勝4大国(イギリス・オーストリア・フロイセン・ロシア)に王政復古のフランスを加えた5大国が同盟を結んで平和を維持する「勢力均衡」と、フランス革命前の体制を正統とする「正統主義」の原則が定められ、ナショナリズムの運動は抑圧されました。
このウィーン体制を象徴する人物が、オーストリア帝国の外相(のち首相)のメッテルニヒです。ドイツ系のハプスブルク家の皇帝が、チェコ人、スロヴァキア人、マジャール(ハンガリー)人、クロアティア人の多民族国家を統治するには、ナショナリズムを徹底的に押さえ込むほかなかったのです。
しかし一度目覚めてしまったナショナリズムの炎は、消すことはできません。それは暖炉の熾火のようにくすぶり続け、燃料が投下されればたちまち燃え上がるのです。
ペリー来航の5年前、1848年にそれは起こりました。
パリで始まった選挙権拡大運動が二月革命に発展し、フランスで再び王政が倒されました。(第二次共和制)。革命の情報は、最新鋭の通信手段だった電信で欧州各国にリアルタイムで伝わり、ドイツ・イタリア諸国に革命が広がります。
ウィーンでも憲法制定を求める市民がハプスブルク家の宮殿を包囲します。皇帝はメッテルニヒを解任し、憲法制定を約束したのです。
ウィーン体制は音を立てて瓦解し、ドイツ全土ではじめて選挙が行われ、各国の代表がドイツ統一を議論しました(フランクフルト国民議会)。
けれども統一方法をめぐって議論は紛糾します。オーストリア皇帝とプロイセン王がドイツ皇帝の座を争い、議会はプロイセン王を皇帝に選出したものの、当のプロイセン王がイギリス型の自由主義憲法を拒絶、統一問題は振り出しに戻ります。
この直後にプロイセン王が首相に抜擢したのがビスマルクです。軍服を着た厳しい姿で有名ですが、ビスマルクは軍人ではなく外交官でした。
新興国家プロイセンの台頭を恐れたドイツの小国家群は統一に抵抗し、オーストリア帝国やフランスが介入の機会を狙っています。ビスマルクは圧倒的な軍事力を背景としつつ、大国の挑発に乗らず、外交交渉によって統一を進めました。いったん勝機が訪れればこれを逃さず、逆に敵国を挑発して相手側から開戦させ、防衛戦争と称して徹底的に叩きのめす――。
こうしてデンマーク戦争、普墺戦争と勝ち進み、最後にナポレオン三世のフランスを挑発して普仏戦争に圧勝し、占領したヴェルサイユ宮殿でプロイセン王ヴィルヘルムー世を皇帝に推戴してドイツ帝国を建国したのです。
ビスマルクの登場は、半世紀続いたヨーロッパの勢力均衡が崩れ、弱肉強食の覇権争いの時代が始まったことを意味します。ビスマルクはドイツ中心の複雑な同盟関係を結ぶことで仮想敵国フランスを牽制しましたが、ビスマルクを失脚させたドイツ皇帝ヴィルヘルムニ世は新たなパワーゲームに熱中し、やがて列強は第一次世界大戦に突入していきます。
この外交の天才ビスマルクのもとを、大久保利通・伊藤博文・木戸孝允ら日本政府首脳が表敬訪問したのは明治6年(1873)のことでした。
明治維新を成し遂げた日本は、敵(欧米)の内情を調べ、幕府が結んだ不平等条約の改正を交渉するため、1871年、岩倉具視を特命全権大使とするヨーロッパ使節団(岩倉使節団)を送り込みました。というより、大久保・伊藤・木戸や明治政府の要人の約半分が東京を留守にして、直接出向いたのです。
100余名の使節団は、6割が政府首脳と官僚、4割が留学生でした。行きは太平洋を渡りまず米国の西海岸に上陸。大陸横断鉄道で大西洋岸に出て、そこからヨーロッパに渡りました。帰りは地中海からスエズ運河を通り、植民地となったエジプト、インド、東南アジア諸国を見て戻ってきました。
彼らは帝国主義列強、とくにイギリスとフランスがいかに強大な力を持っているか、アジアやアフリカがどのように虐げられているかを、つぶさに見てきました。「これは本当にマズい」と思ったわけです。
岩倉使節団は建国2年目のドイツ帝国を訪問し、ベルリンではビスマルク主催の晩餐会に招待されました。米・英・仏・露の圧力にさらされてきた日本は、これまでドイツに無関心でした。しかし大国フランスをビスマルクが打ち破り、統一国家ドイツを建設したことは、使節団に強烈な印象を与えていました。ビスマルクもこの東洋の小国に好意的で、こう語りました。
貴国と我が国は同じ境遇にある。私はこれまで三度戦争を起こしたが、好戦者なわけではない。それはドイツ統一のためだったのであり、貴国の戊辰戦争と同じ性質のものだ。英仏露による植民地獲得戦争とは同列にしないでいただきたい。私は欧州内外を問わずこれ以上の領土拡大に興味を持っていない。 (久米邦武編『特命全権大使米欧回覧実記(三)』岩波文庫P329)
さらに続けます。
現在世界各国は親睦礼儀をもって交流しているが、それは表面上のことである。内面では弱肉強食が実情である。私が幼い頃プロイセンがいかに貧弱だったかは貴方達も知っているだろう。当時味わった小国の悲哀と怒りを忘れることができない。万国公法は列国の権利を保存する不変の法というが、大国にとっては利があれば公法を守るだろうが、不利とみれば公法に代わって武力を用いるだろう。 (前掲書P329)
ビスマルクは「欧米列強は、国際法に従っているように見えるだろう。しかし、そうではない。国際法は大国が自国の利益を拡大するために使っている理屈だから、力のない国は国際法を利用できないのだ」と説いたのです。したがって、帝国主義の時代に小国が生き残るためには ――
我々は数十年かけてようやく列強と対等外交ができる地位を得た。貴方がたも万国公法を気にするより、富国強兵を行い、独立を全うすることを考えるべきだ。さもなければ植民地化の波に飲み込まれるだろう。 (前掲書P329~330)
大久保利通はビスマルクに感化されて「大先生」と呼び、「新興国家を経営するには、ビスマルク侯のごとくあるべし。我、大いにうなずく」と記しました。
大久保暗殺の後、その遺志を継いだ伊藤博文も「日本のビスマルク」を自任しました。大日本帝国憲法の制定のためドイツ国法学を学ぶためベルリンを再訪した伊藤は、ビスマルクとも再会しています。
こうして明治日本はビスマルクのリアリズム外交を忠実に実践し、「富国強兵」の道を突き進んだ結果、日清戦争・日露戦争に勝利し、欧米諸国から列強の一員として認められたのです。
なぜ日清戦争は起こったのか? P192
日清戦争とは、朝鮮における日本と清の主導権争いでした。
「小中華思想」に毒された朝鮮は旧態依然としたままで、軍事的には空白地帯といっていい状態でした。ロシアの南下を危惧した清朝と日本は、いずれも緩衝地帯である朝鮮王国に内政改革を求めます。
日本は、日朝修好条規(1876)で「朝鮮は独立自主の邦」と認めた上で改革を迫りましたが、清朝は、伝統的・儀礼的な冊封国(中華皇帝が臣下とみなす国)だった朝鮮を、近代国際法における従属国(保護国)に転換しようと内政干渉を強化します。
朝鮮国王・高宗の父である大院君と、王妃の閔妃一族との権力闘争が起こると、西太后の命を受けた袁世凱が清軍を率いてソウル(漢城)を占領し、大院君を逮捕して閔氏政権を復活させます(壬午軍乱、1882)。
2年後の1884年、日本と結ぶ金玉均ら朝鮮の開化派がクーデタを起こすと袁世凱は再度出兵し、開化派を徹底的に弾圧し(甲申政変)、閔氏政権を事実上、保護国化したのです。日本は、開化派を守るために清軍と戦うほどの兵力がなく、天津条約を結んで日清両軍の撤兵と、再出兵時の事前通告を定めました。
それから10年、閔氏政権の腐敗と独裁が頂点を極め、これに激昂した農民が大反乱を起こします(甲午農民戦争/東学党の乱)。
閔氏政権は三度清軍の出兵を求めました。これを放置すれば、朝鮮が完全に清朝の手に落ちると判断した伊藤と陸奥も、「日本人居留民保護」を名目に出兵を命じたのです。
大鳥圭介公使が率いる日本軍がソウルの王宮を包囲し、「清軍は撤兵せよ」との詔勅を高宗に出させます。これに応じない清軍に対して「朝鮮政府からの要請」という名目で攻撃を開始、日清戦争が始まりました。
仁義なき秘密外交が第一次世界大戦の雌雄を決した P229
ドイツ陸軍参謀本部は、参謀総長シュリーフェンの作戦計画を採用しました(シュリーフェン計画、1905)。
(1) 仏・露との二正面作戦を回避し、先にフランスを全力で叩く。
(2) 対仏戦争を早期に終わらせるため、抵抗が予想される独・仏国境を回避し、中立国ベルギーを経由して、6週間でパリを攻略する。
(3) 全軍を東に向け、ロシアに勝利する。
(4) イギリスには参戦の隙を与えない。
考え抜かれた作戦でしたが、立案者のシュリーフェンが開戦の前年に死去し、後継者の小モルトケ(ビルマルクに仕えた大モルトケの甥)は神経質で、軍全体の指揮を執るにはあまりにも優柔不断でした。
当初は作戦通りベルギーを突破してフランスに侵攻したドイツ軍でしたが、東方からロシア軍が迫ると、首都ベルリンの防衛に不安を感じた小モルトケは、西部戦線(フランス戦線)のドイツ軍の一部を呼び戻して東部戦線(ロシア戦線)に振り向けました。シュリーフェンが禁じ手とした「二正面作戦」を始めてしまったのです。
西部戦線では戦力を削がれたドイツ軍の進度が鈍り、フランス軍にパリ防衛の時間的猶予を与えました。
これを見たイギリスがフランス側に立って参戦します。英・仏間に軍事同盟はないので、「ドイツ軍によるベルギーの中立侵犯」を罰するという理由をつけましたが、本当の目的は広大な植民地をドイツ軍から守るためです。
6週間どころか半年経ってもパリが陥落しないことに苛立つヴィルヘルム二世は、三国同盟の一員であるイタリアに参戦を促します。
イタリアは参戦しました。しかしイタリア軍が攻撃したのはフランスではなく、同じ三国同盟のオーストリアでした。すでにイギリスがイタリアと密約を交わし、三国同盟脱退と連合国(協商国)側に寝返ることを条件に、オーストリアとの係争地である「未回収のイタリア」の奪回を認めていたのです。
イギリスの秘密外交は中東でその威力を発揮しました。
ロシアが支援するバルカン同盟に敗れたオスマン帝国(トルコ)は、ドイツの支援を期待して同盟国側に立って参戦しました。イギリスから見れば、オスマン帝国は敵側に立ったわけです。イギリスは、オスマン帝国領のアラブ人の指導者フサインに戦後の独立を約束し、オスマン帝国に対する反乱を起こさせます(フサイン・マクマホン協定)。しかしアラブ人にはまともな武器もなく、近代戦の経験もありません。そこで英陸軍の工作員トマス・ロレンス大佐(アラビアのロレンス)がアラブ人の扮装で指揮をとり、イギリス製の武器で戦ったのです。
ロシアの首都ペトログラードでは、イギリス外交官マーク・サイクスと、フランス外交官ジョルジュ・ピコがニコライ二世と接触。アラブ人地域を三国で分割するという密約(サイクス・ピコ協定)を結びました。ロレンスが率いるアラブ軍がメッカから北上してシリアに入ると、そこにはフランス軍が展開していて北上を阻止されたのです。
飛行機・戦車など最新の近代兵器が投入された第一次世界大戦は、工業力が勝敗を分ける総力戦となりました。これに要する戦費は莫大なものとなり、増税ではまかないきれませんから、戦時国債の発行が不可欠でした。
イギリス外相バルフォアは、パレスチナに祖国建設をめざすユダヤ人の組織、英国シオニスト連盟会長であるウォルター・ロスチャイルドに書簡を送り、イギリス政府を代表してユダヤ人の「民族的故郷」建設を歓迎すると約束します(バルフォア宣言)。この結果、欧州で長く迫害されてきたユダヤ人のパレスチナ移住が始まり、アラブ人との紛争を引き起こすことになりました。ロスチャイルド家は欧州最大の金融資本家で、イギリス国債の最大の引受人でした。
こうしてイギリスの二重、三重の秘密外交によってオスマン帝国は解体され、フランス保護下のアラブ人地域(シリアとレバノン)、イギリス保護下のアラブ人地域(イラクとヨルダン)、ユダヤ人地域(パレスチナ)に分断されたのです。
オスマン帝国の崩壊は同盟国側の敗因の一つになったのみならず、その後の中東の不安定化の原因を作り出しました。現在、中東で起こっている紛争の多く ―― パレスチナ紛争、シリア内戦、クルド問題 ―― は、このとき恣意的に引かれた国境線上で起こっています。
かつてアヘン戦争を指導したイギリス外相パーマストンはいいました。
「永遠の友も、永遠の敵もない。あるのは永遠の利益だけだ」
これがイギリス外交の真髄であり、日英同盟の先行きを暗示しています。
「あの戦争」を何と呼ぶべきか? P260
1945年。大日本帝国は世界3位の規模を誇った連合艦隊を喪失し、太平洋の島々と東南アジアに展開していた膨大な数の日本兵は補給を断たれて取り残され、戦う以前に飢餓によって全滅していきました。
米軍はフィリピンから沖縄に上陸し、制空権を失った日本本土は米軍の無差別爆撃の標的とされ、主要都市は軒並み空爆を受け、3月10日の東京大空襲では一晩に10万人が殺され、8月6日の広島、同9日の長崎に対する原子爆弾の投下では20万人以上が殺されました。長崎原爆の日に満洲に侵攻したソ連軍は日本人開拓民を殺傷、暴虐の限りを尽くした上、南樺太と千島全島、択捉島・国後島まで占領、併合しました。
明治以来、営々と築き上げてきた国際的地位と海外領土をすべて失った大日本帝国は、連合国の降伏勧告(ポツダム宣言)を受諾。米軍を主力とする連合国軍の占領下に置かれました。
ダグラス・マッカーサーが率いる連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)は日本政府の上に君臨し、帝国陸海軍の解体、新憲法の制定、財閥解体、農地改革など徹底的な国家改造を行いました。6年後に独立を認められたものの、その後も日米安全保障条約によって米軍が駐留を続け、日本は実質的なアメリカの保護国とされて今日に至ります。
これらすべての災厄を招いたのが、1930年代に始まり、1945年の破滅的敗戦に至る一連の戦争でした。
「独立の維持と、国民の生命財産の保全」が国家の存在目的のはずです。そのために必要な戦争なら、一概に否定することはできません。日清・日露の戦争は、ロシアの脅威に対抗し、日本の独立を守るために必要な戦争でした。
日露戦争に勝利し、また第一次世界大戦では国際貢献を認められ、国際連盟の常任理事国として4大国の一つとなった日本。そのわずか四半世紀後に亡国の瀬戸際まで追い込まれたのは、なぜなのか?
これが本章のテーマです。
連合国のポツダム宣言では、「軍国主義者が日本国民を欺瞞し、世界征服の挙に出た」と説明し、彼らが日本の戦争指導者を裁いた東京裁判でも、侵略戦争を立案した「A級戦犯」として日米開戦時の東條英機首相以下、7名を絞首刑にしました。GHQの検閲のもとで新聞各紙に連載された「太平洋戦争史」でも、満洲事変に始まる一連の戦争は「軍国主義者」が計画・実行したものとされ、従来の「大東亜戦争」という呼称は、軍国主義者のプロパガンダである「大東亜共栄圏」を正当化するものとして使用を禁じられ、「太平洋戦争」と書き換えさせられました。この戦後に生まれた呼称が現在も学校教育で使われています。
満洲事変から大東亜戦争までの一連の戦争を連続したものと考える歴史観は、歴史学会では正統学説とされ、「十五年戦争」という呼称も使われています。
しかし満洲事変の段階では「世界征服」などのプランはどこにもありませんでしたし、「大東亜共栄圏」構想でさえ、日米開戦後にあわてて作ったものです。連合国が悪魔化した「はじめから世界征服を企てていた日本軍国主義者」なるものは存在しません。歴史を丹念に検証していけば、1930年代~45年の日本の戦争指導者の無計画と成り行きまかせぶりには、呆れるばかりです。
本章では連合国の妄想から生まれた「ポツダム史観」を排し、予断をできるだけ避け、事実のみに基づいて議論を進めます。したがって、「十五年戦争」「太平洋戦争」という戦後イデオロギーにまみれた用語を避け、当時の呼称である「北支事変」「日華事変」「大東亜戦争」を使用します。
石原莞爾も反対した日中全面戦争 P297
満洲事変を起こした石原莞爾には、満洲・シベリアの資源を確保して将来の世界最終戦争(対米戦争)に備えるという明確な戦略がありました。ですから石原は、万里の長城以南へは軍を進めようとせず、国際連盟の明確な支援を得られなかった中華民国側もしぶしぶ停戦に合意して、満洲事変の戦闘はすべて終結しました(塘沽停戦協定、1933)。この協定で緩衝地帯とされた北京周辺には、親日派の冀東防共自治政府が置かれます。
満洲事変が早期に終結した理由の一つに、中華民国における内戦がありました。蒋介石の上海クーデタで、壊滅的ダメージを受けた中国共産党でしたが、毛沢東を中心に農村部で組織を立て直し、満洲事変の混乱に乗じて首都南京の西南700キロメートルの地方都市・瑞金を攻略し、「中華ソヴィエト共和国」の独立を宣言したのです。
蒋介石はただちに瑞金制圧を命じ、100万の国民政府軍を動員しました。共産党はこれに耐えきれず、内陸方面へ撤収しました。この大逃避行を彼らは「長征」と呼んで美化していますが実際には敗残兵の群れでした。30万人いた共産軍(紅軍)は逃亡兵が相次ぎ、3万人にまで激減します。
「日本軍は皮膚病だが、共産党は心臓病である」
蒋介石の言葉です。長城の北の満洲にいる日本軍は放置しても構わないが、中華民国にとって命取りとなる共産党ゲリラは根絶するという決意表明です。
日・独による東西からの攻撃を恐れたソ連のスターリンは、各国共産党に呼びかけます。世界革命をいったん停止し、「反ファシズムで共闘できるようなあらゆる政治勢力と共産党との連合政権(人民戦線)を組織せよ」と。
スペインでは共産党員を入閣させたアサーニャ人民戦線政府が成立しますが、地主や力トリック教会が支持するフランコ将軍が反旗を翻し、内幟が始まります。反乱軍を支援するドイツ・イタリアが軍事同盟を結び(ベルリン・ローマ枢軸)、ソ連が政府軍を支援したため独・ソの代理戦争となりました。
ヒトラーはスペイン人民戦線を支援するソ連を、日本は満洲国と国境を接するソ連を、それぞれ仮想敵国とし、情報交換の目的で日独防共協定(反コミンテルン協定)を締結します。イタリアもこれに加わり、国際連盟を脱退した日・独・伊の三国は、「枢軸国」と呼ばれるようになります。
中国では「長征」途中の毛沢東が「八・一宣言」を発しました。1935年8月1日、モスクワのコミンテルン大会に出席していた王明ら中国共産党代表が発表したこの宣言は、蒋介石と張学良に対し、「内戦停止と抗日」を呼びかけました。
しかし「抗日」より「反共」を優先する蒋介石は共産党への攻撃を続けます。間に入った張学良は、蒋介石を西安におびき寄せて監禁し、内戦停止を強要しました(西安事件、1936)。脅迫されて命と引き換えに「内戦停止」を宣言させられたわけですから、蒋介石の本心はますます「反共」に傾きます。つまり、蒋介石は八・一宣言を共産党の陰謀と見抜き、これに応じなかったのです。
ちなみに蒋介石はドイツの軍事顧問団を受け入れ、ドイツからの支援で軍を近代化していました。国民党の「反共独裁」は、ナチの「反共独裁」にそっくりでした。日本は「反共」を旗印とする蒋介石政権とは同盟し、国共内戦で国民政府を支援すべきでした。ところがこのあと日本軍は、なぜか蒋介石に対する攻撃を開始したのです。
大事なことなのでもう一度書きますが、満洲事変は塘沽停戦協定で終わっていたのです。
日本は、何もなかった満洲の原野に莫大な投資を行ない、多くの開拓民を送り込んで近代国家を建設することに忙殺されていました。その目的は、直接的には満洲と国境を接するソ連との戦争に備えることであり、さらには日本と満洲を経済的に一体化して、将来の対米戦争に耐えうるような高度国防国家を建設することでした。ですから日本軍が、長城の南の中華民国に攻め込む理由もなければ余力もなかったのです。
日本にとって好都合なことに、蒋介石の南京国民政府は中国共産党との内戦で忙しく、日本との戦いには消極的でした。
とすれば、日中全面戦争で利益を得るのは、日本でもなければ国民政府でもありません。戦争を望んだのは何者か?
満洲の日本軍に脅かされているソ連のスターリンと、国民政府との内戦で追い詰められている中国共産党の毛沢東です。
日中全面戦争が勃発すれば、蒋介石も毛沢東と手を組まざるを得なくなります。八・一宣言の「内戦停止、一致抗日」が実現するのです。この戦争でどれだけの犠牲があろうが、首部・南京が陥落しようが、国民政府が崩壊しようが、いっこうに構いません。むしろ国民政府が敗戦で崩壊すれば、中国における共産主義革命の絶好のチャンスとなります。
「敗戦を革命に転化せよ!」という敗戦革命論は、ロシア革命の時のレーニンの作戦でした。第一次世界大戦では、ロシアをドイツとの戦争に引き込み、兵士のサポタージュによってわざと負け、帝政を瓦解させたのです。帝政ロシアを打倒することにおいて、ドイツ帝国とボリシェヴィキ(ロシア共産党)とは共犯関係にありました。スイスに亡命していたレーニンを、「封印列車」でロシアヘ送り込んだのは、ドイツ軍です。
盧溝橋事件(1937)に始まる日中全面戦争は、これまで「日本軍国主義の暴走」とだけ説明されてきました。共産党というファクターが覆い隠されてきたのです。
義和団事件後の北京議定書により、北京の公使館を防衛するという名目で、各国の軍隊が駐留していました。日本軍の北京駐留も北京議定書に基づくもので完全に合法です。人口が密集する市街地で軍事演習はできませんから、北京から車で約30分、盧溝橋がかかる河川敷一帯で日本軍が夜間軍事演習を行っていました。付近には国民政府軍が駐屯していました。
1937年の7月7日。闇の中、国民政府軍の方向から日本軍陣地に銃弾が撃ち込まれ、双方で撃ち合いになりました。これが盧溝橋事件です。
追い討ちをかけるように、日本人に対するテロが頻発します。
7月29日。今度は北京の東に位置する通州で、惨劇が起こりました。この地域は塘沽停戦協定で非武装地帯とされましたが、国民政府軍が残存していました。盧溝橋事件後、日本軍がこれに対する空爆を開始しますが、親日傀儡政権である冀東防共自治政府の保安隊を誤爆したことから、今度は保安隊が通州の日本人街を襲撃、非武装の日本国民(半数は朝鮮人)約200名以上をきわめて残虐なやり方で殺害したのです。
これらの事件が、国民政府軍あるいは防共自治政府の保安隊の中に潜り込んでいた共産党の工作員、あるいは共産党の支持者の仕業と考えれば、つじつまが合います。今後の研究にまちたいところですが、共産党が政権を握った今の中国では、自由な歴史研究はできません。共産党に不利な事実を記した史料も、証拠隠滅されているでしょう。真相は藪の中です。
この事件が報じられると日本の世論が激昂し、統制派の武藤章、田中新一らが唱える「対支一撃論」を勢いづかせました。
東京の陸軍司令部(参謀本部)では、参謀総長の閑院宮載仁親王(任1931~40)は皇族で名誉職、参謀本部の実務を担当すべき今井清参謀次長は入院中、事実上の責任者となった石原莞爾作戦部長は「長城の南へ行くな」という考えでした。満洲事変の首謀者が、支那事変ではブレーキ役になったのです。
盧溝橋事件は局地紛争でいったんは終わりましたし、通州事件は冀東防共自治政府が公式に謝罪し、慰謝料を支払ったことで一応は決着しました。
ところが今度は、第二次上海事変が発生します。
そもそも上海はアヘン戦争後に開港し、治外法権の外国人街(「租界」)が存在しました。日本人も3万人弱がここに居住し、これを守るため日本海軍陸戦隊1000人のほか、各国軍隊が駐屯していました。
第一次上海事変は満洲事変の直後、反日運動が高揚する上海で布教中だった日本人の日蓮宗僧侶らが、中国人暴徒に惨殺されたことから始まります。
日本海軍は陸戦隊を増派して上海市を威圧し、謝罪と賠償を求めました。この日本軍陣地に対し、国民政府軍の第一九路軍が攻撃、日本側が応戦して戦闘状態に陥ります。日本軍が圧勝し、各国が仲裁に入って停戦しました。
第二次上海事変は盧溝橋事件の直後、大山勇夫海軍中尉の車が中国軍に銃撃され、殺害された事件を発端とします。上海を包囲する陣地を構築していた国民政府軍3万が、日本人租界を防衛する日本海軍陸戦隊4000と交戦、双方が航空機による爆撃を行い、民間人に多数の犠牲が出ました。
近衛内閣は「支那軍膺懲、南京政府の反省を促す」との声明を出します。「膺懲」とは「懲らしめる」という意味で、この時期からさかんに使われています。これに応えて陸軍は、松井石根陸軍大将が指揮する上海派遣軍を動員しました。
こうして日中両軍は、宣戦布告なきまま全面戦争に突入し、南京へ後退する中国軍を追撃して、日本軍は中国大陸の奥地へと深入りしていったのです。
参謀本部では、石原莞爾作戦部長が戦線不拡大に奔走していました。「今は満洲国の建設に全力を注ぐべきで、無用な戦争は避けるべきだ」と。
ところが直属の部下である武藤章作戦課長以下、参謀本部の大勢は「戦線拡大」。内モンゴル(後述)に戦線を拡大していく関東軍の説得に赴いた石原に対し、武藤は、
「われわれは、満洲事変で石原閣下がされた行動を見習っているだけです」
といい放ち、石原を絶句させます。
ついに石原は近衛首相に進言しました。
「北支(華北)の日本軍を満洲国にいったん撤退させ、近衛首相が南京へ飛んで、蒋介石との首脳会談を実現するべきです。石原がお伴します」と。
近衛首相の側近・風見章書記官長がこの石原案を握りつぶした結果、近衛首相は「国民政府を相手とせず」という意味不明の声明を出してしまいます。
参謀本部で孤立した石原は作戦部長を解任され、関東軍の参謀として左遷されますが、今度は関東軍参謀長の東條英機と衝突します。
世界最終戦論という遠大な世界観に基づいて満洲国を理想国家にしようと行動する石原に対し、東條には世界観というものがなく、規則に従い、「前例を踏襲するだけ」の典型的な官僚タイプの軍人でした。石原は東條を無能と面罵し、激怒した東條は、石原参謀を罷免します。
東條英機は近衛内閣の陸軍大臣を経て首相となり、日米開戦を決断しました。石原のような異才を生かせず、東條のような事なかれ主義の凡庸な人物が出世するシステム。これは今の日本の官僚機構でも変わっていません。
「天才的戦略家」石原莞爾をつぶした「凡人官僚」東條英機 P312
ここからは、のちの東京裁判で「A級戦犯」として処刑され、ヒトラー、ムッソリーニと並ぶ独裁者、ファシストとして悪魔化されてきた東條英機、その実像に迫ってみましょう。
東條英機の父・英教は、戊辰戦争で新政府軍に抵抗した盛岡藩士の子として生まれます。陸軍大学の一期生となり、首席で卒業という秀才であり、机上の作戦計画では優秀でしたが、日露戦争の実戦ではミスを重ねます。また陸軍長州閥のドンである山縣有朋への批判を繰り返したため、大将になれずに退役となっています。英教はこれを悔やみ、息子・英機に夢を託しました。
努力家だった息子の英機は父の期待に応えて陸大をめざし、3度目の挑戦で合格します。このとき、東條英機の陸大受験を指導したのが、陸軍士官学校で一期先輩の小畑敏四郎や永田鉄山、岡村寧次(いずれも陸士16期)でした。東條は、小畑の下宿に泊まり込んで受験勉強をしています。
陸大卒業後は駐在武官としてドイツに派遣され、南ドイツの保養地バーデンバーデンで小畑・永田・岡村の3先輩と再会。長州軍閥打倒と陸軍の刷新を誓ったというのが「バーデンバーデンの密約」で、東京裁判では「軍部暴走の始まり」ではないかと疑われています。4人の交流は帰国後も続き、「一夕会(いっせきかい)」という勉強会を立ち上げました。東條の4期後輩になる石原莞爾もこれに加わり、会の方針が定まりました。
・満蒙問題の解決(→満洲の軍事占領)
・陸軍人事の一新(→長州閥ではない真崎甚三郎・荒木貞夫らを担ぐ)
歩兵第一連隊長時代の東條は、部下の兵卒一人ひとりの家庭環境まで調べ上げ、声をかけました。陸大卒のキャリア将校は、中学を出て徴兵されたばかりの兵卒から見れば「雲の上の人」だった時代です。東條は「人情連隊長」として人気を博しました。
満洲事変後の1935年、東條は関東軍の憲兵隊司令官として満洲に配属されます。憲兵隊とは軍事警察のことで、思想警察の役割を果たしました。東條は関東軍内部の共産主義者の検挙に辣腕を振るい、二・二六事件では皇道派を摘発して関東軍参謀長の板垣征四郎に評価され、板垣の後任として参謀長に昇進します。のちに東條が陸軍大臣に抜擢されるのも、板垣の引きがあったからです。東條は板垣の期待によく応え、やがて連合国による東京裁判で、板垣とともに絞首刑となります。
努力家で、先輩にかわいがられ、後輩の面倒見がよく、与えられた任務を忠実にこなす東條英機。その部下として関東軍参謀に配属されたのが、天才肌で組織を嫌い、空気を読まず、上官を上官とも思わない石原莞爾でした。
支那事変の不拡大方針論者として東京の参謀本部で孤立し、関東軍参謀として左遷されてきた石原莞爾は、直属の上司である東條参謀長を「憲兵隊しか使えない女々しいやつ」と嘲笑します。激怒した東條は石原を解任し、武藤章らの事変拡大派で側近を固めました。
石原の言う通り、憲兵としてのキャリアを積んできた東條参謀長にとって実戦経験がないことが弱みでした。そしてついにその機会がやってきました。関東軍の内モンゴル侵攻 ―― チャハル作戦です。
清朝の崩壊後、モンゴル人居住区の北半分(外モンゴル)はモンゴル人民共和国を建ててソ連の承認を得ましたが、南半分の内モンゴルは中華民国に併合され、独立運動を続けていました。
満洲事変を起こした日本軍(関東軍)が隣接する内モンゴルに派兵すると、モンゴル人指導者でチンギス・ハンの30代目の子孫である徳王デムチュクドンロブが日本軍に呼応して挙兵しますが中国の国民政府軍との戦闘に敗れてしまいます。
この徳王を支援する形で、関東軍は東條を指揮官とする部隊を内モンゴルのチャハルに派遣したのです。「東條兵団」は国民政府軍の排除に成功し、徳王は「蒙古連合自治政府」を樹立できたのです。この政府は最後まで日本軍におんぶに抱っこの状態で、徳王は満州国の溥儀と同様に日本軍の傀儡でした。
日本の敗戦でその地位を失った徳王は、モンゴル人民共和国に亡命しますが、結局は中華人民共和国に引き渡され、「戦犯」として投獄されます。
「東條兵団」は軍紀に厳しく、部下に略奪を禁じました。また世界的な仏教遺跡である雲崗石窟の保護にも配慮するなど評価すべき点もあります。その反面、補給を無視した進軍で兵を疲弊させるなど、帝国陸軍の悪弊をのぞかせています。
近衛内閣の陸軍大臣となった板垣征四郎は、東條を東京に呼び寄せ、陸軍次官に抜擢します。この東條陸軍次官が、戦線拡大を巡って多田参謀次長と激突します。
石原の推薦で参謀次長になった多田駿は、河本大作の義弟として関東軍でキャリアを積みました。天津に司令部を置く支那駐屯軍司令官に任じられると、対中国政策(多田声明)を明らかにしました。この中で多田は、「厳乎たる威力の随伴を必要」としつつも、「搾取主義を排し、与うる主義をとるべし」「支那の独立を尊重し、民族の面目を保持すべし」と論じます。彼は、関東軍の石原莞爾と気脈を通じていたのです。
そもそも参謀本部とは何か? ここで軍政と軍令との違いについて説明しておかなければなりません。
「軍政」とは軍隊の編制 ―― 予算の獲得と配分、徴兵と訓練、装備の購入などの実務のことで、これを担当するのが陸軍省・海軍省です。予算は内閣が原案を作り、衆議院の承認を要しますから、陸軍大臣・海軍大臣は内閣(政府)の一員です。
「軍令」とは軍事行動における作戦・指揮命令のことで、「○○作戦のため○月○日までに陸軍○万人を○○へ移動する」という計画書を作成します。軍令を担当するのが陸軍参謀本部・海軍軍令部で、参謀総長・軍令部長は内閣のメンバーではありません。
現在の日本でも「軍政」は防衛省(トップは防衛大臣)、「軍令」は統合幕僚監部(トップは統合幕僚長)ときっちり分けています。
南京の蒋介石政権に最大の軍事援助を行ってきたのはドイツでした。軍事顧問団を派遣し、大量の武器を輸出していました。だから国民政府軍は、制服までドイツ風です。反共主義を掲げる蒋介石の中国は、ヒトラーにとっても同盟国だったのです。
ところが、日華事変で蒋介石が敗走を続けるのを見たヒトラーは中国を見限り、日本と同盟する道を選びました。これが日独伊三国同盟(1941)です。トラウトマン工作の段階では、日・独はまだ同盟国ではありません。
先述の通り参謀総長は皇族の閑院宮であるため、多田参謀次長が参謀本部の事実上のトップとなり、南京駐在のドイツ大使トラウトマンの仲介により蒋介石との停戦交渉を進めます(トラウトマンエ作)。共産党との内戦に苦しむ蒋介石と日本との同盟が成立すれば、これで支那事変は終わり、日米戦争もなかったわけです。
1937年12月2日、蒋介石はトラウトマンに和平の受諾を伝えました。ところが参謀本部の決定を無視して現地日本軍が南京を攻略してしまいます(12月13日)。
これを見た近衛内閣の広田弘毅外相はゴールポストを動かし、賠償金と領土割譲を求めるなど蒋介石が受け入れ不可能なレベルに条件をつり上げたため交渉は決裂、「国民政府相手とせず」の近衛声明(38年1月)に至ったのです。こうして、多田参謀次長の和平努力は水泡に帰しました。近衛内閣がトラウトマン工作を妨害したことは、ポイント・オブ・ノーリターンを越えたことを意味します。
かつてビスマルクは、ドイツ統一を邪魔するオーストリア帝国との戦い(普墺戦争)でモルトケ参謀総長との二人三脚により圧倒的勝利を収めた時、敵都ウィーンの攻略を禁じて和議を結びました。この戦争の目的はドイツの統一であり、ウィーンの攻略ではなかったからです。
以上見てきたように支那事変の一年目の段階では、陸軍参謀本部が「事変不拡大」、近衛内閣が「事変拡大」だったのです。「好戦的な軍部が近衛内閣を戦争に引きずり込んだ」のではなく、「好戦的な近衛内閣が軍部を戦争に引きずり込んだ」のです。
もちろん、軍部にも事変拡大派はいました。その急先鋒だった陸軍次官・東條英機は、多田参謀次長の罷免を要求しました。結局、「喧嘩両成敗」で東條も多田も罷免され、多田は満洲の第三軍司令官として東京から遠ざけられ、日米開戦の年に予備役に編入されました。一方の東條は第二次・第三次近衛内閣の陸軍大臣を経て、総理大臣の地位に登っていきます。第三次近衛内閣のあとが、東條内閣ではなくて多田内閣だったら、日米開戦は避けられたと私は思います。しかし残念ながら昭和天皇は、多田を信用していませんでした。「満洲事変を起こした石原の仲間だ」という理由です。
敗戦後、多田駿は、東京裁判に検察側証人として出廷し、被告人の東條英機・板垣征四郎らと再会します。法廷での多田は、板垣・松井石根・土肥原賢二のために堂々たる弁護を行いました。同時期の手記では石原莞爾について、
「実に日本の先覚者なり。この先覚者を用ふる能はざりし日本は、今日の如きありさまとなる。誰の罪ぞや」と告白しています。
石原莞爾には明確な戦略がありました。「支那とは早く和議を結び、対ソ戦に勝利し、将来の対米戦に備えて満洲を基盤に国力を蓄える」というものです。
東條英機の戦略はどのようなものだったのでしょう。陸軍次官時代の東條は、軍人会館(現在の九段会館)での演説でこう述べています。
「支那事変の解決が遅延するのは、支那側に英・米とソ連の支援があるからである。したがって事変の根本解決のためには、今より北方に対してはソ連を、南方に対しては英・米との戦争を決意し準備しなければならない」
中国と戦いながら、ソ連とも米・英とも戦うというものです。二正面作戦を避けるという、戦略のイロハのイもわかっていなかったことになります。これでは負けて当たり前です。石原
が東條を侮蔑していたのもわかります。そもそも昭和の陸軍大学校というのは、いったい何を教えていたのでしょう?
これは東條に限ったことではなく、石原を除く昭和期の将軍たちの大半が、大局的な戦略思想に欠けていたのは致命的なことでした。戦略がないから行き当たりばったり、成り行きまかせで戦争を行い、戦線を無限に拡大させて泥沼化させたのです。
外交官も同様で、明治期の陸奥宗光や小村寿太郎のような大局観を待った人物が出ていません。「焦土演説」の内田康哉外相も、「トラウトマンエ作」を潰した広田弘毅外相も、ひたすら世論に迎合し、マスコミ受けする言動を繰り返しただけです。
なぜこうなったのか。
教育の問題だと思います。東京帝大にせよ、陸軍大学・海軍大学にせよ、あらかじめ決められた模範答案にいかに早くたどり着けるか、という情報処理能力ばかりを競ってきたのです。
現実の国際社会で起こることは、日々刻々条件が変わる中で臨機応変に対処しなければなりません。ところが受験エリートであるほど、臨機応変ができないのです。変化する現実に対して常に硬直した対応しかできず、一度決めたことは変えられないのです。それが模範解答だからです。
さらには、学生時代の人間関係、先輩・後輩関係が官庁に入ってからも上司と部下の関係として継続します。実務能力より人間関係が重視され、国益よりも組織防衛が重視されます。部内の失敗は隠蔽され、他の官庁とは情報の共有さえできません。
東大を何位で卒業しました、陸大・海大を何位で卒業しましたという学歴だけで出世が決まり、実務についてからの業績は軽視される。陸大・海大卒の超エリート軍人たちが、実際の戦争指導で致命的なミスを犯して多くの兵士を死なせても、左遷も降格もされずに出世街道を進み続ける。
ミッドウェー海戦で大敗した南雲忠一(なぐもちゅういち)、ガダルカナルの戦いで大敗した辻政信(つじまさのぶ)、いずれも明確な責任もとらされずにだらだらと戦争指導を続けています。
そしてこの学歴偏重・年功序列の人事システムは、敗戦後も踏襲され今日まで続いているのです。霞が関の高級官僚の皆さんには、胸に手を当てて自問していただきたいものです。あなたのその判断は、国益のためですか? 省益のためですか?
彼らはソ連軍による「解放」を望んでいた P402
ポツダムは、敗戦国ドイツの首都ベルリン近郊の別荘地です。45年7月、連合国三巨頭がここに集いました。スターリンとチャーチルはヤルタ会談と同じ。病没したFDRに代わって副大統領から昇格したトルーマンが出席しました。
ポツダムにおけるトルーマンの懸念は、東欧にありました。スターリンがヤルタ協定に違反してポーランド自由選挙を拒否し、ロンドンから帰国した亡命政府の要人を次々に逮捕した結果、ポーランドが共産党政権になってしまったことです。同じやり方で、チェコやハンガリーなど東欧諸国がソ連の軍門に降りつつありました。
前大統領FDRとの密約通り、ソ連が8月に対日参戦した場合、満洲や中国本土、朝鮮、日本本土までもがソ連軍に占領され、共産化する恐れがある――
アメリカは中国市場への自由なアクセスを守るために対日戦争を戦ってきたのです。東アジア全体が共産化し、ソ連の勢力圏になってしまったら、米国企業の自由な投資や営業は望めなくなります。
ソ連との密約は反故にはできない。東アジアをソ連に引き渡さないためには、無駄な抵抗を続ける日本をソ連参戦前に降伏させるしかない。当初の作戦では、米軍による東京攻略は45年の12月。これでは遅すぎるし、米兵の犠牲も計り知れない。
ほかに方法はないものか ―― 。
このとき、ポツダムのトルーマンのもとに、陸軍から極秘電報がもたらされました。
「赤ん坊は無事に生まれた。Babies satisfactorily born.」
ニューメキシコ州アラモゴードの砂漠で行われた、人類史上初の原爆実験成功の知らせです。トルーマンはためらいませんでした。「8月上旬、日本へ投下せよ」。
日本に対するポツダム宣言は、米・英・ソの三首脳が合意しましたが、対日参戦前だったスターリンは署名せず、重慶の蒋介石に電話で了承を取り付け、発表されました。その最後の部分で原爆投下の可能性をちらつかせ、日本を脅迫しています。
13、われらは日本国政府が直ちに全日本国軍隊の無条件降伏を宣言し、かつ右行動における同政府の誠意に付、適当かつ充分なる保障を提供せんことを同政府に対し要求す。右以外の日本国の選択は、迅速かつ完全なる壊滅あるのみとす。(国立国会図書館「日本国憲法の誕生/憲法条文・重要文書」著者が現代仮名遣いに変更)
刻一刻と、大日本帝国は奈落の底へと突き進みます。
45・8・6 米軍、広島に原爆投下。
45・8・9 ソ連が対日参戦。米軍、長崎に原爆投下。
45・8・15 昭和天皇、ポツダム宣言受諾を国民に発表。
ポツダム会談が開かれた45年7月、満・ソ国境にソ連軍の大部隊が続々と集結していくなか、瀬島龍三が東京の大本営作戦課を離れ、「関東軍作戦参謀」の肩書で満洲へ赴任しました。
スターリンは日ソ中立条約の破棄を声明。同条約は破棄通告の一年後まで有効でしたが、米国が原爆を投下し、日本の降伏が早まったと判断したスターリンは、対日参戦を即断しました。
8月9日、ソ連軍が満洲、内モンゴル、朝鮮、南樺太へなだれを打って侵攻します。
関東軍は南満洲に防衛線を敷き、撤収を開始しました。北満の日本人の満蒙開拓団は置き去りにされ、ソ連兵による虐殺と陵辱にさらされます。関東軍の山田乙三総司令官、泰彦三郎総参謀長、瀬島龍三作戦参謀はソ連軍の捕虜となり、拘束されます。このとき、ソ連極東軍司令官ワシレフスキー元帥と停戦交渉にあたったのが瀬島でした。この関東軍の敗走は、「ソ連軍の不意打ちを食らったから」と説明されてきましたが、大本営のこれまでの行動を見ていくと、「はじめから満洲をソ連に引き渡すためのやらせ、戦う振りだったのではないか?」という疑惑が湧いてきます。
瀬島のもとで、満洲に出向していた大本営作戦課の朝枝繁春参謀が、ソ連軍侵攻後の満洲について大本営に送った報告書は東京には残されず、ソ連崩壊後の1993年に、ロシア国防省公文書館が機密解除で公開しました。
この「関東軍方面停戦状況に関する実視報告」(45・8・28)を見てみましょう。
・既定方針通り大陸方面に於いては、在留邦人および武装解除後の軍人は、ソ連の庇護下に土着せしめ生活を営むこととし、ソ連側に依頼するを可とする。
・さらに土着するものは、日本国籍を離るるも支障なきものとす。
満蒙開拓団などの在留日本人、武装解除した日本兵は帰国させず、ソ連に身柄を預けるというのです。これは棄民です。
70万人のシベリア抑留と強制労働はスターリンが一方的に行ったのではなく、東京の大本営の了解に基づくものだったのです。
ソ連は元日本兵を強制収容所に送り込み、強制労働に従事させるとともに徹底的な思想教育を行いました。
「君たちは日本帝国主義の犠牲者である。この戦争を引き起こしたのは天皇と財閥、軍閥である。祖国に戻ったら帝国主義を打倒し、社会主義を実現しよう!」
瀬島、朝枝ら元日本軍将校の一部はソ連の工作員として教育されます。モンゴルのウランバートル近郊にある第7006俘虜収容所が政治教育の舞台となりました。帰国後は東京のソ連大使館の諜報部員であるラストヴォロフの指揮下に入り、アメリカ占領軍(GHQ)の情報をソ連側に送り続けました。
ところが朝鮮戦争後の1954年、元締のラストヴォロフ本人がアメリカに亡命し、ソ連の対日工作の実態を米議会で証言するという大事件が起こります。
追い詰められた朝枝繁春と志位正二は警視庁に出頭し、ラストヴォロフ配下でのソ連の工作員だったことを自白します。
志位正二は関東軍第三方面軍情報参謀でしたがウランバートルに抑留され、工作教育を受けました。帰国後は、GHQの参謀第二部(G2)の地理課に勤務し、シベリア抑留者の調書から地図を作成するという業務に従事、その後は外務省アジア局調査員となり、情報をソ連大使館に渡していました。甥の志位和夫は東大工学部を経て、日本共産党の委員長となります。
朝枝や志位はソ連のスパイであったことを自白しましたが、スパイ防止法を廃止してしまった戦後の日本では、罪に問われることはなかったのです。
瀬島龍三はどうなったのか。
瀬島は「大物」として11年間シベリアに抑留されました。シベリアでは兵士とともに肉体労働に従事し、それなりに苦労したようですが、東京裁判ではソ連側証人として出頭しただけで被告人にはならず、ラストヴォロフ事件にも巻き込まれなかったのです。
釈放された後は、伊藤忠商事という小さな商社に入社し、ソ連・中国との人脈を生かして同社を巨大商社に育て上げ、最後は伊藤忠商事の会長、財界の重鎮として政界にも影響力を及ぼしました。
大本営作戦参謀の生き証人として、戦後、多くのインタビューに応じ、饒舌に語りましたが、肝心のソ連との関係については巧妙に話をそらし、口をつぐんだまま2007年になくなりました。工作員としても財界人としても、きわめて有能な人物でした。
そもそも日本を泥沼の戦争に引きずり込んだ「昭和維新」の思想とは、天皇をいただく国家社会主義、北一輝の思想であり、そのモデルはソ連型社会主義でした。統制派と皇道派との抗争は、「革命方針」をめぐる「内ゲバ」に過ぎません。
軍事クーデタ(二・二六事件)によってその実現を図った陸軍皇道派に対し、統制派が一貫してソ連との不戦、対中国・対米国との戦争拡大を推進して大日本帝国を存続の危機に陥れ、その最後の段階でソ連の日本占領を容易にする「本土決戦」を唱え始めたことは、もはや偶然とは思えません。
彼らは日本が敗北し、ソ連軍に「解放」されることが、「昭和維新」の近道だと信じていたのです。米軍に占領されれば、資本主義社会と財閥の跋扈が続くだけなので、ソ連軍による占領に意味があったのです。このような「赤い将校たち」によって東京の大本営は乗っ取られていたのです。そして数百万の若者を戦地に動員して十分な補給も行わず、屍の山を築いていった責任者であるこの者たちは、戦後も生き残って政財界にも影響力を及ぼし、大日本帝国を崩壊させた自らの戦争責任については口をつぐんだままなのです。
「国連による平和」という虚構 P410
アメリカ・シカゴ大学の国際政治学者ジョン・ミアシャイマーは、個々の主権国家を超えた「世界権力」が存在しない以上、国際システムは常にアナーキー(無政府状態)であり、大国はその生存をかけて、他の大国との覇権争いを永久に続けると論じました。
その上で、国際関係を次の三つのパターンに分けました。
・一極(unipolar)システム……中華帝国や古代ローマ帝国。一つの覇権国家が支配する
・二極(bipolar)システム……19世紀の英・露対立、20世紀後半の米・ソ冷戦
・多極(multipolar)システム……ウェストファリア体制、ウィーン体制、ビスマルク体制
このうち一極システムが最も安定しており、二極システムがこれに次ぐこと、そしてドングリの背比べのような多極システムが最も紛争を生みやすいことを彼は指摘しているのです(ジョン・ミアシャイマー『大国政治の悲劇』五月書房新社)。
二つの世界大戦は、多極システムの不安定さを立証しました。第一次世界大戦の反省の上に構築築された国際連盟とは、要するに主権国家の談合組織であり、植民地代表はもちろん米国やソ連といった大国が参加せず、世界恐慌という極限状態の中で、日本・ドイツ・イタリアが脱退して瓦解しました。
国際連盟に代わるもっと強力な国際機構を作ろうという構想は1941年8月、独ソ戦争が始まった直後に訪米した英チャーチル首相が、米国大統領FDRとの大西洋上会談 ―― 文字通り、大西洋に浮かぶ英軍艦プリンスオブウェールズの艦上で調印した大西洋憲章八ヵ条の最後の項目で、はじめて明記されました。
この4ヵ月後の12月に日米が開戦し、英領シンガポール防衛に派遣されたプリンスオブウェールズは、日本海軍の攻撃機に襲われ、沈没します(マレー沖海戦)。
明けて42年1月1日、連合国26カ国が「the United nations(連合国)」として共同宣言を発表し、枢軸国(日・独・伊)との単独不講和を誓いました。
この26カ国が、「国際連合 the United States(UN)」の原型となりました。「連合国」を「国際連合(国連)」と訳し変えたのは日本外務省ですが、これが定着してしまったので本書でも「国連」の訳語を使います(中国語ではいまも「聯合国」の訳語を使っています)。国連憲章の起草は大戦末期の44年、米国ワシントン近郊のダンバートン・オークスで進められました。
国連の基本原理も、多極システムの維持にあります。具体的には、一国一票の国連総会の上に、最高機関としての安全保障理事会(安保理)が置かれます。
当初、国連軍の出動による武力制裁権を持つ安保理は、拒否権を持つ常任理事国5カ国と、選挙で選ばれる非常任理事国6カ国の計11カ国から構成されました(現在は非常任理事国が10カ国、計15カ国)。5大国とは、第二次世界大戦の勝者となった5大列強(米・英・仏・中・ソ)です。
5大国が拒否権を発動しなければ多数決で採決されますが、5大国のうち1カ国でも拒否権を発動すれば、そこで審議は停止し、議案は否決されてしまいます。
拒否権なるものを最初に要求したのは、ソ連のスターリンでした。
5大国のうち米・英・仏は資本主義陣営。中国は当時まだ蒋介石政権だったので米国陣営。ソ連は孤立しており、残り4大国から武力制裁の対象にされることを恐れたのです。中国の代表権が毛沢東の共産党政権に交代するのは1971年のことです。
1945年のヤルタ会談で、米・英がスターリンの要求をのんで、5大国の拒否権が国連憲章に追加されました。結果、ソ連とその同盟国がいかなる軍事行動を行っても、国連安保理には武力制裁ができなくなりました。この愚かな決定を他の4大国が受け入れたのはなぜか?
自分たちが起こした軍事行動に対する安保理の武力制裁にも、拒否権を発動できるからです。大戦後のソ連は、ハンガリーやチェコ、中国やアフガニスタンに対して侵攻しました。英・仏はエジプトに対し(スエズ戦争)、米国はベトナムに対し、中国もインドやベトナムに対し、軍事侵攻を行っています。これらはれっきとした侵略戦争ですが、国連安保理は何も対応できませんでした。ソ連は120回以上、米国は80回以上、拒否権を発動し、安保理の機能を麻痺させてきました。英国は32回、フランスは18回、中国は10回、拒否権を発動しています。
つまり、安保理5大国が引き起こす戦争を止める権限を、国連は持たないのです。ですから日本と5大国(ロシアや中国)との間で領土紛争が起こった場合、もし日本が安保理に提訴したとしても、相手国が拒否権を発動すれば、それでおしまい。国連は動きません。
5大国以外の国が起こした戦争については、安保理が介入して武力制裁を行なった例が2回だけあります。朝鮮戦争と湾岸戦争です。
前者はソ連の同盟国だった北朝鮮が韓国に侵攻、後者はソ連の同盟国だったイラクがクウェートに侵攻した戦争です。けれ
ども、対米関係の悪化を恐れたソ連は北朝鮮とイラクを見捨て、前者の場合は棄権(安保理を欠席)、後者の場合は武力制裁賛成に回ったため、安保理決議が通ったのです。70年を越える国連の歴史の中で、武力制裁にゴーサインが出たのはこの2回だけなのです。
なお、安保理が直接指揮する「国連軍」なるものも存在しません。実際には安保理決議が可決されたあと、国連加盟国の有志が連合軍を編制するのです。これを「多国籍軍」とか「有志連合」といいます。朝鮮戦争に出撃した「国連軍」も、その実態は米軍を主力とする有志連合軍でした。
「旧敵国条項」についても触れておきましょう。
「旧敵国」すなわち日・独・伊に対しては、安保理の承認なしに軍事的強制力を発動でき(国連憲章第53条)、第二次世界大戦の戦後処理についても、安保理の承認は不要である(第107条)、という規定です。
日本やドイツが抗議を繰り返した結果、1995年12月に国連総会がこの条項を削除すべきである、と決議しました。しかし国連憲章の改定に必要な5大国の承認が得られず、いまだにこの条項は残っているのです。
たとえば、日本と他の国連加盟国との間で領土紛争が起こったとしましょう。「旧敵国」である日本に対する軍事行動は、安保理の承認なしに可能なのです。
「国連に加盟していれば平和が守れる」「いざという時は国連軍が守ってくれる」という愚かな幻想から、日本人は早く目覚めるべきです。
<注>本分では『「国際連合 the United States(UN)」の原型となりました。』と印刷されていますが、「国際連合 the United Nations(UN)」の誤りだと思われます。
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/19be63e4.34db3a5c.19be63e5.f4e2f5ce/?me_id=1276609&item_id=12376116&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbooxstore%2Fcabinet%2F00977%2Fbk4813284620.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbooxstore%2Fcabinet%2F00977%2Fbk4813284620.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
