〈新訳〉フランス革命の省察 「保守主義の父」かく語りき
保守について知ろうと思えば、先ずはエドマンド・バークの『フランス革命の省察』に触れるべきだろうと考えていました。しかし想像するに、時代も経っていることだし訳書でも読むのが難しいだろうと思っていました。
本書は編者がプロローグで書いているように、原著を翻訳しただけのものではないということで、その点でもバークの思想を理解しやすい内容になっているのだと感じました。
また編者の佐藤氏は、西部邁ゼミナールやチャンネル桜で見知っていたこともあり、本書を手にした理由の一つでもあります。
本書の帯には「この迷走、この混乱! 今の日本とどれだけ違う?」とありました。読み進める中で、日本で起こったことや今起きていることなどがいくつも想起されました。
本書は、今の日本を生きる我々の精神武装の一助にもなると感じました。
佐藤健志編集の『〈新訳〉フランス革命の省察 「保守主義の父」かく語りき』を紹介するために、以下に目次や目を留めた項目をコピペさせていただきます。
興味が湧いて、他も読んでみたいと思ったら、本書を手にしていただければと思います。
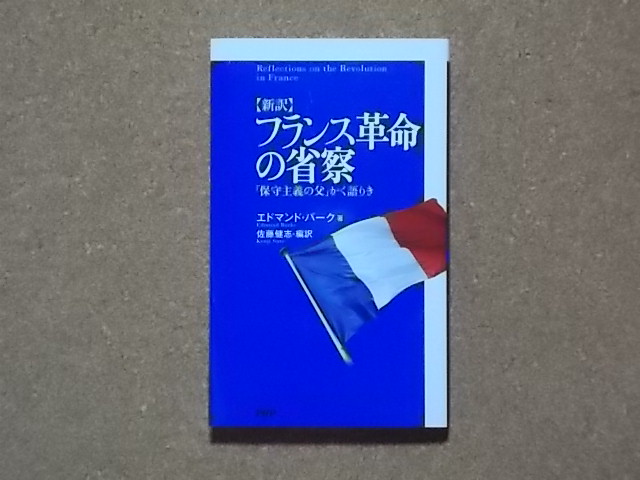
目次
プロローグ『フランス革命の省察』から学ぶもの
革命一年後の所見表明 4 / 事の本質を見抜いたパーク 6 / 急進主義の4つの前提 9 / 名著として読み継がれたゆえん 11 / 事実を超えた真実の提示 14 / なぜ原著を再構成したか 16 / 人間観・社会観を問い直せ 20
第一章 フランス革命と名誉革命の違い
私は革命支持派ではない 36 / 自由なら何でも良いのか? 38 / フランス革命は手本にならぬ 41 / プライス牧師に物申す 43 / 最高機関にも道義的制約がある 46 / 名誉革命に見る保守の真髄 48 / 革命精神は「インチキ商品」だ 51 / 仁義なきデタラメ論争を排す 53
第二章 過去を全否定してはいけない
ジェームズ王退位の真相 58 / 気軽に革命を語るべからず 59 / 自由や権利は古来のもの 62 / 国家には保守と継承の精神が必要 65 / フランスに良い点はないのか? 68 / この革命は愚挙である 70 / 国民議会に潜む問題 73
第三章 人間はどこまで平等か
平民代表の正体見たり 78 / 聖職者・貴族代表にも問題あり 80 / 昔は革命家さえ偉大だった 83 / 社会を狂わす平等主義 86 / 革命派は国をバラバラにした 88 / 「人権」は爆弾テロに等しい 90 / 自由も慣習の枠内にある 93 / 政治は理屈を超えたもの 95
第四章 革命派の暴挙を批判する
無謀で過激な「ぶち壊し屋」たち 100 / 茶番を続ける国民議会 103 / 国王一家に加えられた蛮行 105 / 騎士道の誇りは失われた 108 / 伝統無き社会は機能しない 110 / 人間の自然な感悄に学べ 114 / フランス革命を芝居にたとえると 116
第五章 教会は大事にすべきだ
過去を受け継ぐイギリス人 120 / 固定観念は価値あるもの 122 / 自由な社会ほど宗教が必要 125 / 安易に秩序を否定してはならぬ 128 / 教会資産を保障すべき理由 131 / 資産没収は暴君のやり口 134 / 国家的信用をめぐる二枚舌 136
第六章 フランスに革命は不要だった
金融勢力と知識人の結託 142 / キリスト教へのカルト的攻撃 144 / 前例なき野蛮な略奪 146 / 国家の負債は簡単になくせた 149 / 新紙幣発行と土地の丸投げ 151 / 王政批判は独裁を正当化しない 154 / 弊害は修正不能だったのか? 156 / 革命で貧窮は深刻化した 158
第七章 貴族と聖職者を擁護する
フランスの貴族は立派だった 164 / 名誉や美徳を嫌う革命派 166 / 聖職者への迫害も不当である 169 / キリスト教廃止の下準備 172 / 正しい寛容の精神を知れ 175 / 所有権の否定は社会正義の否定 177 / 正義なきところに英知なし 181
第八章 改革はゆっくりやるほうが良い
修道院を活用できぬ知恵のなさ 186 / 国民議会は正当性を欠いている 189 / 空理空論と現実逃避 192 / すべてを変えるのは無能の証拠 196 / 賢い政治のあり方とは 199 / 革命派のお手並み拝見 203
第九章 メチャクチャな新体制
基本的人権に資格制限がある! 208 / 金持ちへの逆差別 211 / フランスはまとまりをなくした 214 / 平等志向は独裁への道 217 / 有権者を代表しない国民議会 220 / 新紙幣アッシニアはバクチ専用 223 / 地方は没落、得するのは都市のみ 226 / パリの支配はいつまで続く 229
第十章 社会秩序が根底から崩れる
王は国民議会の下僕である 234 / 活力なき行政パシリ集団 236 / 外国勢力の暗躍は必至だ 240 / 失われた司法府の独立性 243 / 判事たちは独裁に奉仕する 246 / 軍の規律が乱れだした 249 / 宴会で兵士をなだめる革命派 252 / デュ・パン大臣の展望と懸念 255 / 自治体と軍の危険な結びつき 257
第十一章 武力支配と財政破綻
国民議会に軍は抑えられない 262 / もはや誰もが反乱を起こす 264 / 農民は革命派の論法につけ込んだ 268 / 武力による支配の限界 271 / 財政健全化は国家の根本課題 274 / 歳入は一年間で激減した 277 / 塩の専売、かく崩壊す 279 / 「愛国」税制の浅ましさ 281 / 支出の効率化も達成されず 284 / いまのフランスに信用などない 286
終章 フランス革命が残した教訓
土地没収の収支は赤字だった! 290 / 革命派はツケを払えるか 294 / 暴落一途のアッシニア紙幣 296 / 山師の猿真似がいいところ 298 / 窮乏したパリが各地を搾取する 301 / 秩序なくして繁栄なし 304 / 「自由な政府」をつくる難しさ 307 / 革命による改善は表面的だ 310 / われらの国体を尊重しよう 312 / 自由と秩序のバランスを求めて 315
はじめに
革命一年後の所見表明
本書の原著『フランス革命の省察(Reflections on the Revolution in France)』は、いまから221年前、1790年11月1日にロンドンで刊行された。著者のエドマンド・バークはアイルランド生まれの政治家で、文人としても知られた人物である。
フランス革命が勃発したのは1789年7月なので、原著が刊行された時点で1年3ヵ月あまりが経過している。ただし国王ルイ16世がギロチンにかけられたのは、刊行から2年以上たった1793年1月のことであり、王妃マリー・アントワネットの首が落ちたのは、さらに9ヵ月後、同年10月のことであった。
革命そのものは、原著刊行のじつに9年後、1799年11月になって終結する。これはナポレオンの政権奪取によるものだが、動乱がほんとうに治まるには、ロシア遠征に敗れたあと、ナポレオンが最終的に没落する1815年まで待たねばならない。
『フランス革命の省察』が扱ったのは、革命の初期段階のみだったのである。なおエドマンド・バークは1797年7月に死去しており、ナポレオンの栄枯盛衰はもとより、革命の終結すら見ることはなかった。
普通に考えれば、これは同書がフランス革命の全体像をとらえていないことを意味しよう。しかもオックスフォード大学の近代史専門家レスリー・ミッチェルが、同大学出版会より刊行された『フランス革命の省察』に付した解説で述べるところによれば、この本は当時、ペストセラーになったにもかかわらず、必ずしも高い評価を得てはいない。
バークはフランス革命のあり方を激烈に批判しているが、彼は同国の政治に詳しいほうではなく、革命下のパリを訪ねたわけでもないのだ。執筆にあたっては、革命に関する資料を(フランス国内で出回った文書も含めて)丹念に集めたようだが、それでも同書には誇張や偏向と受け取られても仕方のない記述はもとより、事実誤認の箇所まで見受けられる。
フランス革命がヨーロッパ中の関心を集めていたこともあって、これらの点はすぐに指摘された。あまつさえバークは、フランス革命に先行する形で生じたアメリカ独立革命(1776年)については、宗主国イギリスの政治家であるにもかかわらず、支持する立場を取っていたのである。
当時の有力政治家による『フランス革命の省察』評も、ミッチェルはいくつか紹介している。まずはアメリカ独立宣言の大部分を起草し、第3代の大統領にも選ばれたトマス・ジェファーソン。
「フランスでの革命など、バーク氏の豹変ぶりに比べれば驚くに足らぬ」
イギリス首相で、革命の過激化を警戒しつつも、長年のライバルだったフランスで王政が崩壊したことを喜んでいたウィリアム・ピット。
「この罵倒は芸術的だ。感服させられる点は多いが、賛成できる点は何もない」
やはりイギリスの政治家で、バークと個人的にも親しかったチャールズ・フォックス(彼はフランス革命を支持していた)。
「どうにも趣味の悪い本だ」
バークはフランス革命にキレているのではなく、ほんとうにイカレているのではないかとする見解すら一部で出回った。1790年代のイギリスでは、誇張された過激な主張をすることを「バーキズム」と呼ぶのが流行ったそうである。直訳すれば「バーク主義」だが、今風の日本語なら、さしずめ「バークる」であろう。
事の本質を見抜いたバーク
ならば『フランス革命の省察』は、話題性だけを売り物としたキワモノ本にすぎまい。けれども同書には、別の驚くべき特徴もうかがわれる。この革命がいかなる顚末を迎えるかに関して、バークは的確に見通していたのだ。
すなわち彼は、フランスがどうにもならない混乱に陥ったあげく、軍人による独裁に行きつくだろうと言い切った。不正確な批判をしつつ、正しい結論にいち早く至る、かかる芸当はどのようにして可能になったのだろうか?
まず注目すべきは、バークが革命政府の行動をあげつらいつつも、その基本理念を批判することを真の狙いとしていた点であろう。『フランス革命の省察』が刊行されて約3ヵ月後の1791年1月下旬、同書を高く評価したフランス国民議会議員フランソワ・メノンヴィルにたいし、彼は長文の手紙を書き送っている。じつはメノンヴィル、本の内容には誤りがあるとも指摘したのだが、バークは「貴君が指摘された点、たしかにその通りかと思う」と認めたうえで、次のように述べた。
「今回の革命について所見を表明したのは、こんなふうに社会を変えるのが望ましいか、イギリス国民がきちんと判断する助けになればと願ってのことだった」
「建築にたとえるなら、現場で石がどのように積み上げられているかを観察するより、設計者がいかなる図面を引いたかを知るほうが重要だと考えた。バカげた理念を、行き当たりばったりの実践でどうにか埋め合わせようとする過程について、いちいち追いかけて何になろう。だいたいキリがない。事態は日を追って収拾がつかなくなっている以上、革命政府は唖然とするようなトンデモ政策を次々と打ちださざるをえないのだ。それらをまともに論じる意味はない。革命の目標がまやかしであり、リーダーと称する連中もインチキにすぎないことが、日々証明されているだけの話ではないか」
「木を見て森を見ず」ではないものの、表面的なディテールにこだわりすぎると、事の本質は往々にしてわからなくなる。裏を返せば、バークは根源的なレベルにおいて、フランス革命のはらむ問題点を見抜いていたのだ。
バークが批判した革命の基本理念とは何か。一言で要約するなら、それは「正しい目標をめざすかぎり、社会の変化は抜本的であればあるほど良い」と見なす考え方と規定しうる。ここからは当然、「正しい目標をめざすかぎり、社会の変化は急速であればあるほど良い」という結論も導かれよう。
かくして成立するのが、いわゆる急進主義の理念にほかならない。フランス革命が真に重要なのは、「自由・平等・博愛」を謳ったことや、人権宣言を採択したことにあるのではなく、急進主義に基づく史上初の大規模な革命だったことにあるのだ。
急進主義の4つの前提
社会を急速かつ徹底的につくりかえようとする試みは、以後の「革命」の基本形となる。全体主義や社会主義はむろんのこと、明治維新をきっかけとしたわが国の近代化・欧米化や、敗戦後にわき起こった民主主義礼賛なども、急進主義の影響を抜きには考えられない。
いや、近年の「改革」志向や「政権交代」ブームとて、遠くフランス革命に通じている。2000年代前半、改革の旗手となった首相・小泉純一郎が「古い自民党をぶっ壊す」と宣言したことや、2009年、当の自民党を下野させることで首相となった鳩山由紀夫が、「博愛」ならぬ「友愛」という言葉を好んだことは、この点で象徴的と評しえよう。
しかるに「正しい目標をめざすかぎり、社会の変化は抜本的であればあるほど良く、また急速であればあるほど良い」という発想は、次の4つの前提のうえに成り立つ。
(1)人間は、社会のあり方を望ましくする方法論を適切に考案する理性、およびそれを確実に実現してゆく能力を持っている。
(2)社会を望ましくする方法論が2つ以上存在する場合、人間は個人的な利害関係や感情にとらわれることなく、どちらが良いかを冷静に判断できる。
(3)右2つの前提は、社会全体で成立している。言い換えれば、みずからのあり方を望ましくしようとすることにかけて、社会は首尾一貫した単一の意志を持っていると見なして構わない。
(4)社会のあり方を変えることに伴うコストや副作用は、変化のスピードを上げたからといって顕著に増大することはない。
まさしく「善は急げ」だが、問題はこれらの前提が、どれ1つとして妥当とは言いがたいことである。
ここで引き合いに出されるべきは、フランス革命が勃発する直前に刊行された小冊子『第三身分とは何か』であろう。「第三身分」とは平民のことであり、「第一身分」の聖職者、「第二身分」の貴族に対比してこう呼ばれる。
著者のエマニュエル・シエイエスは、平民の生まれから聖職者となった人物ながら、第一、第二身分が(平民を抑圧することで)不当に特権を享受していると批判、万人の平等を訴えた。すなわち同書は革命に向けたマニフェストとも呼ぶべきものにしろ、シエイエスでさえ先に挙げた4つの前提を全面的には肯定できていない。
彼は冒頭、望ましい社会のあり方を構想する人間を「哲学者」、その構想を実践する人間を「為政者」と定めた。哲学者の責務は、自由で純粋な思考を駆使して真理を極限まで追求し、反発や無理解を恐れずにそれを広める ―― 要するに知的な急進主義に徹することとされる。ところが為政者の責務は、正しい方向性から逸脱しないよう注意しつつ、一歩一歩着実に進んでゆく ―― つまり「急がば回れ」の姿勢を取ることとされるのだ。
しかもシエイエスは、フランス国民全体が、個々の細かい利害を超えた共同の意志を持っているとしたものの、これは聖職者と貴族が平民を抑圧しているとする主張と噛み合わない。このため彼は、人口の大多数を占める平民こそ「国民」そのものだと述べ、聖職者と貴族を(進んで平民の味方に回ろうとする者を除いて)「非国民」のごとく扱うことにより、やっと議論の整合性を保つ始末であった。
名著として読み継がれたゆえん
前提が誤っているのだから、急進主義は遅かれ早かれ挫折する運命を背負っていると評しても過言ではない。なるほど急進主義者の掲げる目標には、肯定すべき点が含まれていること多いし、改革を実践してゆく過程では、相応の望ましい成果もあがる。
けれども時が経てば経つほど、物事を急激に変えつづけようとすることのコストや副作用がふくれ上がり、たいてい最後には「労多くして功少なし」か、下手をすれば「骨折り損のくたびれ儲け」に陥ってしまう。また急進主義は、人間の理性や能力、あるいは社会的協調性について過大評価する傾向が強いものの、これは「実際にはできないことを『できる』と言い張る」ことに等しく、偽善や欺瞞につながりやすい。
『フランス革命の省察』が名著として読み継がれたゆえんも、かかる問題点をずばり指摘したことにある。エドマンド・バークは、2世紀以上前にこう言い切った。
「国家を構築したり、そのシステムを刷新・改革したりする技術は、いわば実験科学であり、『理論上はうまくいくはずだから大丈夫』という類のものではない。現場の経験をちょっと積んだくらいでもダメである。
政策の真の当否は、やってみればすぐにわかるとはかぎらない。最初のうちは『百害あって一利なし』としか思えないものが、長期的にはじつに有益な結果をもたらすこともある。当初の段階における弊害こそ、のちの成功の原点だったということさえありうる。
これとは逆の事態も起こる。綿密に考案され、当初はちゃんと成果もあかっていた計画が、目も当てられない悲惨な失敗に終わる例は珍しくない。見過ごしてしまいそうなくらいに小さく、どうでもいいと片付けていた事柄が、往々にして国の盛衰を左右しかねない要因に化けたりするのだ。
政治の技術とは、かように理屈ではどうにもならぬものであり、しかも国の存立と繁栄にかかわっている以上、経験はいくらあっても足りない。もっとも賢明で鋭敏な人間が、生涯にわたって経験を積んだとしても足りないのである。
だとすれば、長年にわたって機能してきた社会システムを廃止するとか、うまくいく保証のない新しいシステムを導入・構築するとかいう場合は、『石橋を叩いて渡らない』を信条としなければならない」(第三章)
パークの主張が、フランス革命のみならず、全体主義や社会主義、あるいはわが国の「改革」「政権交代」ブームヘの警鐘ともなっているのは疑いえまい。「急進主義に基づく徹底した社会改革」をめざした点で、フランス革命はその後の「革命」全般のひな形となったわけだが、同革命を根源的なレベルで批判したことにより、『フランス革命の省察』もまた、急進主義の問題点をめぐる古典的分析となったのだった。
事実を超えた真実の提示
興味深いのは、同書の誇張や偏向、あるいは事実誤認が、ここでむしろプラスに働いたことであろう。バークはフランス革命のはらむ本質的な問題を把握したうえで、当の問題点がことさら際立つようにそのあり方を記述した。
結果として、彼の描き出した革命の姿は、特定の歴史的事件をめぐる記述でありながら、「急進主義に徹したあげく収拾のつかなくなった社会改革」全般の戯画となっている。しかもそこには、人間の平等性、あるいは民主主義の価値といった、現在ではしばしば自明と見なされる事柄についての疑問も提起されているのだ。
『フランス革命の省察』は、事実関係において不正確であるからこそ、おそらくはバーク本人の意図をも超える形で普遍性を獲得したのである。同書が発表当時に不評だったことと、のちに高い評価を確立したことは、こう考えれば矛盾しない。
革命がリアルタイムで進行している時点の読者には、事実関係の不正確さや、激越なレトリックが不満のタネとなったのにたいし、革命が過去の出来事となり、距離を置いて眺められるようになった後世の読者は、それら「脚色」によって得られた普遍性に感服したのだ。これが「当初の段階における弊害こそ、のちの成功の原点だったということさえありうる」実例となっているのは、いささかできすぎた話ではないだろうか。
先に「戯画」という言葉を用いたが、「本質的な特徴をとらえ、それが際立つように表現を誇張する」のは、じつは風刺の方法論にほかならない。新聞や雑誌に掲載される有名人の似顔絵は、どれもこのような手法によって描かれている。
バークの省察も、フランス革命についての論評というより「同革命をモチーフとした、急進主義的改革をめぐる風刺文学」と見なしたほうが、その真価を味わうことができよう。本来これは、ジョナサン・スウィフトの『ガリバー旅行記』や、ジョージ・オーウェルの『動物農場』などと比較されるべきものなのだ。
ただし『ガリバー旅行記』や『動物農場』の場合、いかに政治的寓意があろうと、虚構の物語なのは間違えようがない。これにたいし『フランス革命の省察』は、現実の大事件を扱い、かつ論考という形式を取っているだけに、風刺文学的な本質が見えづらかった次第である。
刊行当時のイギリス首相ウィリアム・ピットが「この罵倒は芸術的だ」と語ったのは、こう考えるとき、なかなか意味深長となる。事実をありのまま提示するのではなく、事実を超えた真実を提示することこそ、芸術の果たすべき役割なのだ。ならば罵倒も、芸術の域にまで達した際には、真実に通じて不思議はあるまい。
なぜ原著を再構成したか
本書は『フランス革命の省察』の日本語訳だが、原著の全訳ではなく、「急進主義的改革への風刺的批判」という特徴が際立つ部分を中心に再構成したものである。なぜこうしたのか、理由を述べておきたい。
すでに紹介した通り、バークがフランス革命にたいする見解を発表したのは「こんなふうに社会を変えるのが望ましいか、イギリス国民がきちんと判断する助けになれば」という思いからであった。当時のイギリスには、フランス革命を称賛し、それに倣おうとする急進的な政治勢力が存在したのだ。
はたせるかな、原著の正式な題名は『フランスで生じた革命、およびそれに呼応せんとするロンドン諸党派の動向をめぐる省察』となっている。
「隣の家が火事になったら、こちらも消防の準備をしておくべきではないか。取り越し苦労を笑われるほうが、用心を怠ったあげく何もかもパアにするよりずっと良い」というのが、これについてのバークのコメントながら、『フランス革命の省察』には、古典的名著としての普遍性と、「1790年代初頭のイギリス人読者」を強く意識した時事性とが同居している。もとより時事性も風刺の重要な要素に違いないにしろ、われわれは21世紀に生きている以上、これは原著に時代遅れの部分もあるというに等しい。
たとえばバークは、リチャード・プライス牧師なる人物が行ったフランス革命礼賛の説教について、原著の前半部分で繰り返し取り上げて批判した。この説教、17世紀のイギリスで生じた「名誉革命」を、フランス革命と関連づける形で扱っている。
ゆえにバークの省察も、じつは名誉革命に関する議論から始まるのだが、プライスはイギリス人を革命へと駆り立てるどころか、原著が刊行された直後に世を去ってしまう。フランス革命政府の行動を詳述したくだりとて、誇張や偏向、事実誤認などの点を抜きにしても、当の行動自体がどんどん変わっていった。
どちらに関しても、全面的に割愛することはできないものの、逐一紹介する価値は薄い。そのうえ原著は、決して読みやすい構成になっていないのだ。というのもバークは、もともとこれを手紙として書いたのである。
フランス革命が勃発して数ヵ月が過ぎた1789年秋、バークは知り合いの青年シャルル・ジャン・フランソワ・ドポンより、革命にたいする見解を聞かせてほしいという手紙を受け取った。パリ在住のドポンは国民議会のメンバーでもあり、明らかに激励の言葉を期待していたのだが、革命の過激化(および、それがイギリスに飛び火する危険性)を懸念していたバークは、えんえんたる批判の返事を書きつらねる。さらに彼は翌1790年の早春、この手紙の公刊を決意するに至った。
こうして同年11月、『フランス革命の省察』は出版されるものの、知り合いに宛てた手紙として書かれたこともあって、同書には「綿密に構成された論考」というより、「毒舌に満ちた随筆」と形容されるべき側面も見られる。おまけにこの省察、全訳すれば上下巻にもなるほど大部なものにもかかわらず、章分けなどはまったくなされていない。
版によっては、全体が二部に分けられ、随所に見出しが添えられている場合もあるけれども、これは後世の編集者が読みやすさを考えて挿入したものなのだ。バーク自身、次のように断わっている。
「この省察は手紙という形式で書きはじめられた。事実、当初は純然たる私信にすぎなかったのである。ゆえに分量が長くなり、議論がふくらんだあとも、手紙としての性格を消し去ることはできなかった。もっと別の形式を取ったほうが、論点を手際よく展開できたかもしれない、私はそう自覚している」
本書における再構成は、そのような「もっと別の形式」を探求する試みと理解していただきたい。『フランス革命の省察』で提起された論点には、1790年の刊行当時より、現在のほうがいっそうタイムリーと評しうるものが多々見られる。したがって、それらを極力読みやすい形で提示することには大きな意義があると思われるのだ。
フランス革命の勃発した18世紀末は、世の中の変化するスピードが、産業革命によって一気に加速した時代であった。急進主義による抜本的な社会改革という発想も、このような背景を踏まえて生まれたのだが、以後も変化のスピードはどんどん速まっている。
しかも現在では、経済をはじめとするさまざまな分野でグローバル化が進んだため、局地的なものとして始まった変化が、すぐさま世界全体に波及するようになった。2008年に生じた金融危機はもとより、テロや大量破壊兵器の拡散、はたまた環境破壊などは、その代表的な例であろう。
これは「急進主義的な改革を行いたい」という誘惑が、国内的にも国際的にも高まることを意味する。ところが当の改革が(ほぼ確実に)挫折を運命づけられていることは、過去200年間に行われた急進主義実践の試み、わけても20世紀における社会主義の試みが失敗に終わったことに示される通りなのだ。
人間観・社会観を問い直せ
「物事を抜本的に変えてゆかねばならない」という思いと、「物事を抜本的に変えようとしてもうまくいかない」という思いに引き裂かれ、みずからの立ち位置を決めかねている ―― それが21世紀におけるわれわれの実情ではないだろうか。「構造改革」にたいする批判が高まる一方で、新たな抜本的改革として「政権交代」がもてはやされ、果てはそれにも失望が深まるという、近年の日本に見られる風潮も、かかるジレンマの表れと解しうる。
けれども「改革への不満を解消するため、さらなる改革に走る」というのは、いかんせん堂々めぐりにすぎず、悪くすれば「どんどん収拾のつかなくなってゆく事態に何とか対処しようと、トンデモ政策を乱発する」ことにもなりかねまい。そんな状況のもとで、社会をできるだけ望ましい状態に保つにはどうすべきか。
これにたいする答が簡単に出るようなら、もとより誰も苦労はしない。ただしすでに指摘した通り、急進主義の根底には、人間の理性や能力、あるいは社会的協調性を高く評価する価値観が潜む。ならば「急激に変化してゆく世の中に、急進主義に陥ることなく対応する方法」を見出すには、われわれの人間観・社会観を問い直すことがまずもって必要になろう。
バークが語った通り、ここでは個々の政策を云々することよりも、根本の理念を問い直すことが肝心なのだ。そして『フランス革命の省察』は、急進主義的な改革の問題点を、まさしく人間観・社会観のレベルで提起している。たとえばこんな具合に、である。
「フランス国民議会が改革と称して、既存の制度の廃止やら全面的破壊やらにうつつを抜かしているのも、困難に直面できないせいで現実逃避を図っているにすぎない。物事をぶち壊したり、台なしにしたりするには、手腕ではなく腕力があれば十分だ。そんなことに議会はいらぬ、暴徒にやらせておけばよい。バカであろうと粗野であろうと、何も困りはしないのである」
「物事をこれまでとは正反対にするというのも、安直さにかけては、すべてをぶち壊すのといい勝負である。前例のないことを試すのは、じつは気楽なのだ。うまくいっているかどうかを計る基準がないのだから、問題点を指摘されたところで『これはこういうものなんだ』と開き直ればすむではないか。熱い思いだの、眉唾ものの希望だのを並べ立てて、『とにかく一度やらせてみよう』という雰囲気さえつくることができたら、あとは事実上、誰にも邪魔されることなく、やりたい放題やれることになる」(第八章)
しかり、急進的改革とは、ただやるだけならバカでもできる。急進的改革を成功させるとなれば別だが、改革が切実に必要とされていればいるほど、「はたしてうまくいっているのか」をめぐる判断は狂いやすい。理由は簡単、「うまくいってほしい」という願望が人々の目を曇らせるからである。
社会を望ましくするための方法論を、適切に考案したり、実行したりすることは可能か? そこまでの賢明さは人間に期待しうるものなのか?
バークの議論の根底には、このような懐疑が潜む。彼の政治的な姿勢は「保守主義」と呼ばれるが、「人間の限界や欠点を直視したうえで、なお社会のあり方をできるだけ望ましくしようとする姿勢」と定義したほうが的確であろう。
「おのれ自身を知れ」をモットーにしたのはソクラテスであり、これにたいして「おのれ自身を知ったら最後、私は尻尾を巻いて逃げだす」と応じたのはゲーテである。ならばエドマンド・バークは「おのれ自身を知り、かつ逃げださずにすむにはどうしたら良いか」を追求したと言えよう。そしてフランス革命当時に比べ、21世紀のわれわれのほうが、人間のあり方を直視できているとはかぎらないのである。
本書の訳出に関しては、レスリー・ミッチェルの解説と注釈が付されたオックスフォード大学出版会版(1993年)を底本とし、スタンフォード大学出版会より刊行された注解版(J・C・D・クラーク編、2001年)、そして岩波文庫より刊行された全訳日本語版(中野好之訳『フランス革命についての省察』2000年)を参照した。
とくに訳注に関しては、これらの版の注釈に負う点が多い。各版の編者、および訳者に謝意を表したい。
佐藤健志
昔は革命家さえ偉大だった P83
かつての革命は違っていた。それらの首謀者は、国家の平安を乱し、従来の秩序をくつがえそうとはしたものの、国の威厳を高めることをめざした。かかる大義こそ、彼らの野心を正当化する根拠だったのだ。
こういった革命家には長期的なビジョンがあった。みずから祖国を統治しようとこそすれ、祖国を台なしにする意図などはなかった。また彼らは、政治と軍事に関する偉大な才覚を持っていた。人々から恐れられたかもしれないにしろ、それぞれの時代を代表する人物であったことも疑う余地はない。
クロムウェル(訳注:17世紀イギリスで起きたピューリタン革命の主導者)は、こんな昔ながらの大悪党だが、彼の縁者であり、詩人として名声を博した人物から詩を捧げられている。ここにはクロムウェルが掲げた理想と、革命の成就によって(かなりの程度まで)達成された業績が示されていよう。
あなたが栄光の座に登りつめるほど、祖国もまた輝きを増す。
あなたが国をつくりかえるかぎり、どんな病も生じはしない。
それはあたかも日の出にあたり、卑しい夜の光がかき消され、
世界すべての光景が音もなく一変するときのごとし。
国の秩序を乱したのは事実ながら、クロムウェルのような人物は「権力を不当に奪った」というより「生まれながらのリーダーとして社会に尽くそうとした」というのが正しい。彼らの勝利は、ライバルをしのぐ実力を持っていたがためのものだった。彼らの引き起こした動乱は、破壊の天使のように国土をおおったかもしれない。だが同時に、彼らは祖国に活力とエネルギーをもたらしてもいたのだ。
断わっておけば、これらの人物が美徳を持っていたからといって、彼らの悪事が決して帳消しになるわけではない。しかし当の美徳のおかげで、革命の悪影響がかなり緩和されたのも事実である。
殺戮が続く中でも、国の魂が失われることはなかった。威厳へのこだわり、高貴なプライド、栄光を尊ぶ感覚、これらは滅び去るどころか、逆にいっそう燃え上がった。さまざまな国家機構も、ガタガタになったとはいえ存続していたし、名誉と美徳の持ち主は恩賞や地位によって報いられた。
ひきかえ、いまのフランスにおける混乱は、社会の持つ根源的な生命力を直撃し、麻痺状態に追いやっている。尊敬されてしかるべき立場にいた者は、ことごとく不名誉にも卑しめられ、恥辱と怒りのほかは何も感じられなくなっているありさま。
フランス貴族の次の世代は、陰謀家やピエロ、相場師、高利貸し、それにユダヤ人といった連中を友とせねばならない。いや、師として仰がねばならないことすらあろう。ならばこの手の連中に似てしまうのは理の当然ではないか。
聞きたまえ。優れた者の地位を引き下げることで平等が達成されることはないのだ。どんな社会であろうと、多種多様な人間によって構成されているかぎり、支配層が現れるのは避けられない。
「引き下げ平等主義」にこだわる者は、ゆえに物事の自然な秩序を狂わせてしまう。建物の場合と同様、土台として下に置かれねばならないものを頂上に据えるなら、構造は不安定になってしまうのだ。
社会を狂わす平等主義 P86
フランスの大法官は三部会の開会にあたって、あらゆる職業は名誉なもの、と麗々しく宣言した。もしこれが「まっとうなものであるかぎり、どんな職業も恥ずかしくはない」という意味なら、彼の発言はもっともであろう。
しかしあらゆるものに名誉を与えるとなっては、もう少し突っ込んだ意味合いが生じてくる。美容師や獣脂ロウソク職人といった仕事は、誰がやろうと名誉なものではない(訳注:獣詣でつくられるロウソクは、煙が出るうえ、においも良くないので安物とされた)。もっと隷属的な仕事については言わずもがなである。
そういった仕事に就いているからといって、国家から迫害を受けるいわれはない。だがこんな連中に(個人としてであれ、集団としてであれ)政治を任せたら最後、国家はたいへんなことになる。平等主義に徹することで、フランス人は世間の偏見をくつがえしているつもりかもしれないが、じつは非常識に振る舞っているだけと言わねばなるまい。
むろん何にでも例外はある。けれども健全な一般論は、例外の存在を前提として成り立っているのだ。「卑しいとされる仕事に就く者に立派な人間は一人もいないのか」とか、「そう
いった人間を絶対に抜擢してはいけないのか」などと主張するのは、反論のための反論しているか、愚鈍さを装っているかのどちらかであろう。
権力や権威、それに名声は、高貴な生まれの者にのみ与えられるべきだと言うのではない。そんなつもりは毛頭ない。美徳と英知をすでに発揮しているか、発揮するだろうと期待される者なら、誰であれ政治にかかわる資格を持つ。
かかる資格さえあれば、身分、境遇、職業のいかんを問わず、地位と名誉が保証されてしかるべきなのだ。民間人であれ、軍人、あるいは聖職者であれ、国家に奉仕し、その誉れとなる才覚や美徳を持っている者を理不尽に冷遇するようでは、国の将来も知れたものである。
反対に、まともな教育を受けていない者、粗暴で視野の狭い考え方の持ち主、あるいは金儲けにのみ血道をあげてきた者を、国家の指導層として歓迎するようでも、やはり国の将来は知れたものであろう。出世のチャンスは広く与えられるべきだが、万人が見境なく出世できるというのはおかしい。
低い生まれの者が、栄誉と権力の座に登りつめるのは、あまり容易であるべきではないし、起きて当たり前のことでもない。稀有な才覚は、何らかの試練をくぐり抜けることで、みずからが稀有であると立証すべきなのだ。名誉の殿堂には高貴な者のみが入れる。そして高貴と呼ぶに値する美徳は、多大な困難や苦闘の果てに身につくものなのである。
「人権」は爆弾テロに等しい P90
名誉革命協会のような連中は、何かを破壊しないことには気がすまない。そうしないことには、自分たちの存在が無意味に思えて仕方ないのだ。こんな考えに取り憑かれた者に向かって、先祖伝来の慣習とか、祖国の基本法とか、憲法の枠組みとかいった事柄を列挙し、これらは長年存続してきたばかりでなく、イギリスの国家と国民をたえず豊かにしてきたのだから、その価値は立証ずみなのだと説いてもムダである。
連中の手にかかると、経験に頼るのは学がない証拠になってしまう。しかも彼らは、古来の伝統や、過去の議会による決議、憲章、法律のことごとくを、一気に吹き飛ばす爆弾まで持っている。
この爆弾は「人権」と呼ばれる。長年の慣習に基づく権利や取り決めなど、人権の前にはすべて無効となる。人権は加減を知らず、妥協を受けつけない。人権の名のもとになされる要求を少しでも拒んだら、インチキで不正だということにされてしまうのだ。
人権が出てきた日には、どれだけ長く続いてきた政府であれ、いかに公正で寛大な統治を行ってきた政府であれ、安心してはいられない。人権を旗印にする者は、つねに政府に抵抗する。それも圧政に文句をつけるのではない。統治能力の有無、さらには政府を名乗る資格の有無を問題にしてくるのである。
私は「人間の権利」という概念を否定したいのではない。人々が自分たちの真の権利を行使するにあたって、邪魔立てする気も(そんな力が私にあるとしてだが)毛頭ない。人権主義者の振る舞いは、われわれの真の権利を完全に破壊するものにほかならず、彼らのデタラメを批判することと、権利を守ることは矛盾しないのだ。
文明社会は人間に利益をもたらすためにつくられる。社会が成立していることによって得られる利益は、すなわち人間の権利となる。善の達成こそ社会の意義であり、法はそのためのルールにほかならない。
人間はこのルールにしたがって生きる権利を持つ。また公正に扱われる権利を持つ。親の財産を受け継ぐ権利があり、子供を養育し向上させる権利がある。生きている間は自己を高めるべく学ぶ権利があり、死にあたっては慰めを得る権利がある。
そして人間は、社会が全体としてもたらす恩恵の中から、正当な分け前を受け取る権利を持つ。「社会の一員として恩恵をもたらすのに貢献し、当の恩恵の分け前をもらう」点では、誰もが平等と言える。
ただしこれは、誰であれ同じだけの分け前をもらえることを意味しない。株でいえば、5シリングの小銭しか出資しなかった者も、500ポンドの大金を出資した者も、配当を得る権利がある点では同じである。だとしても、同額の配当をもらう権利があることにはなるまい。
いわんや国政に関して、各人がどれだけの権限、権威、あるいは発言力を持つべきかとなると、これは「人間の基本的権利」にかかわる事柄ではなく、「文明化された社会人」にかかわる事柄である。ならば、たんなる人間と「文明化された社会人」の相違は何か? それは社会的慣習を受け入れたかどうかなのだ。
自由も慣習の枠内にある P93
文明社会は慣習を踏まえて成り立つとすれば、慣習こそがもっとも基本的な法となる。立法、司法、行政のあらゆる権力はここから生まれる。いかなる権力も、慣習を離れては存在しえない。また社会的慣習にしたがって生きている者が、当の慣習のもとでは想定されてもいない権利や、慣習自体を乱すような権利を主張することもできない。
人間が文明社会をつくるに至った動機の一つに、「正義とは客観的なものでなければならない」というものがある。「自分の行為を自分で正しいと見なすだけでは、その正しさを立証したことにならない」 ―― これは文明社会の基本原則と言えよう。
しかし自分が正しいと思うことを自由にやるのは、自然状態の人間にとり、もっとも基本的な権利なのだ。この権利を放棄し、好き勝手な行動を慎むことで、人間は社会に加わる。文明社会に帰属しながら、自然状態も享受する「いいとこ取り」はできない。
法のもとで公正な扱いを受けたければ、自分の利害に関して、何が公正かを勝手に決める権利を捨てなければならないのである。社会の正当性を信じ、おのれの自由をいったん返上することにより、人間は慣習の枠内における自由を確保する。
政府は「人間の自然な権利」、つまり自然権のうえにつくられるものではない。自然権は政府とはまったく無関係に存在するものだし、抽象概念としてはきわめてわかりやすい。しかし、だからこそ現実には使いものにならないのだ。
権利が「自然」なものだとすれば、何もかも要求して当たり前という話になろう。たしかに政府は「人間にとって必要でありながら、なかなか手に入らないもの」を提供すべくつくられている。これらを政府から与えられるのは、人間の権利にほかならない。
けれども「自分の欲求に十分な歯止めをかけること」も、人間にとって必要でありながら、文明社会の存在なしには実現されないことの一つである。社会は個人にたいし、自己を抑制することを求める。のみならず集団で行動する際にも、みずからの意志や欲求を制御し、野放図に暴走しないことを求める。
これには何らかの外圧が欠かせない。自分の意志や欲求を、自分の意志や欲求によって抑え込めるはずがないのだ。その意味では社会によって課せられる制約も、社会によって与えられる自由同様、人間の権利と見なしうる。
ただし自由であれ制約であれ、具体的にどのようなものとなるかは、時代と状況によって異なるし、いくらでも細かく変わりうる。ゆえにこれらを、抽象的な原則によって決めることはできない。まして抽象的な原則から出発する形で、自由や制約について論じるのはおよそナンセンスである。
政治は理屈を超えたもの P95
各人が好き勝手に振る舞うのを禁じ、制約を設けることから政府が生まれるとすれば、政治の本質は権利をめぐるサジ加減の見きわめにありということになる。だからこそ、国家をどう構築し、権力をどう配分するかを決めるには、微妙で複雑な手腕が要求される。
政治にたずさわる者は、人間の本質は何か、人間は何を欲するかについて、深い知識を持たねばならない。さらに政策を実現するうえで、何かプラスで何かマイナスかもわきまえねばならない。
「人間は食べ物を得る権利がある」とか「人間は医療を受ける権利がある」とか、抽象的に論じて何になる! 重要なのは、食糧や医療を実際に提供することなのだ。ここでは哲学の教授達ではなく、農民や医師の手を借りたほうが良いのは明らかだろう。
国家を構築したり、そのシステムを刷新・改革したりする技術は、いわば実験科学であり、「理論上はうまくいくはずだから大丈夫」という類のものではない。現場の経験をちょっと積んだくらいでもダメである。
政策の真の当否は、やってみればすぐにわかるとはかぎらない。最初のうちは「百害あって一利なし」としか思えないものが、長期的にはじつに有益な結果をもたらすこともある。当初の段階における弊害こそ、のちの成功の原点だったということさえありうる。
これとは逆の事態も起こる。綿密に考案され、当初はちゃんと成果もあがっていた計画が、目も当てられない悲惨な失敗に終わる例は珍しくない。見過ごしてしまいそうなくらいに小さく、どうでもいいと片付けていた事柄が、往々にして国の盛衰を左右しかねない要因に化けたりするのだ。
政治の技術とは、かように理屈ではどうにもならぬものであり、しかも国の存立と繁栄にかかわっている以上、経験はいくらあっても足りない。もっとも賢明で鋭敏な人間が、生涯にわたって経験を積んだとしても足りないのである。
だとすれば、長年にわたって機能してきた社会システムを廃止するとか、うまくいく保証のない新しいシステムを導入・構築するとかいう場合は、「石橋を叩いて渡らない」を信条としなければならない。
人間の本性は複雑微妙であり、したがって政治が達成すべき目標もきわめて入り組んでいる。権力の構造を単純化することは、人間の本性に見合っておらず、社会のあり方としても望ましくない。
政治体制を新しく構築するにあたり、物事を単純明快にすることをめざしたと自慢する連中は、政治の何たるかを少しもわかっていないか、でなければおよそ怠慢なのだ。単純な政府とは、控えめに言っても、機能不全を運命づけられた代物にすぎない。
社会を特定の角度からしか眺めようとしない者にとっては、そんな政府のほうがずっと魅力的に映るだろう。達成すべき目標がただ一つしかないのであれば、たしかに政治体制は単純なほうが良い。
複雑な体制は、いくつものこみいった目標を満たすように構築されており、したがって個々の目標を達成する度合いにおいては劣る。だが社会が複雑なものである以上、「多くの目標が不完全に、かつ途切れ途切れに達成される」ほうが、「いくつかの目標は完璧に達成されたが、そのせいで残りの目標は放りっぱなしになったか、むしろ前より後退した」というよりマシなのである。
無謀で過激な「ぶち壊し屋」たち P100
ハッキリ言って、抵抗だの革命だのとしょっちゅう叫ぶ手合いは不愉快だ。この連中は、よほどの場合でなければ服用すべきでない劇薬を、毎日飲めと説いているに等しい。そんなことをすれば、社会全体の体質がひどく虚弱になってしまう。
世の中には、抵抗するにしても穏健にやればいい ―― つまり平和的・合法的な手段で抗議すれば十分という程度の問題も多い。ところが抵抗イコール過激なものと決めてかかっている者にかぎって、そのような場合は何の異議申し立てもしないのだ。戦争や革命をおっぱじめるか、でなければ無関心を決め込むかなのである。
「国はこうあるべし」という自己の理論に酔うあまり、現実の国家に良い点を見出そうとしない者は、ほんとうの意味では社会に関心など持っていない。善政を評価することもないし、悪政については心を痛めるどころか、革命の気運が高まると喜ぶ始末。
革命派にとっては、個々の人間であれ、政策であれ、はたまた政治的な原則であれ、よしあしを判断する基準は一つしかない。従来のシステムをぶち壊すのに役立つかどうかだ。だからこそ、暴力的で徹底した独裁を支持したかと思うと、今度は極端なまでの平等や自由を唱えたりすることができるのだろう。
かかる政治手法は、きわめて好ましくない副作用をもたらす。非常事態においては、ときに非情な振る舞いも必要となるが、世の中をつねに非常事態と見なしたがる革命派は、人間を冷酷なものにしてしまうのだ。
こういった連中は、人権をめぐる理屈をこねるのに忙しくて、人間のあり方そのものを見失っている。新たな英知を切り開くつもりで、じつは心を閉ざしただけ。われわれの胸中に宿っているはずの優しさや共感は、すっかり歪められる結果となる。
陰謀、虐殺、暗殺も、それで革命が成就されるなら安いものにすぎない。犠牲や流血沙汰を回避して改革を実現するとか、死体の山を築かずに自由を獲得するのは生ぬるいようなのだ。革命派は物事をとことん変えないことには納得しない。芝居でいえば、舞台装置の大転換による派手なスペクタクルを観たくて仕方ないのである。
プライス牧師(訳注:イギリスにおける革命支持派。フランスを見習おうという趣旨の説教を行った。プロローグ~第二章を参照)にとり、フランス革命はまさにそんなスペクタクルだった。説教のしめくくりで、彼は感極まってこう述べる。
「いまは何と偉大な時代であることか! この革命を目の当たりにできて満足だ。『神よ、もう死んでも悔いはありません。あなたのもたらす救いをしかと見届けました』 ―― ほとんどこう言いたくなる。英知は世に広まり、迷信と錯誤をくつがえした。人権はかつてなく理解されるに至り、自由を忘れかけていたかに思えた国々は、それを取り戻すべく立ち上がっている。
3000万もの人々が決然たる怒りに燃えて、隷従をはねのけ、圧倒的な声で自由を求めたのだ。民衆が勝利する中、国王は彼らの凱旋行進にしたがわざるをえなかった。専制君主は、かつて支配していた者たちの前に屈したのである」(訳注:国王が民衆の凱旋行進にしたがったとは、1789年10月、ベルサイユ宮殿にいたルイ16世とその家族が、数千人の民衆によってパリに連行されたことを指す。以後、国王一家は実質的な幽閉状態に置かれた)
まともな人間なら誰であれ、この「凱旋行進」にショックを受けたに違いない。これはフランスの勝利などと呼べる代物ではなかった。たぶんフランス人の多くも、今回のパリ連行を恥ずかしくも恐ろしいことだと受け止めたことだろう。
革命派の集会では、無謀で暴力的、かつ不誠実な議論ほど、ずばぬけて素晴らしいものと見なされるようだ。人間性や優しさは、無知と迷信の産物だとバカにされる。温情をもって人に接するのは、民衆への裏切りとして扱われる。
自由は完璧でなければならず、そのためには他人の財産に手をつけても良。暗殺、虐殺、没収が横行する中、彼らは未来社会の望ましい秩序とやらを思い描く。
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1583936b.847a7192.1583936c.2d77a722/?me_id=1213310&item_id=14377963&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F4534%2F9784569774534.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
