中国の戦争宣伝の内幕 ― 日中戦争の真実
「中国の戦争宣伝の内幕 ― 日中戦争の真実」の著者フレデリック・ヴィンセント・ウイリアムズは日中戦争前後の中国、満洲、日本を取材したアメリカ人ジャーナリストだそうです。原書は1938年11月に出版されたものだそうです。
この「日中戦争前後の中国、満洲、日本を取材したアメリカ人ジャーナリスト」が書いたというところに本書の真実味を感じます。
序文でも「私はこれを書くことにおいて手心は加えていない。私は誰をもバックにしてはいない。私は自由に率直に語った。我々がずうっと騙されているよりかは、真実を知った方がよいと考えたからである。」と書いています。
もっとも蒋介石に取り込まれたジャーナリストや宣教師なども手記や書物を残していますから、本人がそう言ったところでウィリアムズは日本の宣伝をしているんだという中国に寄り添った主張もできなくはない所であり、そういう立場の方に本書をお勧めする気はありません。
「南京事件の総括(田中正明著)や「南京事件 証拠写真を検証する(東中野修道・他 著)」で、蒋介石の国民党軍によるプロパガンダが盛んであったことが紹介されていますが、「当時の現地を知るアメリカ人」にはどう見えていたのか、とても興味深いところです。
「中国の戦争宣伝の内幕―日中戦争の真実(フレデリック・ヴィンセント・ウイリアムズ著、 田中秀雄訳)」を紹介するために、以下に目次や目を留めた項目をコピペさせていただきます。
興味が湧いて、他も読んでみたいと思ったら、本書を手にしていただければと思います。
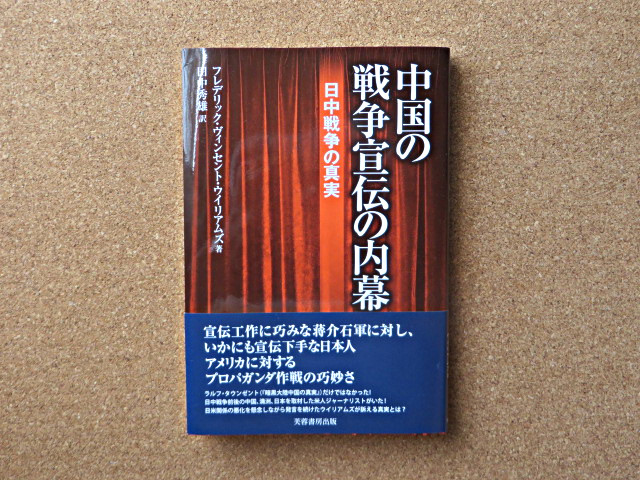
目次
序 文 9
第一章 極東の現状、その全体の俯瞰図
西洋列強のライバルとなった日本 13 / 孤立化した日本の対策と期待 16 / 蒋介石の野望 19 / 中国を侵食する共産主義 21
第二章 西安事件と頻発する日本人虐殺事件
西安事件の真相 25 / 蒋介石、対日開戦をドイツ顧問に告白 29 / 共産主義者、日本を挑発 31 / 通州事件 33 / 日本にいる中国人は安全である 35 / 盧溝橋事件 37
第三章 第二次上海事変の内幕
「アメリカを引きずり込め!」 39 / 蒋介石の上海攻撃 41 / 上海事変の開始 43 / わざと自国民を犠牲にする中国軍 44 / プロパガンダに頼る蒋介石 47
第四章 残虐きわまる中国軍を糊塗するプロパガンダ大戦略
「焦土作戦」と「氾濫作戦」 51 / スケープゴートにされた張学良 53 / 中国ニュースの巧妙なからくり 57 / 中国軍による日本空襲? 59 / ずる賢い宋美齢 61 / 博愛主義者・陸伯鴻の暗殺 63
第五章 日本のアジアに対する崇高な使命感
日本は満洲のサンタクロースである 67 / アメリカは満洲国を承認すべきである 69 / 軍閥のポケットに直行する支援金 71 / 日本機とロシア機の空中戦 72 / 張鼓峰事件の真相 75 / 日本人のアジアに対する使命感 79
第六章 パネー号事件と対米プロパガンダ大作戦
アメリカ人よ、目覚めよ 81 / パネー号事件の真相 84 / 日本はアメリカの最高の貿易相手国である 86
第七章 阿片を蔓延させる日本というプロパガンダ
阿片を蔓延させているのは中国である 93 / 日本が作った満洲の麻薬吸引実態統計資料 95 / 中国は阿片を蔓延させたとして日本を非難 97
第八章 中国人と日本人を比較する
中国人は信用できるのか? 99 / 清潔な日本人と不潔な中国人 101 / 中国の少女売買 103 / 交際上手と交際下手 105 / 礼儀正しい日本人 107
第九章 チャイナタウンの暗殺団と中国の軍閥
恐ろしいチャイナタウンの暗殺団 111 / 暗殺団の実態 113 / 奴隷少女の売買ビジネス 116
第十章 反日を煽る偽写真
上海の廃墟に泣き叫ぶ赤ん坊 119 / 銃剣で処刑される中国兵 120 / お人よしのアメリカ人 123
第十一章 ソ連の中国侵略を阻止しようと戦う日本 125
第十二章 宣教師の善意を利用して日本軍の悪を宣伝する
利用される宣教師 129 / 中国兵に虐殺される宣教師たち 132 / 南京の宣教師の打ち明け話 133 / 日本軍に感謝する宣教師たち 135
第十三章 広東と漢口の陥落、そしてその後の展望 137
解説
よみがえるフレデリック・V・ウィリアムズ 田中秀雄
1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6
序文
この本は極東の情況に光を当てるという目的のもとに書かれている。と同時にある国に対してなされている間違いを正すという目的もある。日本との戦争以前から、そして戦争が始まってから中国で起きている出来事は、プロパガンダのためにぼんやりと雲がかかったように見えている。アメリカにいる人々にはそこで何か起こっているのか、理解のとっかかりがないために特にそう見えるのだ。アメリカ人が極東で起きている出来事に間違った理解をしているのは、新聞記者のせいではないのである。なぜならば、彼らは中国の検閲官が厳格なルールを強制するために何もできないのである。
私が初めて中国を旅したのは、1937年の日中両国が戦いを始める前であった。上海と南京で、蒋介石政府の高官にインタビューしたのである。それから北京に行き、そしてシペリアの国境、それから満洲国を南下して朝鮮、そして日本に行ったのである。
それから私は戦争が始まってから中国を再訪した。最初は中国軍と行動した。それから今度は日本軍とであった。私は両方を見た。世界の各地を見た新聞記者としての長年の経験から、何か起こっているのかを理解することができた。私は戦場を後にした。私は多くのものを学んだ。そして精魂込めて書き上げたのがこの著作である。
私の希望はこの本を読む人が、極東で起きている大きなドラマの登場人物たちにもっとはっきりした判断を下してくれることである。そしてこの『中国の戦争宣伝の内幕』はただ大きな誤りを正すだけでなく、東洋における国家や人々についてもっと身近に友好的な理解ができることを目的としている。
近年極東の危機についてアメリカで書かれたすべてのものはほぼ一方の側に偏していた。一方の側だけから物語られている。あらゆる問題に二つの側があるはずである。もし一方の側だけから話を聞くならば、諸君は公平に情況を判断できない。我々アメリカ人は両方の側から話を聞くのがよろしい。この本を読む多くの人は、最初は日本側に味方をしていると思うだろう。しかしどれほど多くの本や新聞記事が中国贔屓で反日であるだろうか。しかもそういうものを「これは中国の味方をしている」とは言わないのだ。我々は日本に関するものよりも、中国に関して見聞きするものを疑いなく事実として認識する傾向がある。実際問題として、この国には中国のプロパガンダが氾濫している。そして日本を弁護するものをほとんど見ないのである。
アメリカは大きな決断の岐路に立っている。東洋のことに関する限り、今まで通りに盲目的にまっすぐ進んでいくこともできる。しかしまた、「騙されていた……」と事実に目覚めて、太平洋の彼方の大きな帝国との貿易と商業に大きな利益を掴む契機を見出すか、それを他の国に取られてしまうかということなのである。
私はこれを書くことにおいて手心は加えていない。私は誰をもバックにしてはいない。私は自由に率直に語った。我々がずうっと騙されているよりかは、真実を知った方がよいと考えたからである。
世界の歴史がアジアにおいて進展し始めている。その背後に何がうごめいているかを我々は知らなければならない。
共産主義者、日本を挑発 P31
さあ、中国では若い共産党員が、蒋介石が誘拐されてソビエトのコントロール下に置かれ、日本との戦争に同意したという西安とモスクワからのニュースを歓迎していた。後に南京に帰ってきた蒋介石によって戦争は延期されることになり、今度はその言葉は彼らの怒りと不信で迎えられた。彼らのリーダーの幾人かは南京政府で信用を得ていた。彼らは蒋介石の大軍でも日本を打ち負かすには充分ではない、結果として戦争は延期するしかないと警告とともに説得された。南京政府は彼ら数千名を数える若い共産主義者やモスクワの赤軍宣伝大学で訓練と教育を受けた数百名に、実際の戦争の代わりに、さらに一層大衆に反日キャンペーンをするように求め、結局は始まることになる日本との戦争に備えるように説得した。
しかし若い共産主義者は血が熱く敵意に燃えていた。すぐさま戦争を要求した。軍閥の大軍隊が行進し教練をやっている。都会の警察は夜に銃剣訓練をしているではないか? これは血と復讐の栄誉の日、金持が貧者にされ、貧者が金持になるその日を欺こうとするトリックではないのか。町からソビエトの旗が一掃されるのだと彼らは考えた。
「よし分った」彼らは結論づけた。もし蒋介石が言い逃れするなら、自分たちを騙そうとするなら、自分たちの手で事件を起こし、戦争にしてやる、日本を戦争に引き込んで見せると。
実行するのは簡単だった。中国には他国の人々と共に、万を数える日本国民が住んでいた。そのほとんどは孤立していた。中国人の町に妻や子と一緒に市民として暮らしていた。軍隊に保護されてもいなかった。商人や貿易業者は近づきやすく、逃げるのも簡単だ。中国では外国人が殺され続けてきた。目新しいことではなかった。再び起きてもおかしくない。おまけに日本人の男や女、子供たちは他の国から人気が悪くなっていた。モスクワやヨーロッパのある国々による熟練したプロパガンダのためである。その中の特に一国は中国に大きな利害関係があり、日本の商業的台頭を恐れていたのだ。他の国民は後で始末してやる。中国共産党はまず日本人を血祭りに挙げることに決めた。もし日本人が二三千名殺されたとして、誰が対応するのだ。虐殺は日本を激昂させるだろう。自国民を殺されて行動を起こさない国はない。面目は立たない。日本人虐殺は日本との戦争となるだろう。蒋介石も戦わざるを得なくなる。
そしてまた、蒋介石は南京で新たに軍隊を狂熱的に作り直そうとしていた。そしてこれによって中国中にさらに大きなスケールでの日本人男女、子供の虐殺が始まることになった。これには朝鮮人も含まれる。防禦方法を持たない無辜の日本人たちは、家で、店で屠殺され、町や村の街路で暴徒に殺された。数え切れない多数の日本人、朝鮮人たちがこうして死んだ。孤立したコミュニティで殺されていく。
通州事件 P33
私か住んでいた北支の150マイル以内のところに、二百名の男女、子供たちが住んでいたが、共産主義者によって殺された。二十名はほんの子供のような少女だった。家から連れ出され、焼いたワイヤーで喉をつながれて、村の通りに生きたまま吊り下げられていた。空中にぶらぶらされる拷問である。共産党員は野蛮人のように遠吠えしながら、揺れる身体を銃弾で穴だらけにした。
日本人の友人であるかのように警護者の振りをしていた中国兵による通州の日本人男女、子供らの虐殺は、古代から現代までを見渡して最悪の集団屠殺として歴史に記録されるだろう。それは1937
年7月29日の明け方から始まった。そして一日中続いた。日本人の男、女、子供は野獣のような中国兵によって追い詰められていった。家から連れ出され、女子供はこの兵隊ギャングどもに襲い掛かられた。それから男たちと共にゆっくりと拷問にかけられた。ひどいことには手足を切断され、彼らの同国人が彼らを発見したときには、ほとんどの場合、男女の区別も付かなかった。多くの場合、死んだ犠牲者は池の中に投げ込まれていた。水は彼らの血で赤く染まっていた。何時間も女子供の悲鳴が家々から聞こえた。中国兵が強姦し、拷問をかけていたのだ。
これは通州のことである。古い町だが、中国で最も暗黒なる町の名前として何世紀の後も記されることだろう。この血まみれの事件に380人の日本人が巻き込まれた。しかし120人は逃げおおせた。犯され殺された者の多くは子供であった。この不幸なおびただしい日本人の犠牲者たちは暴行が始まって24時間以内に死んだのだが、責め苦の中で死んでいったのだ。中国人たちは焼けたワイヤーを鼻から喉へと通し、両耳を叩いて鼓膜を破り、彼らの「助けてくれ」との叫びを聞こえなくさせた。目玉を抉り出し、自分の拷問者を見られなくした。アメリカ西部の開拓初期の頃のイロクォイ族もスー族もこんなことまで考案しなかった。
セオドアールーズベルト・ジュニア夫人は中国から帰ってきて、『サタデー・イヴニング・ポスト』(1937年10月21日号)に、中国人の品行問題について、啓発的意見を述べている。
「……突然私たちは叫び声を聞いた。それは不機嫌なわめき声に変わっていった。私たちの直ぐ下で、一塊の群衆が激怒した暴徒と化し、大声で叫びながら5人の日本人を追っていた。4人はうまくバスの中に逃げ込んだ。奇妙だが、中国人は日本人を引きずり出そうとしなかった。1人がよろけて落ちた。彼らはそこに襲いかかった。それから彼は血だ
らけになるまで蹴られた。殴られた。踏みつけられた。肋骨が折れ、顔がどろどろと血まみれだった。そこに白いターバンのシーク教徒の交通警察官が南京路の交差点から鞭を持ってやってきて、暴徒をうさぎのように追い散らした。それから救急車を呼んだ。暴徒がまた集まってきた。明らかにやり返しに来たのだ。私はあの日本人が死んでいると確信した。しかし担架に乗せられたとき、彼の手が動くのを見た」
日本にいる中国人は安全である P35
こういう事件が起こっているときも、その後も、日本帝国に住む六万人の中国人は平和に生活していた。彼らの生命や財産は、日本人たちとの渾然一体となった友好的な社会関係の中で守られていた。私は横浜のチャイナタウンを歩いたことがある。他の町でも遊んでいる中国人の子供を見つけた。危険や恐怖など何も知らない表情だった。
かたや中国では、かの国人が暴徒と化して、日本人の子供を好きなように捕まえていたのである。東洋的微笑の中で我々のように暮らし旅した者は、「日本人の残忍さと非人間性、それに較べて貧しき中国人の平和な人間性とはいかに違うものか」と聞くことがある。
通州で無辜の日本人たちを虐殺したまさしくその中国兵たちが、捕虜になったときは日本軍によって給養され、「罪を憎んで人を憎まず」のサムライ精神によって、「もうああいうことをしてはいけない。さあ行け」と説かれていたのである。日本軍の将官は虐殺の罪を無知な兵隊に帰するのではなく、南京の軍閥やモスクワ、無知な耳に叩き込まれた反日宣伝のせいだとしたのである。
世界はこれらの非道行為を知らない。もし他の国でこういうことが起きれば、そのニュースは世界中に広まって、その恐ろしさに縮み上がるだろう。そして殺された人々の国は直ちに行動を起こすだろう。しかし日本人は宣伝が下手である。商業や戦争において、西洋諸国のような方法を取ることに熟達していたとしても、日本人は自らの敵が世界で最強のプロパガンダ勢力であることにもかかわらず、宣伝を無視するだろう。
中国にいる外国人には驚きとしか思えないのだが、日本はすぐに動かない。彼らは共産主義者によって虐殺が遂行されたことが分っていた。また西洋諸国が日本を世界貿易市場から締め出した以上、北支との間でビジネスをしなければならないことが分っていた。率直に言って、中国とは戦争をしたくはなかったのである。中国政府がロシアのボルシェヴィズムの罠に絡め取られていることも分っていた。しかしそれでも中国の人々とは戦争をしたくはなかったのである。なぜなら中国は隣国であり、もし望むならば、生きていくためのなくてはならないお客様だったのである。
日本は南京とモスクワを真剣に観察していた。まずソビエトの国内がぐらついているのを知った。共産主義と第三インターナショナルは時がくれば自壊するだろうと。蒋介石とその統治が中国人に人気がないことも知った。彼らは蒋介石とその将軍たちが外国に資産を蓄えていることを知っており、時が来れば、愛想づかしている彼らに代わって新しい指導者についていくだろうと。その指導者というのは日本のように共産主義に反対し、北支に日本のために貿易を開始してくれる人物である。
盧溝橋事件 P37
日本人虐殺は続いていた。掠奪、殺人が継続した。そして盧溝橋で日本軍が銃撃された。中国共産主義者がこれをやった。火をつけて引火させたのだ。というのも日本軍の軍服は天皇を表象する聖なるもので、日本人は深く永遠なる愛で天皇を仰慕していたからだ。つまり心の中にある火が大きく燃え上がったのだ。
日本は今度は迅速に対応した。共産主義者は後退し、南京の軍閥の統治下に呻吟していた北京市民は、日本との門が聞かれたことを喜んだ。彼らは蒋介石の北京抹消計画を知っていた。また世界では知られておらず、中国人は皆知りたがっていたことだが、蒋介石はモスクワの共産主義と平和協定を結んでいたということも知った。中国共産党は権力の座に昇ろうとしていたのだ。
中国共産党は蒋介石を日本と戦わせようとし、戦争に引きずり込んだ。思ったとおりになった。しかし北京の市民はこれらの共産主義者に抵抗した。町が共産主義者に乗っ取られたならば、南京に屈従しなければいけないし、反日軍閥に救いを求めねばならない羽目になるのだ。
中国ニュースの巧妙なからくり P57
この特電をかなり長く引用したが、それというのも蒋介石の権力下では、彼らの支配地域の事件についてダメージをもたらす証言が漏れ出すようなことは滅多にないからだ。彼らはここ2年ばかり、自分たちに本当に都合が悪いことや外国の新聞に真実を知らせる写真とかが全く見出せないほど、この点に関してとても注意深く慎重であり、熟練している。他に例が見出せないほどだ。もちろんその結果は、国外の普通の人は中国に関して何も分らないし、日本と戦っている人々は偉大な愛国者であり、その指導者なのだという印象を植え付けられるのだ。
しかしながらこの特電は、蒋介石の広報機関が二歩も三歩も先んじる、あるいは適当な弾幕を張って、なかったものにするという彼らのやり方に沿っていることを例示しているのだ。もしそうでないと疑いなく世界に知られ、彼らにダメージを与えることになりかねないからだ。
この端的な一例が中国によってなされた日本への飛行機の襲撃だ。私はそのとき中国におり、このやり方がとほうもない巧妙さでなされているのを見た。
宿縣が陥落しようとしていた。上海は既に落ちていた。上海にすぐ続いて宿縣が陥落することは蒋介石が勝利を保証していた中国人の心に重大な影響を及ぼすだけでなく、軍需品を購入しようという政府の信用をなくしてしまいかねなかった。孔祥煕博士はこれらの交渉を苦心してまとめて、直ぐにヨーロッパから帰国してきた。上海失陥はヨーロッパの一部の銀行家たちを神経質にさせていた。だから中国の「勝利」、「日本の大損害」のニュースは彼らを一番元気づけるものだったのだ。狡猾な蒋介石、孔博士その他はこれによってヨーロッパの天使たちの心を繋ぎとめることができたのだった。
日本軍が宿縣に迫り、町の陥落は後二三日という時、蒋介石とその宣伝班の緊急会議が聞かれた。宿縣陥落をチャラにする何かだ。何かないか? あるアイデアが提供された。誰なのか私には分らない。しかしその会議に出席しており、まぎれもなく目立つ人物だ。ある人はそれが蒋介石夫人だと言っている。確かに彼女はそういうことに天賦の才を発揮したことかあるのだ。
びっくりするような何か、衝撃的な何か、ぶんなぐられるような何かが起こり、宿縣陥落が新聞の一面や見出しから外され、中国は打ち負かされてなどおらず、再起して日本と戦い、その足元、いや少なくとも手の届くところまで迫っているという印象が世界中に与えられねばならない。
その何かというのは(他にいいのがあるだろうか?)中国機が日本を襲撃するということだ。総統と蒋介石夫人は日本軍の空襲によって諸都市が席巻され、空襲されたということで世界中を嘆かせていた。
真実はこうである。彼らは軍隊や軍需工場を撤去すれば、空襲や市民の生命損失を防ぐことができたのである。あるいは少なくとも、これらの諸都市の市民の避難を強制しようとはしなかった。しかし日本の空襲は総統の政府にとって願ってもない大宣伝となっだのだ。
中国軍による日本空襲? P59
報復するのに何かいい方法はないだろうか? 日本への空襲? しかしこの話は何度も討議されたことだった。重い爆弾を抱えて、日本の警戒をすり抜けることのできる飛行機などない。ロシア人パイロットでも成功しないだろう。アメリカ人ヨーロッパ人でも運があればの話だ。爆弾を抱えた飛行機は低空飛行を余儀なくされるから、発見されるのを覚悟しなければならない。しかし爆弾なしでは? 爆弾なしなら、軽い、軽い。千フィート、千二百フィート、千五百フィート以上雲の上を高く飛べる。それで日本に何を? もちろん日本国民に向けたパンフレットだ。それは三つの目的を果すだろう。新聞の一面と見出しから宿縣陥落を内側のページに移し、重要でないものにする。世界(特にキリスト教世界)に、無辜の市民が爆弾で死んでいる現状に対して中国の軍閥は充分に情け深いという印象を植え付ける。三番目は日本人に恐怖を与えることだ。
それから一機の飛行機を飛ばすことが決定された。二機でも三機でもない。半ダースでも駄目だ。たった一機だ。そしてその飛行機が帰ってきたとき、世界に宣言するのだ。もし帰還しなかったならば、六機の飛行機が攻撃しに行ったということにするのだ。
同時に日本国民への声明文もひそかに作成されて、タイミングもちょうど宿縣陥落間近と重なっていた。たった一機が日本に向かって飛び立った。空高く雲の上を飛んだ。むろん爆弾がないからだ。不安な面持ちで蒋介石たちはその帰還を待った。その飛行機は日本の警戒を回避して充分高く飛んだ。それは日本本土まで届かなかった。日本の最南端のそのまた先っちょに到達して、一つそびえている山に向かって降下してパンフレットをばら撒き、パイロットは無事に帰還した。
早すぎる帰還ではなかったが、飛行機が着陸した瞬間に、蒋介石の宣伝班は世界に向けてニュースを発信した。しかも効果を上げようと奇抜な金メッキがほどこされていた。六機の爆弾を持った飛行機が日本に深く侵入し、本土に到達、大工業都市である大阪(日本のシカゴ)の上を低く飛び、日本軍と市民を死ぬかと思うほど驚かしたと新聞記者たちは教えられたのだ。しかしこれらの六機の飛行機(実際は一機だが)は爆弾を落とさなかった(一機さえも爆弾は持たない)。落としたのはパンフレットだったが、それには「中国国民」からの「日本国民」への優しい訴えのメッセージが書かれてあった。
宿縣は失陥したが、蒋介石の宣伝班は陥落を打撃に変えて連打した。外国 ―― 特にアメリカでは、新聞の黒いインクの見出しが金切り声を上げていた。「中国軍機が日本を空襲云々」。そして宿縣に関しては戦略上の要衝の失陥であるから、蒋介石とその政府の破滅
であることを軍事的に封印し、新聞の片隅に閉じ込め、無価値なニュースになってしまった。日本空襲の記事を読んだ人の十分の一もいなかっただろう。
日本人は「中国機に空襲された」ことを、外国の新聞を読むまで知らなかった。四五日経ってから日本の農民が、最南端の寂しい山の麓からパンフレットを回収して憲兵に届けてきた。上海の国際租界では、「空襲」記事が載った号外が有名店のホットケーキみたいに売り出された。それを買った中国人は肩をすくめて、記事を信用しなかった。中国人の間では蒋介石は大嘘つきとして評判を取っていた。だから彼らは蒋介石の宣伝局が報じるプロパガンダにひっかかるにしても、結果として最後の人だちなのだ。しかしアメリカではお互いに見合って、真面目に頷きながら言うのだ。「ざまあ見ろ ―― 日本軍は中国の町を空襲していた。今度は中国の番だぜ」
日本は満洲のサンタクロースである P67
経済的利害関係のために、列強が中国で充分にパワーを発揮できなくなるのではないかと恐れているからでもあるが、我々西洋人とその政府は、間違った同情心や政治的行動によって、中国での戦争と惨害が打ち続くようにしているのである。これには故意にそうしている国もある。中国の大多数を占める本当の人々は、戦争と迫害にうんざりしているが、外国の国々が邪魔をしなければ平和になるのだ。
一部の西洋列強とその国民は、あらゆる方法で日本の邪魔をしている。日本が中国人を牛耳っている軍閥と戦争を始め、この国を保守的なよい政府の下に安定させ、平和をもたらせようとしているからだ。私は多くの中国人と対話した。彼らは率直に私に話した。一番願っているのは、共産主義や軍閥同盟に反対する保守的政府を作り上げることであると。しかしそれができないのは、匪賊の頭目たちが私兵を使って省を領土にして力を誇示しているからだと彼らは屈託なく告白した。
満洲でやったように、唯一つ日本の協力がこれを可能にすると彼らは主張した。彼らは満洲を強調した。今の満洲国である。日本が中国のためになすことができた一例である。もう一つ北支がある。中国南部は全体としては絶望の尺度から言えばまだいい方である。中国南部の安定は大英帝国にかかっている。香港からの影響もある。これは彼らも認めている。赤いロシアはイギリスが香港のゲートを守っている限り、あえて進出はしないだろう。そして彼らは同じ真実が北部にもあるとしばしば言うのだ。日本がたった一国で軍閥を押さえつけ、共産ロシアを排除できているのだ。
満洲とは日本人が出かけて行って貪り食った、罪を犯した国だとごく普通の人たちは信じているだろう。日本がそこに行ったのは確かだ。しかしもし諸君が満洲に行けば ―― 満洲国 ―― 日本はサンタクロースの役をこれまで演じていること、満洲人が断然幸福であることを発見するだろう。彼らの古いご主人、ロシアと中国はまあ残酷な親方で、ひどく苦しめられていたのだ。平和と安全、政府とビジネスの安定、鉄道の建設、都市の建設、病院や学校をもたらしたのは日本だった。
日本が来る以前の満洲は、現在と較べれば哀れと言うしかない光景が広がっていた。しかもなお満州は自分では何もできなかったのだ。今も自分だけの力では自立できていなかっただろう。共産ロシアと軍閥によって破壊されていただろう。日本と出会わなければ、怠惰と衰微の中に陥っていた。さらになお日本が満洲を幸せだと満足できる状態にしているにもかかわらず、我国の政府やその他の国々は満洲を承認しようとしない。いつか未来の歴史家は我々が間違っていることを証明するだろう。歴史はアジアで繰返されているのだ。我々はそれを知ろうと全く努力していない。壁に書かれた文字さえ見ようとしない。
中国人は信用できるのか? P99
もし我々が極東の情況を、本当は何が起こっているか真摯に研究しようとするならば、特に二つの民族の性格を分析しなければいけない。中国人と日本人であり、彼らを全体として、あるいは国民生活の中に見なければならない。まず始めに注意深く分析をするならば、これは我々のほとんどにショックを与えることになる。最初の頃、我々は中国人が正直な友人で、日本人はそうでないと教わってきた。私はこの神話の始まりの60年ばかり前に諸君を連れ戻そうと思う。
我々の祖父たちがまだ子供であった頃だが、アメリカの地理の本に、日本人の実業家は帳簿や会計のために中国人を雇うという趣旨のちょっとした記事が出た。なぜなら日本人なのに、彼らはその自国人を信用していないからだと言うのだ。正反対が真実であることは多いものだ。今日においてさえ、日中間に戦争が始まった当初まで、中国人家庭には多くの日本人の出納係がいたものだ。そして多くの場合(昔からそうだが)日本人家庭には中国人の帳簿管理者はほとんどいない。
こんな愚かな話がアメリカの地理の本に出ていて、子供だった祖父たちが読んでいたのだ。これは数世代を通じて受け継がれてきており、たぶん今日は学校の教科書に書かれて常識となっているのだ。
もし諸君が東洋に来て、中国人商人からものを買うとする。同じものに沢山の値段があるのを知る。もし諸君が東洋に住んだことがあるなら、商人が最初に言った金額を出しはしない。その代わりに商人が負けに負けるまで、駆け引きをして値切る、論争するのだ。そうすると、自分が満足できる三分の一か四分の一というような値段でその物が買えることになる。中国での生活は、何百年もの苦々しい闘争の歴史である。お金は民衆の最大の神様となっているのだ。
さて諸君が今度は日本で日本人商人と交渉するとする。商人が決めている最初の売値と、諸君が払いたい金額がぴったり一致するということを直ぐ理解するはずだ。値段を下げさせて負かす必要もない。値段は公正なルールの下で、適切なマージンが決められているのだ。合理的である。
もし諸君が中国でビジネスをしようと思うなら、定評のある署名を添付してもらうことと、なんらかの国際的な場にある、つまり租界の安全な裁判所の管轄下で、これで申し分のないという取引をしなければいけない。さもなければ、平均的中国人相手だと、逃亡にあって、ビジネスはおじゃんになりかねないのだ。自分の側か正しいと主張したって関係ない。法律を持たなければ駄目なのだ。どういう法律か。できれば権力だ。そうすると勝つ可能性がある。
平均的日本人相手であれば、こういう署名はほぼ正反対に不必要である。彼の言葉は折り紙つきの証文なのである。もちろん中国でしばしばあるように、例外はある。しかし一般の日本人の中においては、言葉は誠実で守られている。実際上は国民性となっている。確かにこういうことは中国では言えない。
交際上手と交際下手 P105
諸君がかの国であるいは外国で出会う平均的な中国人は、非常に愛想のよいごろつきだ。大体において好ましいし、何かあるという場合、交際上手である。諸君の好意を獲得するのがうまいし、言葉も比較的簡単に覚える。それだから民族的な壁も感じないですむが、諸君がどんなに長く彼といたとしても、彼が何を考えているか分からない。しかし彼が微笑むときには、実は何も意味していないのだと諸君は学ぶようになるのである。
日本人はこれと反対に、交際下手である。よそよそしいし、諸君を理解するまでは、彼は話したがらない。外国人が受ける第一印象はまるで不機嫌で、自分を嫌っているように見える。生まれつき疑り深いので、好いたり信用したりする前に諸君を知らなければならないからだ。しかし諸君は通例、彼に頼るようになる。彼は決して騙さないのだ。平均的アメリ力人のように、日本人は語学を得意としない。日本人のほとんどは平均的アメリカ人のように、外国語の習得が苦手だ。
しかしながら、この日本人の短所は改善されるべきで、東京やその他の都市には多くの英語学校がある。日本人は現在、中国人、ドイツ人、イタリア人、フランス人相手に英語を使っている。アメリカにもイギリスにも住んだことがなく、日本を出たこともない日本人の中に、素晴らしい英語をしゃべるのがいる。しかし確かに多くのケースがあるもので、英語を学び話す日本人の言葉が完全でなく、理解しがたいのも事実だ。
日本人は誇り高い民族である。そして傷つきやすい。その誇りは最下層の労働者でも持っている。中国人も誇りを持っているのかもしれないが、それを見せようとしないし、外国人との関係上からか拒絶しようとする。東洋にいる西洋人はおおっぴらに中国人を罵ってきたし、彼らはにこにこしてそれを受け取っていると私は思っていた。
しかし日本人相手ではそうはいかない。とげとげしい言葉や打撃は日本人には報復の対象だ。彼は仕返しをしてくるだろう。彼は侮辱や名誉毀損に堪えられないから、自分を守るために食ってかかるのだ。これがアジア人相手に威張り散らす癖があるタイプの、東洋在住の西洋人相手に日本人の人気がない理由である。事実、中国人は何世代にもわたって西洋人による虐待を親切と礼儀で切り抜けている。奇妙な話だが、彼らは自分で自分を弱き者、服従すべきものと考えているのだ。
アメリカ人は多くの欠点がありながらも、心では民主主義者であり、接触があったあらゆる国民に民主主義を広めようとしている。アメリカ人が平均的な中国人に屈服したとする。彼がいくら親切で優しく、礼儀正しくても、とたんにこのアメリ力人は弱虫で、気の弱い、地位もない、無価値な人間と受け取られるのだ。有利な立場に立たれるのだ。
利用される宣教師 P129
没落し行く蒋介石政府は絶望したあげく、アメリカ人が結果として干渉してくることを期待して、まず同情を、それから援助を獲得しようとして宣教師たちにすがり寄った。彼らは既にプロテスタント派のかなりの部分の同情を獲得していた。今はカソリックに接近を試みようとしている。カソリックは全体として、どちらの側にも立たず一歩下がっている。戦争が始まる前、カソリックは南京軍閥政府から布教を奨励されたことはほとんどなかった。そして今、ロシアのボルシェヴィキの影響から中国を分離させようと日本が猛烈に迫ってきたために、以前の南京支配者はそれまで伝道上において大なり小なり横道にそれていたカソリックに、耳さわりのよいあらゆる約束をしたのである。
同業のプロテスタントのように、カソリックの中にも蒋介石の約束に騙される者がいた。もし蒋介石が日本に勝ったなら、ボルシェヴィキの仕事をはかどらせることになること、彼らの教会の信仰は共産主義とは妥協の余地が絶対ありえないということを見逃していたのだ。そうした一部の伝道師たちは、中国の特にこの場所といったところに長く住み、中国政府の水平線上に浮かぶ赤い色合いをつぶさに観察できる位置にいた人たちであった。
蒋介石一派は彼らに接近し、そしてプロテスタントの宣教師と同じように、日本軍のアトロシティー(残虐行為)と申し立てられている野蛮な話で宣教師の耳を一杯にして、彼らに合衆国の彼らの友人宛に精神的な苦しみの手紙を書かせたのだ。
中国南部の宣教師たちの一部はこれに影響された。疑いなく、上海の数名は友人に手紙を書いている。すべて誠意である。しかし彼らが蒋の影響下に屈服したとき、多かれ少なかれ、厳しく中立であろうとする彼らの至高のものへの願望に反したことになったのである。
中国そして極東を旅行していたとき、日中戦争の前でも最中でも、私は幾つもの宗派の沢山の宣教師だちとコンタクトを取った。そして私は特にカソリックの間に、日本が中国でしていることの正当化について、意見が鋭く分裂していることを発見したのである。多数派は日本を弁護する。その他は中国を弁護する。日本、朝鮮、満洲国のカソリックの宣教師たちは、日本がボルシェヴィズムからアジアを救おうとしているのだと率直に述べる。北京、北支の内陸部でもこれと同じである。しかし上海では傷つき死にかけ、飢えた者のために英雄的に働いている宣教師たちがいたが、戦争の恐怖を目の当たりにしているためか、日本に反対し、中国の肩を持つ若干の熱心な者たちがいた。
蒋介石の取り巻きは、一部プロテスタント宣教師に対すると同様に、彼らにすかさず飛びつき、「母国」に手紙を書いて、日本を激しく非難するようしきりに促したのである。これらの手紙は中国の軍閥に強力なプロパガンダとして利用され、そのいくつかはアメリカの新聞や雑誌に載り、いつもの事ながら多くの匿名読者の目に触れたのだった。
総統や彼ら軍閥がアメリカヘのプロパガンダ目的のために宣教師に擦り寄ってくるかなり以前に、宣教師たちの多くはアメリカ人の間に中国への深いきずなと同情をごく自然に作り上げていたのだった。
宣教師がやろうとしたのは、アメリカ人からの寄付であった。結果的に彼らは中国で起きている光景に対し、故国の人々を中国側に立たせ、より友好的にすることに成功したわけである。彼らは軍閥の支配体制、泥棒性、いかさま性、不信性、道徳的堕落、野蛮性、ふしだら、賄賂といったことには言及しない。これらは役人にも大衆にも共通する中国人の日常生活である。彼らは「素晴らしい」ところ、哀れを誘うところ、同情を喚起するところしか言わないのだ。中国人は善意で貧しくて、西洋世界とキリスト教が彼らに与えられるものを評価し、あこがれていると。
中国兵に虐殺される宣教師たち P132
過去23年で250人もの宣教師が中国兵や匪賊に誘拐されて身代金を要求されたり、殺されたりしている。これに対して戦争が始まってから日本人に殺されたのは10人か12人である。これらの事件が起きたとき、中国人に責任がある場合は知れ渡らないように目立たないように伏せられた。しかし宣教師が日本兵に殺された場合は、絶対数でははるかに少ないのに凶悪事件として世界に告知されたのだった。
宣教師たちは中国の「目立つ場所」にいると言われなければならない。そこは中国兵と匪賊、共産主義者に取り囲まれているところであり、日本側に立って言えば、いかなる事情があっても彼らの死を意味するところと言われなければならない。彼らの名誉のために言えば、宣教師たちは概して中国人に大きな愛を抱いている。彼らのために立派な仕事をしてきた。彼らは自分たちの多くが「米を食うクリスチャンであって、米がなければクリスチャンでない」との認識に論駁してきた。彼らは目に見えても報われない仕事ばかりに人生を費やしてきた。中国はとても返しきれないほどの多くを彼らに負うているのだ。日本は少なくとも宣教師たちによってなされた良いことを理解しているし、戦争で破壊された布教施設の再建のためにお金も寄付している。
私は中国で多くの宣教師たちと話したが、蒋介石を支持する少数派でさえも、ポルシェヴィズムの侵入の危険性を認めていた。しかし多数派の仲間と同じように、チャンスをつかもうと思っていても、群衆の中に変装してうろつき、総統やその配下の軍閥に反対する誰彼を打ち倒そうとしている中国人テロリストによる憎しみや復讐の危険を引き受けようとまでは望んでいないということだ。幾人かは率直に手を縛られているんだと私に話してくれた。もし彼らが日本に好意を持てば、陸伯鴻のように殺されるのだ。あの上海で殺された偉大なカソリックの博愛主義者だ。
南京の宣敦師の打ち明け話 P133
私は戦争が始まる前の冬、南京にいた。カソリックの宣教師の家に滞在していたことを思い出す。聖人のような男で、中国人に誠意を尽くそうと辛苦と窮乏の生活をしていた。それは古い家だった。燃料もなかった。なぜならそれは高いし、それに彼は食事を作るために仕える中国人少年と暮らしているだけだったのだ。家の中はとても寒く、我々はオーバーコートを着たまま食事をし、着たままで私は寝た。
この司祭は着の身着のままの苦力や、彼を認めようともせず、学校を経営する特典を許さなかった蒋介石の役人に対してさえ深い愛を抱いていた。もっとも別の宗派は市内にカレッジを経営していた。夜に、彼は蒋介石の役人たちに語学を教えることを許されていた。
それだけだった。彼は忍耐と祈りを以って、いつか中国政府の力強い保証と許可を得て、南京に本物の学校を開くのだ、それから遂には本物のカレッジを創設するのだと希望していた。
戦争が始まると、蒋介石政府の態度に変化が起きた。それまでこの司祭を撥ねつけるだけだったのが、南京にカレッジを開く特典が提供されてきたのだ。覚えて置いて欲しい。戦争が始まった後に、提案があり、約束がめぐってきたのだ。蒋介石とその軍閥は合衆国から得られるだけのあらゆる同情を必要としていた。総統の目は疑いなく、二千二百万人の合衆国のカソリック信者に注がれていた。カソリックは共産主義に反対しており、彼の背後にモスクワの影響を見、感じていることを恐れたのだ。
私がその後上海で、この司祭の同僚に会ったとき、彼は全く無邪気に誠意を以って私に、蒋介石が彼とその仲間に南京にカレッジを作っても良いという約束をしたと言ったのだ。
「戦争が終ったときは勝ったときだ」
同僚もそうだが、この司祭は数年間を上海で過していた。中国人の居住地に入り込み、苦力の中でも最も哀れな人々の間で慈悲と慈善事業に立ち働いていた。戦いが始まったとき、空から降ってくる中国軍の爆弾は自国民をバラバラに引き裂いていた。彼らは命の危険を冒して自らの持ち場に留まっていた。しかし彼らはこの情況とその背景にあるものを、彼らが呼ぶところの「わが子たち」の悲惨と受難とのみを除いて何も理解できなかった。
しかし旅をしてきた宣教師たちや外国の土地にいた体験がある司祭たちは、中国の城壁にボルシェヴイキの殴り書きかあるのを望楼から見ていて、違うものを感じていた。彼らは中国のためには、蒋介石や彼の配下の軍閥、ボルシェヴイキに支配されないほうがベターで、そして日本は中国を沈みゆく泥沼から救い上げ、立ち上がらせようとしているという意見だった。
解説3
本書は、ウィリアムズが支那事変の始まる前、そして始まってから中国や満洲、日本で取材し、体験し、見聞したことを基にしたレポートである。本書でも確認できるように、彼はカリフォルニア州のロサンゼルスやサンフランシスコで約二十年間、新聞記者として活動していたジャーナリストであった。そうした実績のあるプロの目による中国=極東レポートであるということを念頭に入れて読んで欲しいと思う。
また彼は当時親中国的だと思われていたアメリカ人の記者であるから、孔祥煕を始めとした取材対象の南京政府要人たちはあまり警戒をしなかった可能性が高い。ウィリアムズの書いている南京政府の思惑や行動の描写には高い真実性が含まれていると私は思う。
むろん本書は元々はその当時の現場レポートである。日本とアメリカが中国問題を介して直接的な対峙=戦争という形にならないように、彼が必死に願いながら書いた本である。
結果はうまくいかず、日米関係は最悪の結果にまで行き着いた。池田林儀の言うように、ものの見事に蒋介石の宣伝上手は当たり、宣伝下手な日本人はアメリカとの戦争に引きずり込まれていったのである。まさに拙論「プロパガンダとしての南京事件」を傍証する著作であった。
「蒋介石の宣伝係はプリンターインクで戦っている。兵隊や銃ではない」とウィリアムズは本書で書いているが、こういう認識が当時の日本軍になかったわけではない。「支那軍は鉄砲を撃たずに電報を打つ」という言い方である。
実際の戦争では日本軍は強かった。中国側を圧倒した。しかしその強さが残酷であり、非人道的であると中国側は宣伝していた。そうではないという宣伝を日本はできなかった。実際はウィリアムズの言うように、一般の中国人にとって良い社会を作ろうとしていたのにである。
ウィリアムズは、Japanese are poor propagandists(日本人は宣伝が下手である)と二度も本書で書いている。アメリカにいて、ひどくなる一方の日本のイメージを見ていて、これはほとんど嘆息であったのだろう。
しかし本書を訳しながら、私はつくづく日本は完全に包囲されて出口がなくなっていたのだなと感じた。それこそ嘆息していた。元々宣伝が下手くそな日本人が四方を敵に囲まれて、何を言っても信じられるはずがなかったのである。執るべき方策は限られていた。
本書の記述は日本が広東や漢口を占領した1938年10月の時点で終っている。しかしその後になっても支那事変の構図は全く変化することはなかった。対米英戦争は必然であった。日本がいかに和平策を講じようと、中国国民党も共産党もアメリカの対日「干渉」interventionの深化 ―― 日米外交関係の破裂を待ちながら、日本の悪宣伝に狂奔していればよかったのである。
だからといって、そのことに我々が自虐的になる必要はない。自信を持ってよいのである。本書を読めば分かるように、過ちは明確にアメリカにイギリスにあったのである。そのことに彼らが気づくのは日本が敗戦してからである。昭和の戦争という問題は、昭和20年8月の戦闘が終った時点までで論じられるべきでなく、日本敗戦後の世界情勢がどうなって行ったかを見きわめて論じられるべきはずだからである。東アジアの場合を具体的に言えば、共産中国の成立、朝鮮半島における朝鮮戦争という二大事件がある。これこそ、アメリカやイギリスの最大の過ちであったはずであり、こういうことが起らないように、日本はたった一人で戦っていたのである。つまり共産主義との戦いである。
あるいは、ジョン・オサリヴァンが書いた有名な『マニフェスト・ディスティニィー』(1839年)を例証にあげることができよう。建国して50年のアメリカは歴史において汚れを知らず、未来に向けて世界史を作る責任と義務がある。つまり人間の自由と平等、進歩を打ち立てるのがアメリカの責務だと言うのである。この中に「博愛主義者は圧政や残虐性、人類の多くに課せられた不正に対して熟考できているのだろうか? 道徳的な恐怖を持って振り返らないのだろうか?」という文言がある。「圧政、残虐性、不正」は本当は中国の問題ではなかったのだろうか。アメリカは180度の誤解をしていたのである。
このことをウィリアムズもラルフ・タウンゼントも理解していた。本書と、『アメリカはアジアに介入するな!』を合わせ読んでいただければ、この昭和十年代のアメリカの異常さがご理解いただけるであろう。
解説4
昭和12年12月13日の南京陥落後に起きたとされる「南京事件」について、あるいはその後の中国側のプロパガンダに関して、ウィリアムズは本書で特に何も語っていない。中国が日本軍の残虐行為=アトロシティーを宣伝していたと書いているだけである。
おそらく彼は日本の南京攻略戦には特に問題はないと認識していたのであり、中国側の非難にしても、プロパガンダの一つとしか認識していなかったのだろう。特にこのことについて書く必要も認めていなかったのだ。
彼の認識に近いのが周仏海であろうと思われる。彼は重慶から脱出して日本と共に親日政権を樹立した汪兆銘の片腕であった人物であるが、南京陥落前の昭和12年11月20日に南京を離れ、長沙に逃れている。その時の事を『中華日報』(昭和14年7月)に回想して書いている。
土地の古老が彼に言った。「傷兵が地に満ち、散散に悪事を働いている。これから日本軍のやってこないうちに、恐らく傷兵や退却兵、さては匪賊の蹂躙の下で、自分らは生き延びる者なく亡びてしまうだろう」と。
これはウィリアムズが本書で書いている悪辣な中国兵の描写と符合するだろう。また周仏海は昭和15年から日本敗戦後まで南京に在住している。その問、彼は克明な日記を毎日のように書き付けていた。そこには北支で日本軍が悪い事をしているという記述はあるが、しかし「南京虐殺」については一切記述がない。むろんこれは私的な筆録であり、公開を念頭に置いたものではない。もし恐ろしい中国人大量虐殺が南京であったとすれば、ふとした折に何らかの感懐があってしかるべきで、ないというのはやはり虐殺はなかった
のだ。
私は前記の「プロパガンダとしての南京事件」で、『南京の真実』(講談社文庫)を書いたジョン・ラーベを批判しているが、彼はドイツ・シーメンス社の中国支社の筆頭として、約30年もの間当地で働いていた人物である。
日本で大正期初頭にシーメンス事件が起き、当時の海軍の上層部にまで問題が広がったように、シーメンス社は軍需方面に関係が深い電気製品製造会社である。ドイツ軍事顧問団を通して、あるいは直接間接に蒋介石政権と深い関係があると思わなくてはならない人物である。そうした人物が書いたとされる『南京の真実』が本当に中立的なのか、疑問を持たれても仕方があるまい。
例えば南京安全区国際委員会委員長の立場にありながら、しかし安全区には南京陥落以前から中国兵が入り込んで立ち退かないと怒る仲間のローゼンの発言を書きながら、ご本人のラーベはいそいそと龍と周の二人の上校(大佐)を三万ドルの現金ともどもかくまうのである。彼らは翌年2月にラーベが南京を離れる間際までラーベの自宅にいた。それだけでなく、汪漢萬という将校もかくまわれており、彼は使用人という形で南京をラーベと共に脱出している。(『南京の真実』より)
こういう行動をとっているラーベが書いている日本軍の残虐行為が、どの程度信頼に足るものなのか疑問と言うしかない。中国側の反日プロパガンダ戦略に沿った形で行勤し、日本を非難し、著述していた人物なのは明らかである。本書でウィリアムズが観察し、レポートしているドイツ顧問団と蒋介石の親密な関係を念頭に置けば、これはたやすく理解されることだろう。
その他にも例えばウィリアムズが南京で取材した宣教師が蒋介石政府からどのような待遇を受けていたのか、戦争前と以後との鮮やかな豹変事例が本書で紹介されている。これは象徴的である。南京にいた宣教師たちが日本軍の悪を告発していたのはよく知られているが、本書はその背後にある真相を明らかにしていよう。
ウィリアムズはジャーナリストとして、中国側に立って日本非難の合唱をしている国々の姿勢に、徹頭徹尾プロパガンダを見ている。それがまやかしであるのは、彼が極東の
戦場をつぶさに見て歩いた体験からはっきり分っていたのだ。
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1583936b.847a7192.1583936c.2d77a722/?me_id=1213310&item_id=13442570&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F4673%2F9784829504673.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F4673%2F9784829504673.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
