アメリカの対米政策を読み解く
日本はアメリカに虐められた。
東京大空襲や原爆によって一般国民が惨殺されたにもかかわらず、「原爆投下は日本に敗戦を決意させたから悪いことではなかった」「日本がアメリカに戦争を仕掛けたんだから自業自得だ」というスタンスの日本国民もいる。
自分の親や家族が戦争の犠牲になっていてもそう言えるんだろうかと思う。学校でも「日本が悪かった」と教えられたし、南京大虐殺問題や従軍慰安婦問題などでも日本が攻められているが、日本を貶めようとしている流れがあることに気づいた。
それらが占領期のアメリカや、その後それを利用した中国・韓国などによるプロパガンダだということを暴く資料が出てきたようで、それを紹介する書物も沢山ある。
本書もその一つだ。
著者が多くの資料を読み込むことによってたどり着いた歴史観は歪められた近現代史を正すものであり、これまでの東京裁判史観のような歴史観からすれば、それは歴史修正主義史観とのレッテル貼りたくなるものなのだろう。
しかし、そんな揶揄を跳ね返す資料と推論で
本書はアメリカの対日政策をテーマとして各紙に発表された論考や著者が訳した著作のあとがき等をまとめたものであり、対日政策を読み解くための入門書・ガイダンスと言っていいかもしれない。
著者は読者が本書を批判的に読んで、自問することを勧めている。
「ルーズベルトはなぜハル・ノートの存在を真珠湾攻撃前も、その後も議会や国民に隠したのか」
「イギリスがドイツと同様にポーランドに侵攻したソビエトに宣戦布告しなかったのはなぜか」
「ルーズベルトを擁護する歴史家は政権に計り知れない影響を与えたソビエトのスパイや容共派高官の影響になぜ触れようとしないのか」。
私は歴史には疎くまだ分からないことだらけだが、歴史修正主義というプロパガンダ用語に誤魔化され怯むことなく、誤った歴史解釈は改めるという真摯な態度を持ちたいと思った。
渡辺惣樹さんの「アメリカの対日政策を読み解く」 を紹介するために、以下に目次や目を留めた項目をコピペさせていただきます。
興味が湧いて、他も読んでみたいと思ったら、本書を手にしていただければと思います。
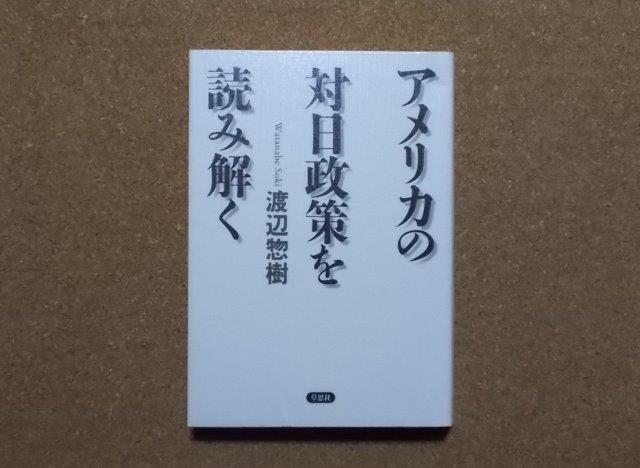
目次
はじめに 日米関係を新たな文脈で読み解く時が来た
Ⅰ日米衝突の謎 15
日米戦争の知られざる「原点」--フィリピンと対日外交 17
『日米開戦の人種的側面 アメリカの反省1944」を語る 24
二十世紀初頭のカリフォルニアで始まっていた対日戦争 33
誰が軍縮の努力を無にしたか 43
ケネディ駐日大使に望む。両国の不幸な歴史に学んで欲しい 48
開国から開戦まで、アメリカの変容を追う(「アジア時報」インタビュー) 66
日清戦争 アメリカはなぜ日本を支持し、朝鮮を見限ったか 91
Ⅱアメリカのロジック 95
米国内の「慰安婦」騒動を解決する決定的ロジック 97
「歴史修正主義」と叫ぶレッテル貼り外交との戦い 116
TPP真の狙いは中国と知財保護 49
TPP「自由貿易至上主義」は誤解(「正論」インタビュー) 93
Ⅲ ルーズベルト神話 163
ルーズベルト神話と「ルーズヴェルト・ゲーム」 165
知られざる国家機密漏洩事件――ルーズベルトとチャーチルの密約 184
日米開戦・民事訴訟なら「ルーズベルトは有罪」(「正論」インタビュー) 202
大統領の嘘に対する怒りと悔恨 29
局地戦を拡大させた大統領の得意な性格 224
なぜ戦後アメリカはルーズベルト批判を許さないのか 229
Ⅳ 干渉主義外交の代償 237
ベトナム戦争終結、建国二百年、「世界の警察官」への疑義 239
岸信介はなぜ“安保反対”に怯まなかったのか 247
ヒラリー・クリントンを悩ますもう一つのスキャンダル 255
干渉主義外交(ヒラリー外交)は修正されるか 268
ドル覇権に挑むプーチンの資源戦略 280
あとがき 劣勢に向かうアポロジスト(釈明史観主義者)の歴史観 285
アメリカのロジック から
P104 日本を貶める情報戦争
日本人は野蛮でずるい民族であると訴えたいグループのひとつに反捕鯨団体があることはすでに述べた。もちろんそういったグループはこれだけではない。いわゆる「南京大虐殺事件」を使って反日本人プロパガンダ工作を続けるグループも存在する。歴史書の体裁をしたプロパガンダ本、アイリス・チャン著The Rape of Nanking(和訳「ザ・レイプ・オブ・南京」)はいまだに書店の棚に並んでいる。
著者のアイリス・チャンは北米各地で講演活動を繰り広げていた。わが町の有力大学でも講演していた(ブリティッシュ・コロンビア大学、20036年3月)彼女は2004年11月にピストル自殺を遂げている。しかし、南京で日本軍が30万人を超える虐殺をしたと主張する政治グループは、彼女を殉教者として聖人化する活動を維持しているのである。
いわゆる「南京虐殺事件」についてのプロパガンダ情報戦争では、日本は劣勢を強いられでいる。
欧米の歴史家はもはや数十万規模の虐殺や大量の強姦事件があったと、疑いもしない。たとえば、ニーアル・ファーガソン教授(ハーバード大学)は、金融史経済史の分野では評価が高く、私も彼のこの分野の作品を文献として使用している。しかし戦争問題を扱った歴史書(「世界の戦争 憎しみの時代」2006年)は史書としては疑問符が付くものである。
彼はこの書で6ページ半を費やして「南京虐殺事件」を描写している。
「犠牲者の数は26万人と推定されている」(477頁)
「南京攻撃で忘れてはならないのは強姦である。(中略)8千人から2万人の女性が強姦されたと推定されている。アメリカ人宣教師のジェームス・マッカラム(James McCollum)は、一晩で少なくとも千人の女性が強姦されたとしている」(477-78頁)
この問題については、ファーガソンは歴史家として失格である。彼はこうした数字について強い疑義が呈されていることに全く言及していない。おそらく事件について懐疑的な文献には一切目を通していないのではないかと思われる。文献リストには「ザ・レイプ・オブ・南京」が挙げられている(663頁)のだが、同書は歴史家のプライドがあれば出典に挙げるのを躊躇う代物である。
ファーガソンは南京で実際に強姦したという元日本兵Azuma Shiroの証言も載せている。Azumaは「女性をレイプすることはお咎めなしだった」「強姦した女は刺し殺した。殺せばしゃべりはしない」と証言しているという。(479頁)。このAzuma Shiroなる人物の述べた言葉の出典が明示されていないので確定できないが、恐らく東史郎のことだと思われる。本誌の読者であれば、すぐにぴんとくる人物である。ファーガソンは、東が「中帰連」(中国帰還者連絡会)の幹部であったこと、つまり戦後、中国・撫順戦犯管理所で思想教育を受けた人物であることには何の言及もせず。一介の元兵士の発言として記述しているのである。
これが欧米の「一流」歴史家の現実である。ファーガソン教授はタイム誌で「世界で最も影響力のある100人」(2004年)に選出されている。
P106
危うい「慰安婦像問題」
ここで表題の「慰安婦像問題」に話を戻す。 外国に暮らす多くの日本人にとって、とりわけ北米西海岸に暮らす日本人(日系人)にとって、ロサンゼルス市近郊の町グレンデールの公園内に「慰安婦像」なるものが設置されたことは不快の極みである。かつて日本人強制収容の引き金になったのは、「日本人は北米社会に同化できない劣等“人種”である」とする思想であった。
あのような異形な少女像を見て、日本人という人種そのものが獣のような性格であるなどと再び誤解されたら、悪夢のような日本人排斥運動さえ勃発するかもしれない。外国に暮らす日本人は、韓国のファナティックなロビー活動に不愉快な思いを抱き、強く憤っている。日本政府が毅然とした態度を見せないことにも苛立っている。
私の暮らすバンクーバーは、同市周辺を含めるとおよそ230万の人口を抱えている。そのうちの4万6千人(2.2%)が韓国系である。日系の3万人(1.4%)を大きく上回っている。いつグレンデール市の二の舞にならないとも限らないのである。
この町に暮らす韓国系の人々は狂信的ではないと信じてはいるものの、万一に備えなければならない。グレンデール市のような動きが始まったら、私たちは直ぐに行動を起こさなければならないと考えている。私たちはメディアを含む白人社会に対して、どのようなロジックを使って訴えたらよいのだろうか。そのことを予め考えておく必要がある。
実は、私はその訴えの作業はそれほど難しくはないと考えている。正しいロジックで白人社会に訴えれば、案外簡単に理解してもらえるのではないかと考えている〔注:バンクーバーに隣接するバーナビー市にあるセントラルパークヘの慰安婦像設置計画が2015年に持ち上がったが、日系人の抗議の結果、中止となった〕。
P108
“クロス(反対尋問)”に晒されない証言は無価値
私は従前から「河野談話」はかなりいい加減な証言を根拠にした、外交的配慮の下に発せられたものであろうと疑っていた。産経新聞が「河野談話」の基礎となる、いわゆる「慰安婦」証言の実態をスクープ(2013年10月16日)したことで、私の疑義は妥当だったと確信するにいたった。
私か確認したかったのは、「慰安婦」であったと証言する女性に対して「クロス(=反対尋問 Cross examination)」がなされたか否かであった。
彼女たちの主張は、かつての日本が罪を犯したと訴えるものである。その主張は極めてシリアスである。したがって、日本に対する糾弾は法のルール(ロジック)に則るものでなくてはならない。
そのルールは法廷の場だけの特殊なものではない。法廷外における論争にも適用される。韓国は日本国民に対して謝罪と金銭を要求している。ならば法の精神に則った適正な議論(Due Process)があって当然だ。
証言が証拠として価値を持ち得るためには、その証言が「クロス=反対尋問」に晒されなければならない。それは法理論の基本中の基本である。私は「河野談話」発表にいたる過程で、彼女たちの訴えに対する反対尋問、あるいはそれに類似のプロセスは踏まれていないだろうと推察していたが、それが間違いないことが産経新聞のスクープで明らかにされたのである。私の言う「反対尋問」とは、彼女たちの人格を否定する作業ではない。証言に矛盾はないか、嘘がないか、伝聞証言ではないか、そうしたことを厳格にチェックするプロセスである。
この問題で挙証責任(Burden of proof)があるのは韓国側である。日本にはない。したがって、韓国側か提出する証拠を吟味し、証言の信憑性についてその証言者に「クロス=反対尋問」するだけでよい。こちらから「なかった証明」などしなくてよい。それを証明したかったらすればいいが、その行為はあくまで外交的配慮によるものであって、日本側には挙証責任はない。それが大原則である。「売春婦」ではなく「性奴隷」であったと訴えたければ、挙証責任はあくまでそれを主張する女性の側にある。
日本は、あの時代に公娼制度があったことは否定していない。ただし、あの吉田清治のファンタジー(注:軍命令による女性誘拐等だが、自らが慰安婦狩りの当事者だったという「吉田証言」を16回にわたって記事にしてきた朝日新聞は、2014年8月、同証言を虚偽と判断して、すべての記事を取り消した)のような事件などありはしなかった。もちろん性奴隷など存在しない。「それを示す証拠も、信ずるに足る証言もない」。そう反論し、どっしり構えていればよいのである。アメリカではネバダ州の一部の地域で売春は依然合法である。当時、売春が合法であったということを理解することはそれほど難しいことではないのだ。
産経新聞の報道にあるように、「慰安婦」だったと名乗りをあげた女性からの聞き取り調査は「杜撰」であった。しかし北米社会では「杜撰」という言葉での説明は意味をなさない。「杜撰」とは何か、その本質を明示する必要がある。その本質とは、前述のように「慰安婦証言はクロス(反対尋問)がなされていない。したがって無価値である」ということなのである。北米はアメリカでもカナダでも陪審制度が根付いている テレビでは裁判のドキュメント物が人気である。証言が「証拠価値のある証言」たり得るには「クロス(反対尋問)」のプロセスが必須であることは、一般人でさえ理解している。ハル・ノートの存在を知らない一般人でも、このことはよくわかっているのだ。
万一カナダで「慰安婦像」設置の動きがあれば、「クロスのなされていない証言」を証拠として採用しろというのか」と反論すればよいのである。
P135 歴史学の限界を理解した歴史論争の必要性
これまでの議論で、日本の「史実をベースにした歴史の見直し」にポジティブに働く空気がアメリカに芽生えていることは理解していただけたと思う。さてそれでは、いかなる方法で日本の主張を発信していくべきなのだろうか。
多くの読者には言わずもがなであるが、歴史家の叙述はあくまでも過去の記録や証言をもとにしての「確からしい記述」でしかない。一次資料であるとされる日記にも後で誰かに読まれることを想定した悪意の記述もある。現場にいた人物でさえ思い違いもあるし、利害関係があれば敢えて嘘を語ることもある。したがって、歴史家は、できるだけ多くの資料を検討しながら、そこから浮かび上がった「正しさらしさ」に基づいて叙述するしかない。法律用語を援用するなら、「証拠の比較衡量」基準(証拠の優越基準)(Preponderance of Evidence)に沿って、過去の事件を描写するということである。相反する記録などを丹念に読み解き、その上で自ら信ずる歴史解釈を提示する。歴史家にできるのはこの作業だけである。
それでは、日本を貶めるために利用されている二つの大きな事件(「南京大虐殺」「性奴隷としての慰安婦」問題)は、いったいどのような記述がなされているのだろうか。
後者の慰安婦についてはすでにワシントン・ボストの記事を紹介した。一方の「南京大虐殺」事件については、イギリスの歴史家ニーアル・ファーガソン(1964年生れ)の「世界の戦争」(2006年)が参考になる。ファーガソンは2004年にタイム誌が世界で最も影響力のある百人に選んだ歴史家である。同書には「強姦」とタイトルされた節があり、5頁半(475-80頁)にわたって日本軍による凄惨な強姦の悪行が描写され、およそ5週間半で26万人の民間人が殺されたと書いている(477頁)。また南京攻略戦の過程で報じられた「百人斬り競争」が事実として語られている。
ファーガソンに常識があれば、一日当たり6500人も殺した後、死体はとうしたのか、なぜ虐殺が始まっても二十数万人の市民は先を争って逃げなかったのか、写真は残っているのか、などの疑問が湧くはずである。しかし彼がそのような作業をした形跡はない。この書の副題は「憎悪の世紀」(History's Age of Hatred)であり、このテーマを補強するには格好の「残虐事件」だったからである。
南京事件についての歴史家の描写の例をもうひとつ挙げる。中国人作家ユン・チアンの毛沢東の伝記(2005年)にある一節である。
「南京でとんでもない虐殺かあった。民間人、捕虜併せて30万人が日本軍により殺されたと推定されている。毛(沢東)はこの事件についてその時点でもその後も何も語っていない」
チアンのこの書は毛沢東の非道ぶりがテーマであり「日中戦争最大の悲劇であった事件」に毛沢東が何の感情も示さないこと、つまり彼の冷酷さを描くために「南京大虐殺」を取り上げたのである。「30万人虐殺」は彼女にとってはアプリオリな歴史的事件である。二カ月足らずで30万を殺すことがあり得るのか、もしそんなことがあれば動機は何か。なぜ南京だけでそんな事件が起きたのか、などという疑問は浮かばないらしい。私は、歴史家は過去の事件や人物を断罪する場合には十分に慎重でなくてはならないと考えている。自説を補強するために都合のよい事件を無批判に使う手法を取らないよう戒めながら執筆している。
歴史描写は先に書いたように「証拠の比較衡量」の作業であるだけに、歴史の裁判官にも相当する歴史家が、証拠の存在を知らなかった、あるいは知っていても無視してしまえば、都合のよい証拠だけで歴史的事件や人物を断罪することは容易である。残念ながらこれが歴史学の限界なのである。
プロパガンダとしての歴史記述も歴史学の限界として避けられないと納得してしまうことは、敗北主義として非難されるかもしれない。しかし、繰り返しになるが、歴史記述があくまで「証拠の比較衡量」であり、歴史家自身が裁判官であるという歴史学の本質がある以上、何ともしようがないのである。「南京事件」も「慰安婦問題」も日本を貶めることに何らかの利益を感じる勢力によるプロパガンダによって真実が大きくねじまげられていると考える。歴史家にとっては、比較衡量の材料となる新たな証拠を提示したり、根拠となっている証拠に対して疑義を提示していく作業を地道に続けていく以外に方法はない。
30万人という数字は一日に8千人近い民間人や捕虜の殺戮に相当する。これだけの数の人間を殺し、死体を処理することが可能か。ましてや少なくない西洋人カメラマンの目を盗んでそれを実行しなくてはならない。その上、これだけの大量殺戮を見ても逃げ出そうとしない民間人などいるのか。こうした疑問を提示すれば、常識ある人間ならその虚構性はすぐにわかる。南京事件に詳しい東中野修道教授らによる南京事件の証拠写真の分析(「南京事件 証拠写真を検証する」草思社)で、証拠とされる写真そのものにも捏造があることがすでに論証されている。こうした研究成果を発信する作業も重要だ。
先に紹介したニーアル・ファーガソンの書には出典が示されているが、そのうちの一つは日本車兵士だった東史郎(Azuma Shiro)という人物の証言である。(「世界の戦争」479頁)
「支那人の女は下着をつけていない。ズボンのようなものを紐で結んで留めているだけだ。我々は紐をほどき、彼女たちの下腹部を見た。その後、やってしまえと次々に強姦した。強姦した女は必ず刺し殺した。死体は何もしゃべらない。」
ファーガソンが引用した証言の主である東史郎は、中国からの帰還兵で組織した中国帰還者連絡会(中帰連)の幹部である。中帰連は中国政府のプロパガンダ組織の性格が濃厚な団体であり、東の証言本が捏造であることは、彼が名誉棄損裁判で敗れていることからも明らかだ。ファーガソンの書には、東史郎なる人物にいかなる思想的背景があるか示していない。ファーガソンはその名声とは裏腹に、南京事件について真摯に研究した形跡がない。ここでも、戦争は悲惨なものだという主張を補強するために資料のつまみ食いをしていることが知れる。それでも、日本の研究者が「東史郎なる人物は善意の証言者ではなさそうだ」という疑問を提示することには大きな意味がある。
ルーズベルト神話 から>
P21P213 大統領の嘘に対する怒りと悔恨
日米戦争の原因を冷静に遡ればヨーロッパで始まった戦争(1939年9月)に起因していることは問違いない。そのヨーロッパの戦いの原因はドイツとポーランドの、バルト海に面した港町ダンツィヒの帰属をめぐる争いだった。もともとドイツの前身であるプロシア領であったダンツィヒは、ベルサイユ条約(1919年)によって独立したポーランドが外交権を得たことで「自由都市」となり、ドイツから分断されたが、そこに暮らす90%の住民はドイツ系であった。
ヒトラーはポーランドに対してダンツィヒの返還を要求した、そしてドイツ領から飛び地になっているこの港町へのアクセス権(ポーランド回廊問題)を要求した。ウッドロー・ウィルソン米大統領が第一次世界大戦後のパリ講和会議で主張した民族自決原則からすれば、ヒトラーの要求に埋があると考える政治家はイギリスにもアメリカにも多かった。機甲化されたドイツ陸車とその航空戦力を考えたら、ポーランドはドイツとの外交的妥協を求めた方が賢明である。多くの政治家はそう考えた。本書「ルーズペルトの開戦責任」の著者であり、当時下院議員をつとめていたハミルトン・フィッシュもそうした政治家の一人であった。
ドイツにとって、ダンツィヒ帰属問題の解決は、過重な賠償をはじめ、敗戦国ドイツに対するベルサイユ条約の不正義からの回復運動の完成を意味した。これによってドイツ国民の恨みは解消できるはずであった。フィッシュらは、ヒトラーのナチス政権はダンツィヒ帰属問題を終結させ次第、その矛先をソビエトロシアに向けると考えていた。2つの全体主義国家は必ずや壮絶な戦いを始めるだろうとみていたのである。ヒトラーは、何度もダンツィヒ問題の外交的解決を図ろうとしていたし、同時に、英仏とは戦いたくないというメッセージを発していた。
ドイツは第一次世界大戦ではイギリスの海上封鎖に苦しんだ。食料不足で多くの国民が餓死し、それが社会主義者の跋扈の呼び水となり内部から崩壊した。ヒトラーが、第一次大戦の苦しみの記憶から、食料も石油資源も豊富な東(ウクライナ方面)を目指すだろうと多くの政治家は予想していた。だからこそ、彼らの外交常識からすれば、ポーランドはドイツと妥協し、場合によってはドイツに協力して共に東進するオプションもあるはずだった。ソビエトはポーランドにとって十分に危険な国であった。しかし、ポーランドはなぜか意固地にヒトラーの要求を拒否した。
ポーランドの頑なな外交姿勢に業を煮やしたヒトラーが、犬猿の仲であったソビエトと独ソ不可侵条約(1939年)を締結したのは、ポーランドの強硬姿勢の背後にイギリスとフランスがいることを確信したからであった。ポーランドの独立維持は英仏の安全保障になんの関係もなかった。
ダンツィヒをドイツ領に戻したとしても、英仏の安全が脅かされるはずもなかったのである。
ハミルトン・フィッシュは第一次世界大戦に参戦した。黒人部隊(第369連隊:通称ハーレム・ヘルファイターズ)に属する。一中隊(K中隊)の指揮官として戦った。死を覚悟した激戦の中を運よく命拾いして帰国できた。それだけに、第一次大戦後に出来上がったベルサイユ体制の不正義に敏感であった。アメリカの伝統に反してヨーロッパのいざこざに介入した結果が、ベルサイユ体制であった。ベルサイユ会議での国境線引きはとても公平とはいえなかった。ヨーロッパ各地に憤懣の火種を撒き散らした。ダンツィヒ帰属問題はその典型であった。
アメリカ国氏の多くが、ダンツィヒ帰属問題で、英仏がなぜドイツに宣戦布告したのか理解できなかった。英仏はポーランドに対して、その独立を守るためにもドイツとの妥協点を探るべきだとアドバイスすべきではなかったのか。アメリカ国民は、英仏がいったい何を目的にドイツに宣戦布告したのか皆目見当がつかなかった。
戦争目的のわからないヨーロッパの戦いに、参入したいと思う国氏がいるはずもない。ヨーロッパでの戦端が開いても、アメリカは介入すべきではないと考えるものがほとんどだった。8割以上の国民だけでなく、与党民主党が圧倒的多数のワシントン議会でさえも75パーセント以上の議員が非干渉を主張していたのである。1940年の大統領選挙では、フランクリン・デラノ・ルーズベルト(FDR)ら大統領候補はヨーロッパ問題への非介入を公約とせざるを得なかった。ルーズベルトは投票日(11月5日)直前のボストンの演説で次のように訴えた。
私はこれまでも述べてきたように、そしてこれから何度でも繰り返すが、あなた方の子供たちは外国の地での戦争に送り込まれることはけっしてない(1940年10月30日)。
ヨーロッパの戦いに介入したいルーズベルトは参戦のための準備を進めていた。それについては「アメリカはいかにして日本を追い詰めたか」の中で詳述したのでここでは詳しく触れないが、端的に言えばルーズベルトはニューディール政策の失敗による経済的打撃から回復したいがために参戦を考えていたのである。これをより深く論証するにはルーズベルトとニューヨーク金融資本家との関係を探らなければならない。すでにアメリカにはいくつかの優れた研究がある。それについては機会をあらためて紹介したいと考えている。いずれにせよ、アメリカが参戦する制度的準備は整っていた。しかし圧倒的な、ヨーロッパ問題非干渉を願う世論を前にルーズベルトは身動きがとれなかった。
1940年9月に発足したアメリカ第一主義委員会は、防衛力の強化には理解を示しながらも、アメリカ自身が攻撃されない限り、ヨーロッパの戦いにアメリカの若者を送ってはならないと主張し、全米各地に支部を設け、その会員数は80万を超えていた。アメリカ第一主義委員会のスポークスマンの役割を果たしていた飛行冒険家チャールズ・リンドバーグはマジソンスクエアガーデン(二ユーヨーク)やソルジャーフィールド飛行場(シカゴ)で演説し、集まった数万人の聴衆を熱狂させていた。
われわれはこれまでに英仏両国が支配するヨーロッパと付き合ってきた。ドイツが戦いに勝利すれば、今度は、ドイツの支配するヨーロッパと付き合えばよいだけの話である。
ルーズベルトは彼らの活動に苦虫を噛みつぶしていたのである。
こうしてアメリカ国内ではヨーロッパ問題非干渉の強い世論が形成される中で、日本の真珠湾攻撃が起こる。1941年12月7日早朝(ハワイ時間)のことである。アメリカ国民は、ルーズベルト政権の対日外交などには関心はなかった。ヨーロッパでの現在進行形の戦いだけに目を向けていた。アメリカ国民にしてみれば後ろから鈍器で頭を殴られた感覚であった。日本の在米資産の凍結も、対日石油禁輸にも強い関心はなかった。ましてや、日米戦争の危機感を強めた近衛文麿首相がルーズペルトとの直接会談を望んでいることも、最後通牒の性恪を強く持ったハル・ノートが日本に手交されていたことも知りはしなかった。
ルーズベルト大統領が、日本に対して宣戦布告を議会に求めたのは真珠湾攻撃の翌日のことであった。その演説は次のようなものであった。
昨日すなわち1941年12月7日、わが国は大日本帝国の海軍空軍兵力によって突然の、かつ入念に計画された攻撃を受けた。12月7日はわが国の「恥辱の日」として記憶されることになろう。
わが国と日本は平和状態にあり、同国政府および天皇と、太平洋方面における、和平維持に向けで交渉中であった。
実際、日本の駐米大使らは、日本の航空隊がオアフ島攻撃を開始してから一時問後に、直近のわが国の提案に対する公式回答を国務長官に手交したのである。これ以上の外交交渉の継続は無益であると述べられているが、戦争行為あるいは武力行使を示す言葉は含まれていなかった。
日本とハワイの距離に鑑みれば、この攻撃には何日もの、いや何週問もの周到な準備があったことは明白である。そのことはしっかり記憶されなければならない。この間に日本は、和平の継続を望むという姿勢を見せて、わが国を欺いたのである。昨日のハワイ諸島への攻撃で、わが海軍及び陸軍は甚大な損害を被った。残念であるが、多くの国民の命が失われた。加えて、ホノルルとサンフランシスコを結ぶ公海上でも、わが国の艦船が魚雷攻撃を受けたとの報告があがっている。
作日、日本はマレーを攻撃した。昨晩香港を攻撃した。フィリピンを攻撃した。ウェーク島を攻撃した。そして今朝、ミッドウェー島を攻撃した。
日本は太平洋全域にわたって奇襲攻撃を実行したのである。昨日そして本日の日本の行動が何を意味するかは自明である。わが国民はすでに意思を固めた。(日本の攻撃が)わが国の生存と安全にどのような意味を持つか理解している。
私は陸海軍の最高司令官として、わが国の防衛のためにできることはすべて実行に移すよう命じたところである。われわれは、わが国に対して行われた攻撃の(卑怯な)性格をけっして忘れることはない。
(拍手)
日本の入念に準備されたわが国への侵略に対する戦いに、どれほどの月日が必要であっても、正義の力をもって完全なる勝利を実現する。
(拍手)
われわれは全力で国を守り抜かなければならない。そして二度とこうした欺瞞に満ちた行為によってわが国の安全が脅かされてはならない。私は(日本の攻撃にいかに対処するかについて)どのような思いを国民とそして議会が持っているか、十分に理解していると信じる。(中略)
私は議会に対して、1941年12月7日日曜日の、挑発されていないにもかかわらず、わが国を卑劣にも攻撃した事実をもって、合衆国と大日本帝国は戦争状態に入ったことを、宣言するよう求める。 (拍手)
このルーズベルト演説に肯定的に応えたのが、ヨーロッパから帰国後下院議員に選出され、野党共和党の重鎮の一人になっていたハミルトン・フィッシュ議員であった。彼はアメリカ第一主義委員会の主張に賛同していた。その彼がルーズベルトに続いて次のように演説し、議会に対して、対日宣戦布告容認を訴え、ルーズベルト大統領支持を呼びかけたのである。
私は(日本に対する)宣戦布告を支持するためにこの演台に立たねばならないことを悲しく思う。そして日本に対して腹立たしい気待ちで一杯である。私はこの3年問にわたって、わが国の参戦にはつねに反対の立場をとってきた。戦場がヨーロッパであろうが、アジアであろうが、参戦には反対であった。
しかし、日本海軍と航空部隊は、不当で、悪辣で、恥知らずで、卑劣な攻撃を仕掛けてきた。
日本との外交交渉は継続中であった。大統領は、日本の天皇に対してメッセージを発し、ぎりぎりの交渉が続いていた。日本の攻撃はその最中に行われたのである、このことによって対日宣戦布告は不可避となった。いや必要になったのである。
参戦の是非をめぐる議論のときは終わった。行動するときが来てしまった。
干渉主義者もそうでない者も、互いを非難することをやめるときが来た。今こそ一致団結して、大統領と、そして合衆国政府を支えなければならない。一丸となって戦争遂行に邁進しなければならない。日本の(信義を裏切る)不誠実なわが国への攻撃に対する回答はただ一つ。完全なる勝利だけである。われわれは血も涙も流さればならないだろうし、戦費も莫大になろう。しかし、日本による一方的なわが国領土ヘの攻撃に対しては戦争によって対処するしかなくなった。
私は再三再四、外国での戦争にわが国が参戦することに反対を表明してきた。しかし、わが国が攻撃された場合、あるいは合衆国議会がアメリカの伝統である憲法に則ったやり方で宣戦を布告するなら、大統領および合衆国政府を最後の最後まで支援しなければならない。
日本民族は、神が破壊せしもの(民族)に成り果てた。日本人は気が違ってしまったのである。
一方的な軍事攻撃を仕掛けてきたが、これはまさに国家的自殺行為である。私は先の大戦で志願して戦った。このたびの戦いにも時期をみて志願するつもりである。そして今度も黒人部隊に入って戦いたいと考えている。
国を守るためにはどんな犠牲を伴っても致し方ない。気の触れた悪魔のような日本を完膚なきまでに叩き潰すためには、どのような犠牲であれ大きすぎることはない。
戦いの時は来た。手を携え、常々とアメリカ人らしく戦いを始めよう。そしてこの戦争は、たんにわが国に向けられた侵略に対する防衛の戦いというだけではない。世界に、自由と民主主義を確立するための戦いであることを知らしめよう。勝利するまで、わが国はこの戦いをやめることはない。
国民に、そしてとくにわが共和党員や非干渉主義を信条とする考たちに訴える。今は信条や党派を超えて大統領を支えるときである。最高指揮官の大統領を支え、わが軍の勝利に向けて団結するときである。
わが国の外交はつねに正しくあれ。万一問違っていることがあろうとも、アメリカは祖国なのである。
こうして日米戦争が始まった。この4日後の12月11日にはヒトラーは国会で演説し、アメリカに宣戦布告した。ヨーロッパの戦いはアメリカとアジアを巻き込んだ世界大戦となったのである。
フィッシュが対日戦争を容認したことでアメリカ第一主義委員会の活動は停止した。
ルーズベルトは1944年の選挙でも勝利(4選)すると、ドイツと日本の敗戦後の世界の枠組みをチャーチルとスターリンとの間で話し合った(ヤルタ会談:1945年2月)。それは世界の半分を共産化することを暗黙に認めたもので、自由主義諸国への裏切りであった。チャーチルは参加していたものの、ルーズベルトを手玉に取るスターリンに何の抵抗もできなかった。戦争の始まりがポーランドの自由と独立の保特にあったことなどもはやどうでもよいことだった。そして、その会談のわずか二力月後にルーズベルトは世を去ったのである。
ルーズベルトにとって、その立場を変えてまで対日宣戦布告を容認したフィッシュには恩があるはずだった、しかし、かねてからフィッシュがルーズベルトの進める経済政策(ニューディール政策)を批判し、ルーズベルトの恫喝的政治手法を嫌っていたこともあって、ルーズベルトは彼を政治の世界から葬ることを決めた。1944年の下院議員選挙で、フィッシュの選挙区の区割(ニューヨーク州)を変更させ、フィッシュの選挙が不利になるよう、ニューヨーク州に圧力をかけた。
典型的なゲリマンダーの手法であった。その結果フィッシュは敗れた。
ルーズベルトの死後、彼の対日外交の詳細と日本の外交暗号解読の実態が次第に明らかになり、ハル・ノートの存在が露見すると、フィッシュは臍をかんだ。窮鼠(日本)に猫を噛ませた(真珠湾攻撃)のはルーズベルトだったことに気づいたのである。彼は、対日宣戦布告を容認する演説を行ったことを深く愧じた。彼は、ルーズベルトに政治利用され、そして、議席を失ったのである。
ルーズベルト外交の陰湿さが戦後の研究で明らかになると、フィッシュのルーズベルトヘの怒りは日に日に増していった。しかし、彼は自重した。母国アメリカが世界各地で共産主義勢力と対峙している現実を前にして、既に世を去っていたとはいえ、自国の元大統領の外交の失敗を糾弾することはできなかった。
長い沈黙の末、彼がようやくその怒りを公にしたのがこの書である。上梓された1976年は、真珠湾攻撃からすでに35年が過ぎ、ルーズベルトの死からも31年が経っていた。フィッシュ自身も既に87歳の高齢であった。世を去る前に本当のことを書き残したい。その強い思いで本書を出版したのである。
読者におかれては、あの戦いで命を失ったアメリカの若者の父や母の視点も忘れずに、本書を読んでいただきたい。著者が語っているように、「天使も涙する」ほどの手口でアメリカを参戦に導いた元大統領の政治手法にあきれてしまうに違いない。そして同時に、本書に記されている内容がアメリカの為政者にとって、どれほど都合が悪いかも理解できるに違いない。
本書はルーズベルト外交を疑うことをしない歴史家からは「歴史修正主義」の書と蔑まれている。
「歴史修正主義」という言葉はプロパガンダ用語である。ルーズベルトの政治は正しかったとする「ルーズペルト神話」に挑戦する本書に、「歴史修正主義」というレッテルを貼ることは無意味である。歴史修正の是非は、あくまで真実を探ろうとする真摯な心を持つ者だけに許される判断である。
フランクリン・ルーズペルトが最も嫌い、そして最も恐れた男の語る歴史から何が読み取れるのか。それについては「訳者あとがき」(注:本書239-46頁)で語りたいと考えている。
(『ルーズベルトの開戦責任』「訳者まえがき」草思社、2014年)
あとがき 劣勢に向かうアポロジスト(釈明史観主義者)の歴史観
&nbs 「はじめに」にも書いたように、本書に纏めた論考は、いわゆる「歴史修正主義」と一般には揶揄されている考えに基づいている。「主義」という用語が使われてはいるが、唯物史観のように、ためにする史観ではない。単純に言えば、ルーズベルトやチャーチルの進めた外交を懐疑的に見る史観である。戦前のドイツや日本が格別「良い国」であったとする主張でもない。
ドイツや日本が仮に「悪い国」であったとしても、そこに至る原因にベルサイユ体制の不正義や、日本人への人種差別があったことも見逃してはいけないと考える。二つの「悪い国」の矯正、あの悲惨な第二次世界大戦は不要ではなかったかと考える。大戦を回避していれば新たにソビエトというモンスターは生まれなかったし、冷戦の悲劇もなかったと考える。そういう史観である。
日本ではこのように考えることがまるで倫理的に、”悪”のように思われている。アメリカがそう主張するからである。実はアメリカ国内でもルーズベルトやチャーチルの進めた外交を軽蔑する政治家や歴史家は多いのである。
そうした人物による著作をハーバート・フーバー元大統領が一覧表にしてくれている(「裏切られた自由 Freedom Betrayed」889頁)。執筆者は、歴史家だけではない。ルーズベルトを身近で見てきたジャーナリスト、政権幹部、米軍幹部、ヨーロッパ各国の指導者など錚々たる顔ぶれである。従って、歴史修正主義はけっしてマイノリティーの見方ではない。ただ、ルーズベルトの後に続いた政権(民主党、共和党を問わず)やその意を受けたメディアが、そうした史観の発表を妨害し、その著書を侮蔑した結果、マイノリティーと誤解されているだけである。
フーバーの書にはルーズベルトやチャーチルの外交を是とする書の一覧もある(前掲書888頁)。そうした史観を持つ者は、「アポロジスト(Apologist)」と呼ばれている。「釈明史観主義者」とでも訳すことができよう。執筆者には、歴史家もいるが、チャーチル本大を含め、当時の外交をリードした政府高官やその親族が多い。
私が「アポロジスト」の書を信用しない理由は、明らかに重要だと思われる史実を、意図的か無意識かは知らないが、取り上げないからである。チャーチルの書にそれが特に顕著なことはフーバーが指摘している。アポロジストは、本書でも取り上げたタイラー・ケント事件(ルーズベルト大統領が英国首相に隠れて一介の大臣(海車大臣)であるチャーチルと直接交信を続けていた事件)や、ルーズベルトの抱えた重篤な病を書かない。あるいは、ルーズベルト夫人であるエレノアの左翼思想にも触れようとしない。政権内部に侵入したソビエトのスパイの外交に与えた影響にも目をつむる。
私は、ルーズベルトやチャーチルの進めた外交を批判的に見る歴史観が今後は優勢になっていくと信じている。本年中に、ハーバート・フーバー元大統領が著した「裏切られた自由」を翻訳上梓(思草社)する予定である。この書は、歴史修正主義の集大成である。千頁前後の大著になるが、これまで知られていなかったあの戦争の実態が、膨大な資村をベースに赤裸々に語られている。
「アポロジスト」はますます劣勢に追い込まれることになるだろう。
本書編集にあたり今回も草思社編集部の増田敦子さんと、校正を担当してくれた川鍋宏之さんの協力を得た。この場を借りて感謝の意を表したい。
2016年春 渡辺惣樹
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1583936b.847a7192.1583936c.2d77a722/?me_id=1213310&item_id=16958749&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0622%2F9784794220622.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0622%2F9784794220622.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/151ce07f.831127cc.151ce080.8b13ee84/?me_id=1278256&item_id=17483250&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakutenkobo-ebooks%2Fcabinet%2F9161%2F2000006449161.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakutenkobo-ebooks%2Fcabinet%2F9161%2F2000006449161.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)