国史教科書(市販版)
アマゾンの、本書の特徴を紹介した項目には次のようなものがあります。
面白い教科書を目指しました。楽しみながら学べる「読み物」に仕上がっています。
光と影をバランスよく配置。従来は、日本に誇りが持てるような逸話は教科書にはタブーでした。しかし、日本の歴史には誇らしいこともあったはずです。「光」と「影」をバランスよく配置することで、生徒たちは、悪いことは繰り返さないように、また良いことは伸ばしていこうと思えるはずです。
朝廷を重視した構成 従来の教科書は、政権担当者の政治史が中心でした。しかし、日本には建国以来「朝廷」が存在し、為政者たちは朝廷との関係性により、特色のある政権を構築しました。本書は「天皇」を軸に、為政者たちが天皇・朝廷とどのような関係を築くことで権力を掌握したか、その権力構造と特色を深く理解できる作りになっています。
国史教科書編纂委員会の「国史教科書(市販版)」を紹介するために、目を留めた項目をコピペさせていただきます。
興味が湧いて、他も読んでみたいと思ったら、本書を手にしていただければと思います。
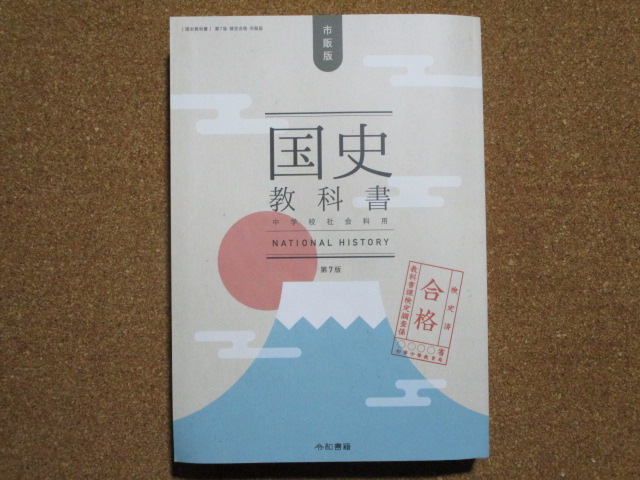
 アマゾンで購入
アマゾンで購入
二・二六事件と盧溝橋事件 P361~P364
<課題>大陸での戦線はなぜ拡大したのだろう。
昭和11年(1936)2月26日、陸軍の一部の青年将校が決起する二・二六事件が起きました。皇道派と呼ばれる青年将校らは昭和維新の目標を掲げ腐敗する資本家、重臣、軍閥などに天誄を下すことで、天皇親政を実現しようと決起したのです。決起部隊は、岡田啓介首相ら多くの閣僚を襲撃し、総理大臣官邸、陸軍省、参謀本部、警視庁、東京朝日新聞などを占拠し、軍首脳を通じて昭和天皇に昭和維新断行を訴えました。政府と統帥部の上層部には青年将校らに同情的な意見が多かったのですが、昭和天皇は「速かに暴徒を鎮圧せよ」と命ぜられ、反乱は鎮圧されました。
この事件の結果、軍の皇道派は力を落とすも統制派が力を強め、政治への関与を強めていきます。事件後
に成立した広田弘毅内閣は、しばらく廃止されていた軍部大臣現役武官制を復活させました。陸軍大臣と海
軍大臣は現役の軍人でなければならないという制度です。これによって、内閣の決定に対して、軍が事実上の拒否権を持つことになったのです。軍が大臣を出さないと、組閣を阻止できることになりました。
そして翌昭和12年(1937年)7月7日、盧溝橋事件が起きました。当時、北京には、明治33年(1900年)に起きた義和団事件以来、条約に基づいて日本車が駐屯していました。北京郊外の盧溝橋付近で夜間演習をしていた日本軍が何者かの銃撃を受け、翌8日夜明けに国民革命軍の陣地を攻撃して両軍の戦闘に発展しました。この事変が起きると、早期解決を目指す不拡大派と、これを機に国民革命軍を屈服させようとする拡大派が対立しました。満州の関東軍は国民革命軍に一撃を与えるべく、一部の兵力を山海関に集めました。まもなく現地では停戦協定が成立しますが、近衛文麿首相は華北への大規模な出兵を決定しました。
関東軍が南下すると蒋介石との緊張は高まり、日本軍は7月末に華北での攻撃を開始しました。8月に上海で戦端が開かれると、近衛首相は不拡大方針を放棄して全面戦争に突入しました。この事変の名称は「支那事変」と閣議決定されました。このときも、双方がいずれも宣戦布告していないので「事変」と呼びました。現在では日中戦争(日華事変)と呼びます。
また、事態が拡大した一つの要因として、7月29日未明に起きた通州事件が指摘されます。冀東(きとう)防共自治政府の保安隊(中国人部隊)が日本軍守備隊と通州特務機関と日本人居留民を襲撃した事件です。保安隊は日本軍110名を全滅させると、日本人居留民の家を一軒残らず襲撃し、385中、223名を虐殺しました。しかもその虐殺方法があまりに猟奇的で、日本中を震撼させました。反乱は一日で鎮圧され、自治政府が謝罪し、慰謝料が支払われて解決しましたが、日本では過大に宣伝されたため強硬論を後押ししました。
当時、陸軍参謀本部作戦部長だった石原莞爾は、不拡大を主張しましたが、作戦課長の武藤章が強硬路線を主張したため、参謀本部をまとめられませんでした。
9月には内戦で戦っていたはずの蒋介石率いる国民党と毛沢東率いる共産党が「抗日」で手を結び、抗日民族統一戦線が発足しました。日本軍は12月に、南京国民政府の首都である南京を陥落させましたが、蒋介石率いる国民革命軍は内地の重慶に拠点を移し、長期戦にもつれこんでいきます。国民政府は、アメリカ、イギリスなどの支援を受けて抗日戦争を継続しました。
ところで、終戦後の極東国際軍事裁判(東京裁判)で、南京占領期間中に日本軍が20万人以上の住民を
虐殺したと認定されました(南京事件)。現在の日本の学界では、虐殺の人数について、10数万~20万人、4~5万人、1万人前後、捕虜などの不法殺害は2万人近くだったが民間人の殺害は数千人、といった学説が示されていますが、定説はありません。これに対して中華人民共和国政府は、30万人以上の虐殺があった
と主張しています。
当時、国民革命軍の軍人の多くが民間人に扮して便衣兵と呼ばれるゲリラ兵となって民間人を人質に立て龍もり、あるいは敵対行為をしていました。これは国際法違反でした。逮捕され処刑された便衣兵も多く、これを「虐殺」と指摘されている可能性もあります。
また、日本軍入城時の南京の人口は20万人程度でしたので、30万人を虐殺することは不可能です。また、日本軍が南京を占領してから1ヵ月後には人口が5万人増加していますが、大虐殺の直後に5万人が移住してくるわけがなく、30万人大虐殺の根拠はいまだ示されたことかありません。
ポツダム宣言と原爆投下 P390~P392
<課題>ポツダム宣言の意図は何だったのだろう。
原爆投下はどのような被害をもたらしたのだろう。
(昭和20年)7月25日、トルーマン大統領は、日本に2つの原爆を投下するように命じました。一発目を投下して日本が降伏しなかったから、仕方なく二発目を投下したという事実はありません。ところで、アメリカは原爆を2発しか所有していませんでした。
7月26日、日本に対する降伏勧告であるポツダム宣言が出されました。当初、アメリカ政府案には、天皇の地位を保障する文言がありましたが、調印直前に、大統領はその一文を削除しました(文献史料「ポツダム
宣言」参照)。大統領に助言する高官たちは、すでに日本は和平に向けて動きはじめていて、この一文を入れることで日本は確実に降伏すると分析していました。実際にアメリカ政府の分析は正しく、日本の政府と統帥部は天皇の地位の保障を終戦の絶対条件と考えていました。ポツダム官言を受け取った日本では、ポツダム宣言に天皇の地位について記載がなかったので、政府と統帥部のなかで大論争が起こりました。大統領は、日本が受諾できない文面を作成したと見られます。原爆を投下するためには、ポツダム宣言は日本によって
一度拒絶される必要があったのです。
ポツダム宣言が発せられてから2日後の7月28日、鈴木首相はポツダム宣言について「重視する要なきものと思う」と述べたところ「政府は黙殺」という記事が朝日新聞に掲載され、世界のメディアは「日本はポツダム宣言を拒絶した」と間違って伝えました。これで米国は原爆を投下する口実を得ました。
8月6日、「リトルーボーイ」(おちびちゃん)と命名された1個のウラン型原子爆弾を搭載したB29爆撃機
「エノラ・ゲイ」がマリアナ諸島のテニアン島を離陸、日本時間の午前8時15分、第一投下目標の広島市の市街中心部に投下しました。原爆は上空533.4メートルの地点で爆発し、巨大なキノコ雲が立ち上りました。これにより、20万人が死亡しました。
長崎に「ファットマン」(太っちょ)と名づけられたプルトニウム型原子爆弾が投下されたのが8月9日の11時2分でした。約14万人が死亡しました。2つの原子爆弾による昭和25年(1950)10月までの犠牲者の数は約34万人となります。
(注:緑色は「ソ連参戦と戦争終結」P393にある文章です)
真岡(まおか)郵便電信局事件 P397~P399
昭和20年8月15日には対米戦争は終結しましたが、日ソ中立条約を破って8月9日に参戦したソ連の攻撃は続きました。ソ連は北海道を占領することを目指していたのです。ソ連軍は満州、南樺太、千島列島を次々と占領していきました。
当時、南樺太には40万人以上の日本の民間人がいました。南樺太第二の都市である真岡へのソ連軍の上陸作戦が始まったのは8月20日早朝でした。当時の真岡は北海道への引き揚げ拠点となっていて、1万5000人以上の日本人がいました。市街地に布陣すると市民を巻き込む危険があるため、日本軍はいっさいの発砲を禁じて内陸の山中に後退していました。しかし、ソ連軍は容赦なく霧の真岡に艦砲射撃を実施して上陸し、無差別に民間人を殺傷して真岡を占領しました。
当時、電話交換業務を担っていたのは真岡郵便電信局に勤める若い女性職員たちでした。現在、電話は自動で接続されますが、当時は交換手
が手動で回線をつないでいました。電話交換業務は、戦闘中でも継続する必要があり、8月16日に残留組を募りました。ところが多くの職員が志願したため、家族と相談してから申し出るように指示し、その日は決めませんでした。残留組20名が決まったのは17日のことです。その他の局員は疎開させました。8月19日からは非常態勢が敷かれました。交換業務は昼夜を通して行われるため、従来は三交代制でしたが、この日から二交代制に変更されました。19時からは夜勤体制になり、高石ミキ班長以下11名の女性が当直しました。
そして迎えたのが運命の8月20日早朝です。ソ連軍の艦砲射撃が始まると、身内の安否を確認する市民らがいっせいに交換台を呼び出し、交換手たちは業務を遂行していきま
した。真岡郵便局は平屋の本館と二階建ての別館があり、電話交換業務は別館の二階で行われていました。ソ連軍の攻撃が激しくなり、真岡郵便局も被弾するようになると、別館二階に女性交換手12名が孤立することになりました。
そして、ついに最期を悟った交換手たちは、自ら命を絶ったのです。真岡の北に位置する泊居(とまりおる)郵便局にお別れの連絡がありました。泊居郵便局の職員たちは「死んではいけない」と叫びつづけましたが、受話器越しに激しい砲声のなかから聞こえた「もうどうにもなりません。みなさん、さようなら。さようなら」という言葉を最後に連絡が途絶えました。持ち場で倒れていた者も多く、後日遺体を引き取りに行った上田局長は「職務に対する責任感を見たように思った」と述べています。17歳から24歳の若い女性職員9名が亡くなりました。これが真岡郵便電信局事件です。ソ連軍の攻撃で犠牲になった職員を含めると、真岡郵便局の殉職者は19名にのぼります。この戦闘で死亡した真岡の住民は約1000人です。
交換手たちは、自分たちの仕事の重要性を認識していたのでしょう。それゆえ自ら残留を希望し、ソ連軍の攻撃が近づくなか、恐怖に震えながらも職務を遂行したのだと思われます。しかし戦争は、そのような使命感に燃える若者たちの尊い命を、いとも簡単に奪ってしまうのです。この逸話は、私たちに戦争の本当の恐ろしさを教えてくれているのではないでしょうか。
昭和43年に北海道稚内市をご訪問になった昭和天皇と香淳皇后は、樺太が見渡せる高台で北に向かって
深く拝礼し、和歌をお詠みになりました。そこには御製碑があります。
(昭和天皇 御製)
樺太に命をすてしたをやめの
心を思へばむねせまりくる
(香淳皇后 御歌)
樺太につゆと消えたる乙女らの
みたまやすかれとたゞいのりぬる
それから66年後の平成23年(2011年)に発生した東日本大震で、宮城県南三陸町の防災無線を担当していた若い女性職員が、津波が押し寄せるその瞬間まで避難を呼びかけ殉職した話を第六章二項にコラムとして掲載していますので、読み比べてみてください。
昭和天皇と香淳皇后の和歌は稚内公園にある行幸啓記念碑に刻まれています。
2011年8月21日に稚内公園を訪問した際に、行幸啓記念碑・九人の乙女の碑等を写しました。
こちらでご覧ください → 日本の風景 北海道 稚内公園